NHK日曜美術館、
『20世紀との対話 ~森村泰昌の創作現場~』を見ました。
森村泰昌さんは、有名な絵画や写真の人物に扮して自分自身を撮影する
「セルフ・ポートレイト」と呼ばれる手法の作品を創作されています。
森村さんの作品は、以前に雑誌などで、
マリリン・モンローなどに扮した写真を見た記憶がありますが、
まあ、名前を知っていた程度です。
NHKの日曜美術館という番組は、一人の作家や作品を取り上げて
研究者やその作家・作品を愛する著名人などをゲストに向かえ
スタジオトークを交えながら紹介する回もあれば、
一人の作家が作品を創る過程に密着する回もあります。
私は作家が自作について語るのを聞くのが好きではありません。
「作品を解釈する自由」を奪ってしまうからです。
今回の番組は後者なのであまり期待していなかったのですが、
ある意味、稀にみる意義深い番組でした。
ロシア革命の指導者・レーニンが赤の広場で労働者達に演説する写真をモティーフに、
森村さんの出身地である大阪の「あいりん地区(釜ヶ崎)」でレーニンに扮した
『なにものかへのレクイエム(夜のウラジーミル 1920.5.5-2007.3.2)』
という作品についてです。
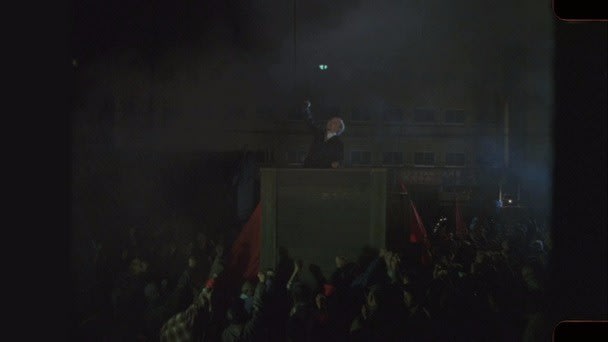
夜のウラジーミル

なにものかへのレクイエム
写真はレンブラントの歴史画のような崇高なイメージに仕上がっています。
実際に釜ヶ崎で暮す労働者達を雇って作品は創られていますが、
それに対して、番組アナウンサーの中條誠子さんが
「失礼な言い方かもしれませんが・・・」と断わりながら
次のような疑問を作者にぶつけます。
釜ヶ崎で日々、必死に暮す人達がいる。
森村さんはそこで芸術作品を創るために照明を焚いて写真を撮る。
そしてその作品を我々は美術館に行って鑑賞する。
その事に対してとても複雑な思いが沸いてくる・・・
というような質問です。
それに対して森村さんは、
自分と彼等が全く違う立場だということをひしひしと感じる。
あそこ(釜ヶ崎)に行かなければなにも問題はない、
なにも起こらない、だけれども私はあえてそこへ行く。
この作品が彼等のためになる、などとは全く思っていない・・・
でも私はこの作品が創りたい。
自分は芸術家であるから自分の仕事は"美"を生み出すことだ。
というようなことを、きっぱりと答えます。
"芸術とは何か、美とは何か"という素朴な問いを、こういった「美術番組」の中で
作者に伝え、本音の答えを引き出す場面はめったにありません。
いい番組だったと思います。
"予定調和"ではない、この質問をした中條アナウンサーも凄いと思います。
『20世紀との対話 ~森村泰昌の創作現場~』を見ました。
森村泰昌さんは、有名な絵画や写真の人物に扮して自分自身を撮影する
「セルフ・ポートレイト」と呼ばれる手法の作品を創作されています。
森村さんの作品は、以前に雑誌などで、
マリリン・モンローなどに扮した写真を見た記憶がありますが、
まあ、名前を知っていた程度です。
NHKの日曜美術館という番組は、一人の作家や作品を取り上げて
研究者やその作家・作品を愛する著名人などをゲストに向かえ
スタジオトークを交えながら紹介する回もあれば、
一人の作家が作品を創る過程に密着する回もあります。
私は作家が自作について語るのを聞くのが好きではありません。
「作品を解釈する自由」を奪ってしまうからです。
今回の番組は後者なのであまり期待していなかったのですが、
ある意味、稀にみる意義深い番組でした。
ロシア革命の指導者・レーニンが赤の広場で労働者達に演説する写真をモティーフに、
森村さんの出身地である大阪の「あいりん地区(釜ヶ崎)」でレーニンに扮した
『なにものかへのレクイエム(夜のウラジーミル 1920.5.5-2007.3.2)』
という作品についてです。
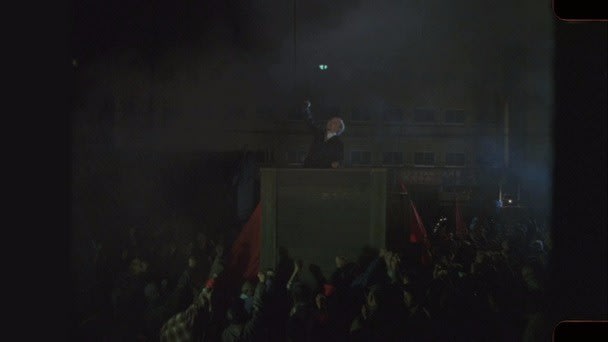
夜のウラジーミル

なにものかへのレクイエム
写真はレンブラントの歴史画のような崇高なイメージに仕上がっています。
実際に釜ヶ崎で暮す労働者達を雇って作品は創られていますが、
それに対して、番組アナウンサーの中條誠子さんが
「失礼な言い方かもしれませんが・・・」と断わりながら
次のような疑問を作者にぶつけます。
釜ヶ崎で日々、必死に暮す人達がいる。
森村さんはそこで芸術作品を創るために照明を焚いて写真を撮る。
そしてその作品を我々は美術館に行って鑑賞する。
その事に対してとても複雑な思いが沸いてくる・・・
というような質問です。
それに対して森村さんは、
自分と彼等が全く違う立場だということをひしひしと感じる。
あそこ(釜ヶ崎)に行かなければなにも問題はない、
なにも起こらない、だけれども私はあえてそこへ行く。
この作品が彼等のためになる、などとは全く思っていない・・・
でも私はこの作品が創りたい。
自分は芸術家であるから自分の仕事は"美"を生み出すことだ。
というようなことを、きっぱりと答えます。
"芸術とは何か、美とは何か"という素朴な問いを、こういった「美術番組」の中で
作者に伝え、本音の答えを引き出す場面はめったにありません。
いい番組だったと思います。
"予定調和"ではない、この質問をした中條アナウンサーも凄いと思います。




















