武州下原(現在の東京都八王子市付近)鍛冶の祖である刀工周重(ちかしげ)
について、得能一男先生の一書には以下のような説明がある。
周重初代(ちかしげ) 享禄-武蔵
「周重」「武州住周重」山本但馬。はじめ滝山住、のち下原に移る。下原鍛冶の祖。
周重の出身と鍛冶の伝系についてはいろいろにいわれているが、作刀ならびに
山本家の資料から推して、下野の得次郎派の刀工で相州鍛冶との交流があった
と思われるので、北条家が越後上杉家と野州、相州から鍛冶を集めた時の鍛冶の
一人であったと推定される。作刀は田舎臭のある相州傍系鍛冶の作とみられる
もので、板目に大肌がまじって地沸がつき、白気ごころのあるものもある。地肌に
「如輪杢」と称する渦巻き肌のあらわれるのが下原派の特徴とされているが、初祖
周重の作刀にもすでにそのきざしが認められる。刃文は直刃または直刃に小のたれ、
小互の目まじり、小沸がついて匂口が沈むものが多い。茎の形は千子村正の影響
をおもわせるようなたなご原茎になり、先は丸山形、あるいは浅い刃上がりの栗尻
になる。
周重二代(ちかしげ) 永禄-武蔵
「武州住周重」但馬周重の長男。山本藤左衛門のちに内匠。北条氏康より康の字を
賜り康重に改銘。初代康重同人。永禄、天正ころ。作刀は父に似て、互の目乱れが
多くなっている。

なぜ相州伝系の刀の茎(なかご)は先が優美に細くなっているのか。
中途から急激に細くなって腹が張ったような形はタナゴ腹といって、
伊勢国の村正(文亀年間。三代村正は天正)が得意とする形状
だった。二代目村正はさらにタナゴ腹が強い。
相州物では国宝の名物亀甲貞宗なども先が細い優美な姿となって
いる。備前物も末物になると茎が短く片手打ち用となり茎尻が異様に
張ってくるが、古備前などはそれほど張っていないやはり優美な姿だ。
(国宝 亀甲貞宗。鎌倉時代。五郎入道正宗の弟子もしくは子とされている)
また、まったく相州伝系ではない鍛冶の作でも相州茎のように茎尻が
細くなっているものもある。
(安藝國住仁宗重作 天正八年二月吉日)
(所有者:私/撮影町井勲氏) クリックで拡大
クリックで拡大
古刀の若州冬広や新新刀元興のように相州伝系の刀工作が先が細い茎尻
であるというのは伝系なので頷けるが、このように周防二王・備後三原系と
思われる作風の刀でも、茎だけは相州物のような作もある。
ただし、冬広四代目(永禄~天正)の又次郎(藤左衛門)は備中松山城主三村
元親の招きにより備中松山に移住し、天正ころには備後にても鍛刀したとの
記録があるようだ。
私は一時期、末古刀である四代目冬広を使っていたことがあったが、茎尻は
結構細かった。細いというよりも、あまり張らないタナゴ腹のような形だった。
そして注目すべきは、四代目冬広は「備後にても打つ」という経歴があることだ。
端的に言えば、私の手元にある天正年間の四代目宗重(天正年間)の茎の形状
は極端に四代目冬広に酷似している。備後と藝州は隣国であり、安芸国大山は
備後三原からは距離にして13里だ。江戸日本橋から戸塚宿まで10里半で42km。
当時は大よそ10里が1日の旅の行程(40km)だったので、13里となると2日
行程となるが、速足ならばどうにか1日で行ける距離だろう。
また、冬広には藝州冬廣としての藝州打ちの記録も作も残っている。ということは、
戦国末期の藝州打ちは、まだ広島城はなかったので、藝州内の鍛冶職のところに
身を寄せて駐鎚した可能性が高い。
藝州大山住の宗重の作が末三原の作風と酷似している点、また西の隣国二王
一派とも作柄に共通項が非常に多い点、そして、若州冬広四代目の備中松山、
備後、藝州での鍛刀。これらは、まったく同時代、同時期、同地域にいた鍛冶職
という共通項があるので、なんらかの技術的な交流等があったのではなかろうか。
藝州大山宗重四代目延道彦三郎は元々の遠祖は筑州左の流れだが、左の作柄
よりも周防二王派や備後三原派に作柄がよく似ており、そして、茎の形は冬広に
酷似している。
四代目冬広(永禄)
ただし、この時期、天正頃の末古刀には他の地方でも茎尻が細くなる物が
みられる。
美濃関三阿弥派の兼春(弘治)の子兼春の門人で加州に移住した炭宮の
竹右衛門兼春(加州兼春初代、天正)もまた、茎尻が細くなる造りとなって
いる。
やはり末備前の茎尻は一般的ではないイレギュラーな
ように思える。
片手打ちの時代の形状としては刀身バランスを保つ
ために尻側を張らせて重量と堅牢さを持たせる形状
だったことだろうと思えるが、その後、両手刀法の登場で
段々刀身が伸びるのと同時に末備前の茎長さも伸びたの
だが、片手打ちの頃と同じ尻の張ったいわゆる「備前茎」
のままであった理由を私は知らない。
左の永正時代の片手打ち形状(長二尺一寸、則光)から
両手操法が普及し始めた天文年間の備前茎は刀身と共に
茎長さも伸びた。
また、この頃から二つ目釘が多く見られるようになる。
目釘の折損および抜け防止のための「保険」として二つ
目釘仕様は登場したのだろう。
太刀・刀が補助武器ではなく、十分に使用することを前提に
再設計されたのだろうと思われる。
(右の刀2口はそれぞれ二つ目釘仕様の末備前則光)
ただし、安芸国大山(おおやま)の宗重と西の隣国二王の作は
要所要所で酷似するが、二王の茎は末備前物のように尻が張って
いる。古備前が茎尻が細いのを勘案すると、うぶ茎において茎尻が
張るのは周防国二王の作の方が歴史が古い。
後に二王は金剛兵衛のように茎尻を卒塔婆形に近い剣形に成形する
者も現れるのだが、総体としてうぶ茎の茎尻はデンと張っている。
備前茎(末備前)よりも歴史が古い鎌倉時代に二王はすでに茎尻を
張らせていたのだから、尻が張る茎を「二王茎」と呼んでも良さそうな
ものだが、刀剣界には備前第一主義があるからか、そうした呼び方は
存在しない。
ごく個人的な私見としては、強烈な斬撃による衝撃を逃がす
ためには、茎尻はだんだんと細くなっていったほうがよいの
ではなかろうかとは思うが、実験をした訳ではないので確かな
定見を私は持たない。
刀剣製作は造形においても意味のないことは絶対にしないので、
茎尻を張らせるのも、何らかの意図と工夫があったのだろう。
二王と作域は酷似する安芸国大山宗重だが、茎の形状は
二王系ではなく冬広系であるといえる。
私の宗重は天正八年の作だが、茎形状は冬広との交流が
あったからか、冬広のように洗練された形状となってはいる
ものの、片手打ち時代の名残か、かなり長さは短いままで、
その上刀身は二尺三寸四分となって片手打ち時代の二尺一寸
標準からすると長めであり、丁度日本刀の刀身形状変化の
いく度目かの過渡期にあった刀身であることが見て取れる。
その後、戦乱が終了した頃からは、懐古主義的な思想が
広まり、南北朝時代の太刀を磨り上げた形状を写すという
いわゆる「慶長新刀」姿が登場する。
これは戦乱が終わってなお武骨武辺を自己主張の盾としたり
傾(かぶ)くことにより憤懣を表現したりした武士たちに好まれた。
元幅と先幅の差がない身幅で鋒も延びるダンビラ調が当時の
武士たちに好まれた。不人気な物は作られはしない。
完全に実用を離れて「見た目」から入る日本刀が初めて武士用の
刀剣としての日常差しとして歴史上登場したのだが、これこそが
まさしく「新刀」の日本刀の性格付けを成す端緒そのものであった
といえることだろう。
それまでは、平安初期の直刀から平将門の乱での湾刀の多用
による戦果をふまえて湾刀=いわゆる後世でいう日本刀(明治
以降の呼称)という太刀が登場した。大刀(たち)・横刀(たち)は、
反りを得て太刀となった。
遠く平将門の蜂起の頃から慶長までは、日本の太刀・刀はずっと
戦時戦闘武器として形状が模索され改良に次ぐ改良で、かなり
姿の変化を見せた。
だが、いわゆる「慶長新刀」が初めて「容姿から入る」という設計
思想を現出させた。
戦乱は終わったからだ。
過去に存在した刀を援用するのではなく、新作刀としての美術刀剣
の登場は、いわゆる「慶長新刀」が嚆矢だったのではなかろうか。
面白いのは、江戸期に入ってからは、やはり刀身の姿の変化が
みられることだ。
ただし、幕末刀は水心子の復古刀論によって古刀の再現が
試みられたが、意外とイメージしているような、南北朝様式の
ような大ダンビラ大鋒の刀身はそれほど多くもなく、一般的でも
ない。圧倒的に「普通の形状」の刀剣のほうが多かったという
事実がある。
それなのに、幕末に登場した再現南北朝のような形状が幕末刀
の一般形状であるかのように扱われるのは、その時代の決して
マジョリティーではなかった刀剣を時代の代表選手のように据えた
という点において、私は多少面白い視点だなと感じている。
それはあたかも、ありもしない「慶長新刀」という新刀が存在したかの
ように創作した、いつもよくやる鎌田魚妙などの作戦勝ちに似たような
ものを感じるからだ。
第一、「古刀」と「新刃(あらみ)=江戸時代当時の現代刀のこと」と
いう言葉も概念も作られたものだから。
あまり言葉上のレッテルにのみこだわっていると本質は見えないと
思う。
縄文時代も弥生時代も、後世に便宜上つけた名称であるし、縄文
時代にすでに栽培や稲作が行なわれていたことは最新の科学的
解析で判明してきたのだし。倭人は中国大陸のある地方から列島と
半島南部にやって来て居住したということも、稲作は半島からの
輸入ではなく、九州から半島南部に輸出したものであるということも。
日本刀の解釈も、科学的メスが入る以上、より適切で妥当性を有する
解釈に時代と共に変化して行くのが自然なあり方なのではなかろうか。
日本刀(という言葉自体が明治以降に中国語から援用されたものだが)
の概念も、「五箇伝」だけで網羅はできない。
五箇伝にしても、後世の人間が、識別しやすいように、縄文-弥生と
同じように、あくまで便宜上弁別するために区分けしたものであるし、
土地の行政管轄のような仕切りや区分けが存在した訳ではない。
相州伝と呼ばれる鎌倉刀工は自らは「相州伝」であるとは認識して
いなかったことだろう。鍛刀地が相州である、というだけだ。
これは、九州も、中国(なかつくに)の備州(備前備中備後)も美濃も
武州も同じで、地域の工業的特産物として刀工群はあったことだろう。
刀剣学習において、系統分類的に五箇伝という便利な区分けを用いる
のは識別が楽だが、五箇伝至上主義に陥ると、五箇伝以外は刀では
ない、とかいうような意識が発生し、目を曇らせる。
さらに、五箇伝の中でさえ、大和伝を格下に見ようとしたりするような
穿った視点がいつの間にか醸造されてしまう危険性がある。
冒頭に紹介した得能先生の一文でさえ、下原鍛冶を「田舎臭のある相州
傍系鍛冶の作」と断じてしまっている。下原鍛冶の作の茎は相州貞宗に
迫る見事な形状を成しているにもかかわらず、だ。要するに上(かみ)の
出来が、相州伝「上位」刀工にどれだけ近いかという美術刀剣目線でしか
下原鍛冶を見ていないし、下原鍛冶の特徴である「匂い口沈む」ということ
が、実用刀剣上どのような効果をもたらしたかには目が行かない。
刀剣の実用的見地で気を吐いた得能先生でさえこれなのだ。
このような刀剣界では一般的な視点に依拠して、九州肥後菊池の同田貫
派はかつては超格下の拙劣刀と美術刀剣界では見られていた。「ただの
頑丈な物斬り刀」と。
それに光明を与えて世間の見方と人気をひっくり返したのが劇画『子連れ狼』
に始まる胴太貫(ドウタヌキ)なる架空刀だった。
肥後同田貫(どうだぬき)に名称の音韻が似ていたから、人々は誤認によって
主人公拝一刀が使う斬鉄刀に魅了された。
世の中の人は、拝一刀の刀は九州肥後同田貫だと誤認して、異様な
ほどに肥後同田貫の人気が高まった。
ドラマに主演した俳優の萬屋錦之介氏が個人的に肥後同田貫を買い占め
たのも市場効果の爆発的高騰をもたらした。
だが、劇画『子連れ狼』の主人公元公儀介錯人の拝一刀が使用した
胴太貫は肥後同田貫ではない。まったく架空の尾張の刀なのである。
↓証拠はこれ。(原作『子連れ狼』の「山田朝右衛門」の回のトビラ絵から)
山田朝右衛門と対決した拝一刀と山田朝右衛門の刀のなかご図
拝一刀の胴太貫(どうたぬき)は尾張の清水甚之進信高(実在)の作だった!
これには中学生の時に騙されましたよ。清水甚之進が胴太貫であるという資料を
探しまくっても資料がない。
あるわけがない。清水甚之進は尾張の刀鍛冶、本物の同田貫(どうだぬき)は
肥後菊池の刀鍛冶で延寿の流れなので、京の来派が始祖になる。
「子連れ狼」の刀が実在の肥後同田貫とは別物の架空の刀という設定だった
のを知らなかったから、すっかり実在の清水甚之進が同田貫作者の直系だ
とか私は中学生の時に思い込んでた。おかしいなぁとは思いながらも、歴史の
事実と架空のエンターテイメントの境目が解っていなかった。
胴太貫と銘した信高の作品って見たことないなぁ、探しても資料が出てこない
なぁ、甚之進が肥後に習いに行って名称をもらったのかなぁなどと突拍子も
ないことを中学の頃には思って悩んでいた。
上記画像のトビラ絵の右の刀(劇中での山田朝右衛門の差し料)は、実は
柳生連也が好んだ秦光代の鬼の包丁というこれまた実在の脇差を、政勝
という実名の尾張藩士が好んで清水甚之進に作らせた物だ。
つまり、『子連れ狼』で戦った拝一刀と山田朝右衛門の刀は、左右両方とも
尾張柳生に好まれた清水甚之進信高の作という訳なのです、現実は。
このトビラ絵は劇画の旧版では掲載されているが、新版のコミックスでは削除
されている。
他のマニアの人たちも40年前から知ってはいたのだろうが、ネット上で
このことに言及して10年ほど前に公開したのは私が初めてかと思う。
それにしても、拝一刀の胴太貫も山田朝右衛門の鬼包丁も、この絵を見ると
短きに過ぎる茎だ。二尺一寸ほどの片手打ちの時代の古刀然としている。
しかし、これまたコアなマニアネタなのだが、劇画『子連れ狼』では、最初は
片手打ち用の二尺程の短い刀として拝一刀の「胴太貫」は紹介されて登場
している。
それが、話が進むうちに、どんどん寸が延びてきた・・・。
まあ漫画ではよくある話だが、このトビラ絵は、連載当初の設定を刀剣学的
にはきちんと反映している茎(なかご)の形状だといえる。片手打ち時代の
古刀のような長さにはこうした短い茎の刀が多いからだ。
日本刀の鑑賞は「当て鑑定」が多いため、どうしても区(まち)より上の
刀身部分のみに目が行きがちだ。
だが、茎こそ外装の柄に納まり、柄こそ唯一使い手の人間と接する部分で
あるので、非常に大切なのだ。上(かみ)の実用上の性能を左右するほどに
茎の在り方は重要なのである。
しかし、実用的観点からの日本刀研究というのは、第二次世界大戦後は
希薄な分野であるので、美術刀剣論者たちは茎の形状についての説明に
長けてはいない。
茎の在り方、形状、茎錆の着け錆の意味等については、総合的に日本刀を
解析するという視点に基づく、斯界のこれからの新しい研究分野であるように
思える。
茎ひとつから見えてくるものもある。
それを紐解くのも、また刀を愛でる楽しみかな。
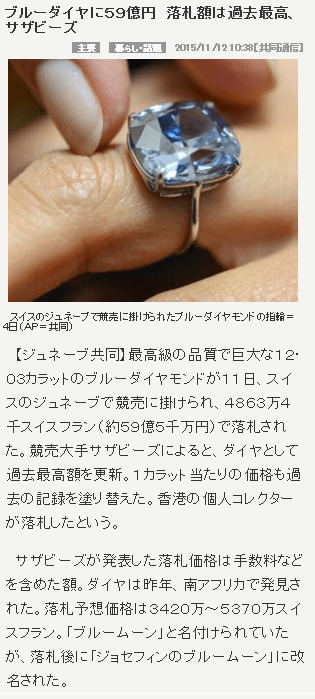
まあ、それくらいはするのだ
ろう。
ピンクダイヤの原石4億円、
カットして20億円のダイヤが
国際宝飾店で見せしめとして
エージェントに盗まれたり、
本社社屋に.22ロングライフル
の銃弾撃ち込まれたり、こち
とらの搭乗したヘリを南ア傭
兵が撃墜しようとしたり、ま
ったくもってシャレにならな
いんだよね。こちらも別動傭
兵部隊でという手もあったが、
大局的に見て方針は変更した。
「サイト」だけでなく、身体
生命に関する恫喝はとんでも
ないものがあったから。
巨大国際ダイヤ・コングロマ
リットに刃向って世界市場に
風穴を開けようとしたりする
と、ホントに消されることに
なる。
国際宝飾展での巨大ダイヤ盗
難はICPOが動いても良さそう
なもんだが、日本警察なんて
のはそうそうに捜査打ち切り
よ。
そりゃあ、ガバメント通しで
世界を牛耳る巨大資本が裏で
圧力かけてるんだから、大人
の大人過ぎる事情ってやつだ
よな。
俺はこうして生きているけど、
闇から闇へ消されているの一
杯いるんじゃないの?
映画『ブラッドダイヤモンド』
は、あれ、実話だから。
ただの炭素の塊の石なのに、
なんというか・・・。
スィートテンダイヤモンドと
か、婚約や結婚にはダイヤと
か、日本人は結納制度に目を
付けた某資本に食い物にされ
ている
のだということの自覚は無い。
キンバリーができる前は、ほ
ぼ全域紛争ダイヤだというの
に。
血に塗られたダイヤで何がお
祝いなもんか。
それでも、命あってのものだ
ね、だねってね。
宝飾用ダイヤなんてのは、人
を殺して、アフリカの大地を
血に染めて手に入れてるのだ
ということを(本当にそう)、
日本人はきちんと知ったほう
がいい。ロシアにしてもヨシ
フによって鉱山強制労働で多
くの人民が殺されたというこ
とも。
そして、価格なんてのも、実
は世界を牛耳る英国に本部が
ある南ア某資本が操作して相
場は作られているのだという
ことも。あれは宝飾ではなく
虚飾なんだと。
ナインスロージュナ!ドゥラ
ーク!ってやつさね。
(露天掘り鉱山の真下まで行く
のには巨大トラックで数時間か
かる。
当時、サハの国民の平均寿命は
33歳だった)
















