9月16日、長正館一刀流稽古
9月17日、長正館月例稽古
9月20日、長正館剣道稽古
8月21日、木曜会(誠先生の剣道教室)
9月23日、長正館一刀流稽古
9月27日、長正館剣道稽古
9月30日、往馬玄武会
9月30日、一刀流の稽古は休みにして有志で暑気払い
9月28日、木曜会(誠先生の剣道教室)
10月4日、長正館剣道稽古
10月5日、木曜会(誠先生の剣道教室)
--------------------------------
9月16日、長正館一刀流稽古


(写真でO野先生が足を崩しているが膝の故障のため)
毎週土曜日の稽古で、第1と第3は大太刀中心の稽古としている。
乗突、乗身、折身、本生、切返、地生之合下段、引身之本覚については、
この一年で部分的に変更したので重点的に注意深く指導した。(つもり)
長正館の一刀流はこの数年でかなり質が向上してきていると思う。
--------------------------------
9月17日、長正館月例稽古(前半は一刀流)

まずは、二つ之切落~張合刃までの稽古。
張合刃は長正館で伝わっている形と禮楽堂では若干異なるので両方の説明。

あとは小太刀の触りだけ稽古。
小太刀での半身から、一重で入り身になる部分、と小太刀での切落しの稽古。
--------------------------------
9月17日、長正館月例稽古(後半は剣道、奥で一刀流)

ともかく異常に暑いので、軽く基本稽古、あとは2分の回り稽古一回。
奥では、引き続いて一刀流の自主稽古がされていた。
--------------------------------
9月20日、長正館剣道稽古

最初の30分、基本稽古の時間は私は初心者のHちゃんの指導。
Hちゃんは素質があり、一ケ月経ってないのにもう打ち込みも切り返しも出来る。
こういう子は指導していても楽しい。
稽古には回り稽古から参加。足が痛い。
この日の稽古で三段受審予定のM女史が左手親指骨折。
下手な受け方をしたのか、変なところを力強く叩いたのか・・・
おかげで10月9日の審査はパスして11月に持ち越し。
怪我は禁物。全員で気をつけたい。
--------------------------------
8月21日、木曜会(誠先生の剣道教室)

最近は、基本の面打ちに加え、摺り上げ技と返し技の稽古が中心。
足の故障で飛び込めない身には願ったり叶ったりである。
一つでも身につけたいものである。
--------------------------------
9月23日、長正館一刀流稽古

この日は刃引と払捨刀の稽古。
特に刃引は一つ一つの理合を丁寧に説明する。
以前の長正館では、摺込と摺上の違いが不明確だったのだ。
あとは裏切と拳之払。これは分解して理合を説明。速く遣うと意味がわからなくなる。
古流は大きくゆっくり遣うのが原則だと思う。速く遣うのはあとからでOK。
--------------------------------
9月27日、長正館剣道稽古

準備運動+素振り。
写真は跳躍素振りに入る手前のHちゃん。構えもしっかり出来ている。
このあとHちゃんへの指導を張り切ってしまい、足の痛みが増してきた。
後半の回り稽古は無理かも知れない。

回り稽古は打たせる稽古に徹した。打つ気を見せて打たせる稽古。
私の右足。数人との稽古だけなら何とかなるが、回り稽古を続けていると足の痛みがひどくなる。
--------------------------------
9月28日、木曜会(誠先生の剣道教室)

この日も技の稽古。
写真は「三殺法」の話。相手の「気を殺し剣を殺し技を殺す」。
いまの自分に一番欠けている話だと痛感した。
--------------------------------
9月30日、往馬玄武会

超ひさびさの往馬玄武会の稽古。
この日は休まれた方も多く4人で稽古。
--------------------------------
10月4日、長正館剣道稽古

いつも通り、基本稽古中はHちゃんの指導。
後半は審査を控えた4人には審査的な稽古。
骨折した看取り稽古のM女史にも看取り稽古のノウハウを説明。
写真は、初段審査のN崎君に「刺すような面をするな」と改めて言ってるところ。
彼は部活で教えられたのか、右手を伸ばしてこすりつけるような面を打ってしまう。
刺し面とも、かすり打ちとも言うのだろうが、左拳を上げなければ刀法では無い。
刀法を無視した剣道は剣道では無くなると思う。私が審判なら旗は上げない。
--------------------------------
10月5日、木曜会(誠先生の剣道教室)

写真は終わりの礼。
この日は指導していただいた技の数がたくさんあって頭がパンパンで大混乱した。
指導の動画は会員で共有しているので後でオサライしなくては。
稽古は本数を重ねると足が痛くて動けなくなるので、隅っこで騙し騙しやっている。
まだまだ本格的には動けない。動けないので稽古相手にも迷惑をかけてしまって申し訳ない。
9月17日、長正館月例稽古
9月20日、長正館剣道稽古
8月21日、木曜会(誠先生の剣道教室)
9月23日、長正館一刀流稽古
9月27日、長正館剣道稽古
9月30日、往馬玄武会
9月30日、一刀流の稽古は休みにして有志で暑気払い
9月28日、木曜会(誠先生の剣道教室)
10月4日、長正館剣道稽古
10月5日、木曜会(誠先生の剣道教室)
--------------------------------
9月16日、長正館一刀流稽古


(写真でO野先生が足を崩しているが膝の故障のため)
毎週土曜日の稽古で、第1と第3は大太刀中心の稽古としている。
乗突、乗身、折身、本生、切返、地生之合下段、引身之本覚については、
この一年で部分的に変更したので重点的に注意深く指導した。(つもり)
長正館の一刀流はこの数年でかなり質が向上してきていると思う。
--------------------------------
9月17日、長正館月例稽古(前半は一刀流)

まずは、二つ之切落~張合刃までの稽古。
張合刃は長正館で伝わっている形と禮楽堂では若干異なるので両方の説明。

あとは小太刀の触りだけ稽古。
小太刀での半身から、一重で入り身になる部分、と小太刀での切落しの稽古。
--------------------------------
9月17日、長正館月例稽古(後半は剣道、奥で一刀流)

ともかく異常に暑いので、軽く基本稽古、あとは2分の回り稽古一回。
奥では、引き続いて一刀流の自主稽古がされていた。
--------------------------------
9月20日、長正館剣道稽古

最初の30分、基本稽古の時間は私は初心者のHちゃんの指導。
Hちゃんは素質があり、一ケ月経ってないのにもう打ち込みも切り返しも出来る。
こういう子は指導していても楽しい。
稽古には回り稽古から参加。足が痛い。
この日の稽古で三段受審予定のM女史が左手親指骨折。
下手な受け方をしたのか、変なところを力強く叩いたのか・・・
おかげで10月9日の審査はパスして11月に持ち越し。
怪我は禁物。全員で気をつけたい。
--------------------------------
8月21日、木曜会(誠先生の剣道教室)

最近は、基本の面打ちに加え、摺り上げ技と返し技の稽古が中心。
足の故障で飛び込めない身には願ったり叶ったりである。
一つでも身につけたいものである。
--------------------------------
9月23日、長正館一刀流稽古

この日は刃引と払捨刀の稽古。
特に刃引は一つ一つの理合を丁寧に説明する。
以前の長正館では、摺込と摺上の違いが不明確だったのだ。
あとは裏切と拳之払。これは分解して理合を説明。速く遣うと意味がわからなくなる。
古流は大きくゆっくり遣うのが原則だと思う。速く遣うのはあとからでOK。
--------------------------------
9月27日、長正館剣道稽古

準備運動+素振り。
写真は跳躍素振りに入る手前のHちゃん。構えもしっかり出来ている。
このあとHちゃんへの指導を張り切ってしまい、足の痛みが増してきた。
後半の回り稽古は無理かも知れない。

回り稽古は打たせる稽古に徹した。打つ気を見せて打たせる稽古。
私の右足。数人との稽古だけなら何とかなるが、回り稽古を続けていると足の痛みがひどくなる。
--------------------------------
9月28日、木曜会(誠先生の剣道教室)

この日も技の稽古。
写真は「三殺法」の話。相手の「気を殺し剣を殺し技を殺す」。
いまの自分に一番欠けている話だと痛感した。
--------------------------------
9月30日、往馬玄武会

超ひさびさの往馬玄武会の稽古。
この日は休まれた方も多く4人で稽古。
--------------------------------
10月4日、長正館剣道稽古

いつも通り、基本稽古中はHちゃんの指導。
後半は審査を控えた4人には審査的な稽古。
骨折した看取り稽古のM女史にも看取り稽古のノウハウを説明。
写真は、初段審査のN崎君に「刺すような面をするな」と改めて言ってるところ。
彼は部活で教えられたのか、右手を伸ばしてこすりつけるような面を打ってしまう。
刺し面とも、かすり打ちとも言うのだろうが、左拳を上げなければ刀法では無い。
刀法を無視した剣道は剣道では無くなると思う。私が審判なら旗は上げない。
--------------------------------
10月5日、木曜会(誠先生の剣道教室)

写真は終わりの礼。
この日は指導していただいた技の数がたくさんあって頭がパンパンで大混乱した。
指導の動画は会員で共有しているので後でオサライしなくては。
稽古は本数を重ねると足が痛くて動けなくなるので、隅っこで騙し騙しやっている。
まだまだ本格的には動けない。動けないので稽古相手にも迷惑をかけてしまって申し訳ない。










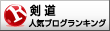

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます