今年もすでに3カ月が経過、なんとまあ月日の流れの速いこと!
今朝方、駅に向かう途中の公園では、桜が満開模様だった。
明日からは4月、新年度である。と言っても何か身辺周辺の環境が新しいことになるというようなことはまったくないのであって、次から次へと本を出していくのみという感じなのだが、せめて季節の移り変わりぐらいは感じ取りながら、生活していきたいと思う。
それにしても今日は暖かかった!
いよいよ昼寝の季節やねえ…。

今年もすでに3カ月が経過、なんとまあ月日の流れの速いこと!
今朝方、駅に向かう途中の公園では、桜が満開模様だった。
明日からは4月、新年度である。と言っても何か身辺周辺の環境が新しいことになるというようなことはまったくないのであって、次から次へと本を出していくのみという感じなのだが、せめて季節の移り変わりぐらいは感じ取りながら、生活していきたいと思う。
それにしても今日は暖かかった!
いよいよ昼寝の季節やねえ…。

昨日、梅田のヨドバシカメラ前で行われた「立憲主義を取り戻す関西市民連合」の街宣での冨田宏治先生のメッセージが、新刊ブックレット『「保革」を超えて、転形期を切り拓く共同を」(冨田宏治・著)の内容に、あまりにもピッタリだったので、ご紹介させていただきます。ぜひ、お聴きくださいね。
関西市民連合立ち上げ街宣での富田宏治先生のメッセージ
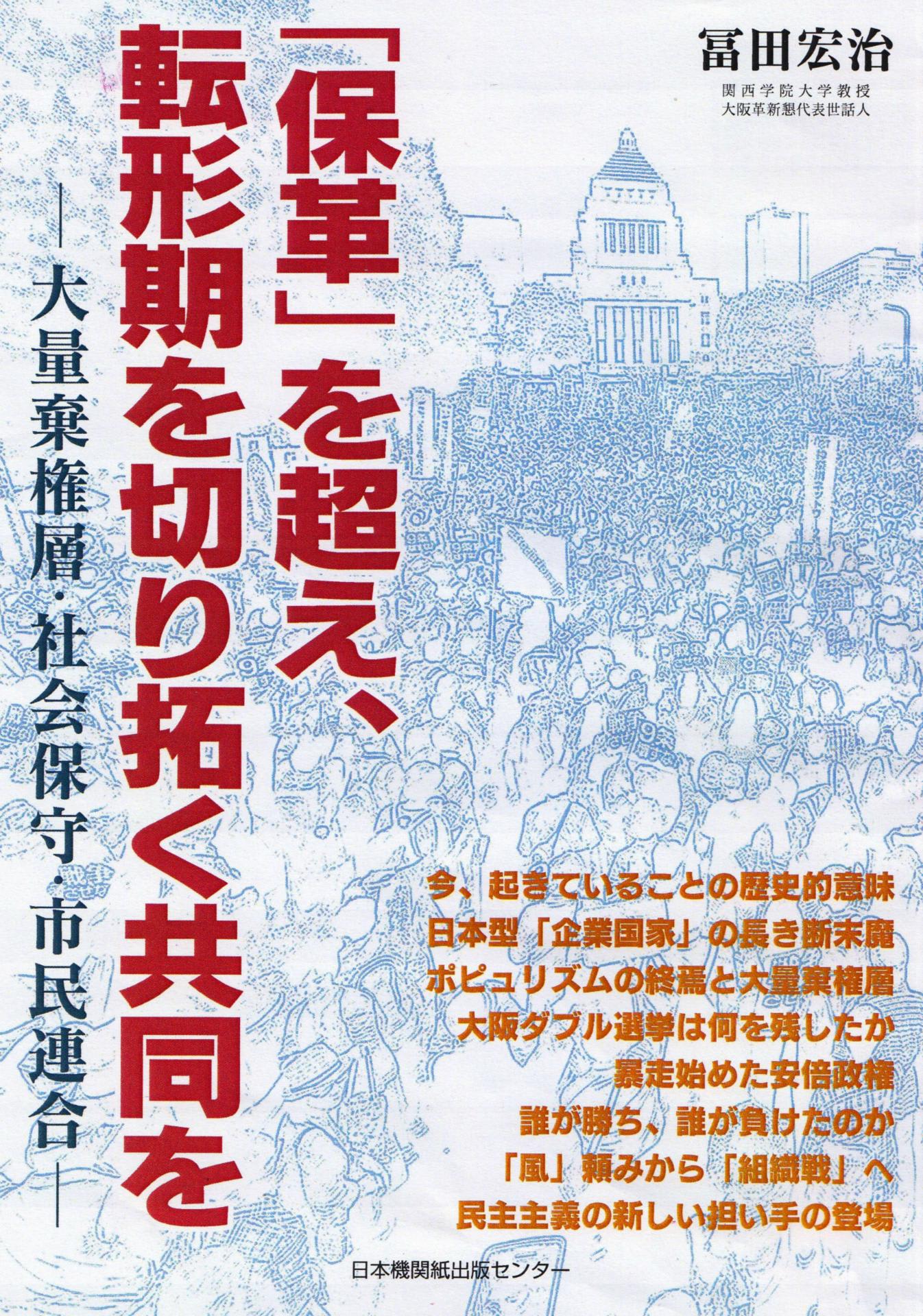
安保関連法案に賛成した落選対象議員を次々と政治資金規正法違反で告発する上脇博之さんの『追及!民主主義の蹂躙者たち』の書評を、「全国商工新聞」でいただきました。ありがとうございます。

聴いてもらえたら元気~子育て相談から①
いろんなところで子育て講座をさせていただいている。ご質問や相談を受けることも度々ある。今回から何回かに分けて、子育て相談を紹介したい。
と言っても私に的確な解決策が示せるわけではないが、とにかくみなさん胸の内を吐き出せて、聴いてくれた、と思うだけでほっとするようだ。
◎着替えが遅い
「もうすぐ一年生なのに、あれもできないと気になることばかりで、心配が絶えなくて…」
聞くと、衣類の着替えが遅い。近所の人に会っても挨拶もできない。つい「そんなことできなかったら学校に行かれへんよ」と怒鳴ってしまうと言うのだ。初めて我が子が学校に上がるんだから、わからないことだらけで心配するのは当たり前ですよ。私もそうでした。
大丈夫!衣類の着替えなんかみんなと一緒にするので、すぐにできるようになりますよ。挨拶ね、お母さんがご近所の方にニコニコ挨拶なさっていたら、そのうちするようになります。
入学前の禁句は「○○できなかったら学校に行かれへんよ」という言葉。学校というところはコワイところだという緊張感を与えてしまいますから。それよりちょっとお茶碗運んでくれたら「さすが一年生になるから頼りになるわ」と背中を押してやってください。
◎友達ができない
「二年生の女の子です。なかなか仲の良い友達ができなくて…。本人は友達ほしがっているんですけどね。親としてはどうしてやったらいいのかと…」
友達をほしがっている気持ちがあるのがいいですよね。二年生くらいだと特定の子と仲良くなるというより、その日その時でいろんな子と遊んだりしますからね。
四年生くらいになるとできますよ。親ができることは「友達つくりなさい」とやいやい言うことではなく、たっぷり愛情を届けてやることです。いっぱい抱いて、おいしいごはんを作ってあげてください。愛されて育った子は必ず人を自分の中に受け入れて仲良くできますから。(拙著『子育てがおもしろくなる話』参照)
◎うそをつく
「五歳の男の子です。うそをつくんです。どうしたら直るでしょうか」
ハハハハ…うそをつくのは、自分の身を守るためのちょっとした知恵が出てきたんですよ。すぐバレそうなうそでしょ。いちいちカーッとせず、う
そをつかれて笑っていてください。ときにはうその中に子どもの願いが込められてもいるので、そこに寄り添ってあげたいですね。
「おとうさんといっしょに公園でいっしょに野球してホームランを打ったよ」。「いっしょ」が2回も出てくる日記には(実はうそでしたが)この子の願いが込められていたのです。父ちゃんといっしょに公園で野球したいよ、ホームランを打ってみたいなという切ない願いです。うそをついたと叱るより、一緒に野球をしてやりましょと話したことでした。
◎自分から話さない
「先生が子どもの話を聞いてあげてくださいと言うのですが、うちの子、自分からなかなか話をしてくれません。どうしたら…」
私たち教師も同じですが、お母さんが忙しオーラやイライラオーラを出していると、近寄って来ませんよね。それにせっかく「あのね、今日ね…お弁当のとき…あのね」ともたもたでも話をしようとしているのに、話をとって「ああそれ、先生から聞いたよ」とやってしまうと、ますます自分から話さなくなります。
それにもまして一番の反省は、子どもの目を見て、話に共感してなかったなあと思いますよ。「ケンちゃんとこの犬な、めっちゃ賢いで。ぼくの言葉わかるんやで」と言っているのに、「はよ宿題してしまいなさい。もうごはんやで」とやっていませんか。
自分の方から「今日どんな勉強したの」と聞き出すよりも「お母さん今日うれしかったわ、種から植えてた椿の花が咲いたんやで。あれや、見てごらん、ホラ」と言うと、「ぼくもうれしいことあってん。ゆうちゃんがな『ぼくの絵うまいなあ』って言うてくれてん」と語り出すのです。そうです。大人も自分を語ることで、子どもも心を開くようです。
みなさん、こんな時代の子育てですから、悩みもいっぱい。いいのです。人を育てるってそんなもんです。子どもは思い通り育つ、子育ては楽だ、と言う人こそ危ないですよ。
(とさ・いくこ 和歌山大学講師・大阪大学講師)
秘密保護法、そして戦争法などをめぐるこの間のたたかいを通じてよく言われていることに、「日本の民主主義が新しい段階を迎えた」という表現があります。
それはいったいどういうことなのでしょうか。
そして私たちはこの新しい認識の上にたって、憲法改悪を真正面に抱える安倍政権に対して、これからどのような見通しをもち、取り組みを進めていけばよいのでしょうか。
論客の一人として、大阪の「都構想」をめぐる住民投票やダブル選挙のたたかいを支えた冨田宏治先生(関西学院大学法学部教授・大阪革新懇代表世話人)の、勇気が湧き、展望が見通せるとても親しみやすい講義をお読みください。
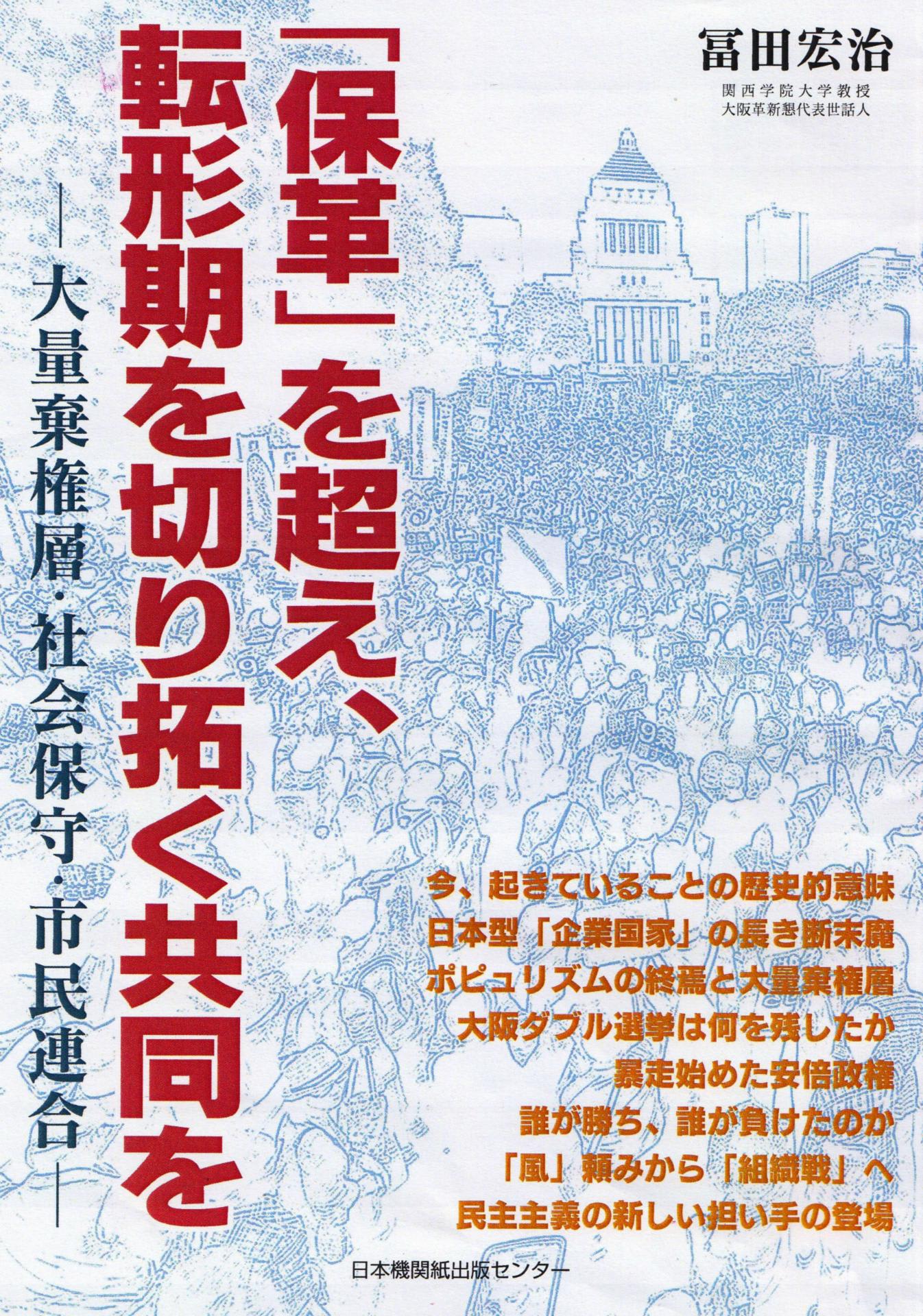
定価は本体800円。
3月18日出来予定!