今日は、1年生を対象に、LA科目という科目群の選択前に行うプレ授業を担当しました。
国際社会と日本、という科目です。
同名の科目を複数の教員が担当しております。ま、自分の授業内容をしゃべればいいということだったので準備していったのですが、いや、難しい。
だって、目の前にいる学生の関心がどこにあるのか、まったくと言っていいほど、手掛かりがないのです。
「日本語教育~」であれば、主専攻が何であれ、とにかく関心がある学生が集まっていると思えばいいのですが、「国際社会と日本」では、あまりにも漠然としています。
いきおい、「日本語教育を通してみた日本と国際社会のかかわり」という話も、聞いている学生さんの顔を見ながら、歴史の話が面白いかな、語学の話が面白いかな、教員養成の学生が多いのかな、理系の話のほうがいいのかな、などと頭の中がぐるぐるとしてしまいます。
当初、日本語教育の話をするつもりでしたが、突っ伏して寝る学生もいて、あんまり日本語教育に偏った話をしても面白くないか、と、授業で見せる映像の話に切り替えたりしましたが、やっぱり難しいですな。
うるさい!とか注意したり、なんか、いつもと調子が随分違いました。
聞く気がない学生さんに、焦点の定まらない話をするほど厄介なことはありません。
プレ授業を担当する先生方が大変な思いをなさっていることがよくわかりました。
何事もやってみるものですね。
国際社会と日本、という科目です。
同名の科目を複数の教員が担当しております。ま、自分の授業内容をしゃべればいいということだったので準備していったのですが、いや、難しい。
だって、目の前にいる学生の関心がどこにあるのか、まったくと言っていいほど、手掛かりがないのです。
「日本語教育~」であれば、主専攻が何であれ、とにかく関心がある学生が集まっていると思えばいいのですが、「国際社会と日本」では、あまりにも漠然としています。
いきおい、「日本語教育を通してみた日本と国際社会のかかわり」という話も、聞いている学生さんの顔を見ながら、歴史の話が面白いかな、語学の話が面白いかな、教員養成の学生が多いのかな、理系の話のほうがいいのかな、などと頭の中がぐるぐるとしてしまいます。
当初、日本語教育の話をするつもりでしたが、突っ伏して寝る学生もいて、あんまり日本語教育に偏った話をしても面白くないか、と、授業で見せる映像の話に切り替えたりしましたが、やっぱり難しいですな。
うるさい!とか注意したり、なんか、いつもと調子が随分違いました。
聞く気がない学生さんに、焦点の定まらない話をするほど厄介なことはありません。
プレ授業を担当する先生方が大変な思いをなさっていることがよくわかりました。
何事もやってみるものですね。










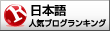

















僕が出た講義では、先生は前の席の20人としか授業してなかったです。