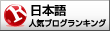外国にルーツを持つ子どもたちの支援をしていると、この問いにはしばしば、たびたび、頻繁に出くわす。
思考を支える言語の発達を阻害されてしまっていたら、表面的には発達障害ではないか、という疑問がわいてくるのも仕方がないことだと思っている。
で、だ。「発達障害である」ことがわかったら、学校現場の先生はどうするつもりなのだろうか。
日本語や教科指導について、現状でもいっぱいいっぱいになっていらっしゃる状況下で、さらに一歩進んで、指導方法を検討されるのだろうか。
大学教員であるということで、学校現場の先生方に何が提供できるのか、ふと、レッテル貼りをしているだけではないか、と思うことがある。
レッテルを貼って、そのあとは現場の先生に丸投げになってしまわないか、そういう危惧や懸念は常に持っているんだけど、発達障害について勉強してきたわけでもなく、できる話なんて、僕にとっては、ものすごくものすごく些末で限定的。
本書で取り上げられている話はどれも興味深い。
でも、読んでいて、端的に腑に落ちたのは、あとがきにあった著者の摂食障害の話の部分だった。
レッテルを貼った、だからどうするのか。レッテルを貼った、そのレッテルを貼るに至った原因は何なのか。
そこを解決しないことにはどうしようもない、という事。
前職に勤めていた時、地域の小中学校を巡回して先生方のお話を聞いていたことがあったけど、ある時、お一人の先生が
「上田先生、やっとわかったんです。なんで外国人児童生徒に発達障害の子が多いのかが!」
と、私にお話しされたことがあった。
その理由たるや、とてもここでは書けないような、とんでもない話だった。
学校現場が多様化している中、そこで児童生徒に向き合う教員が何を身につけて、何を学んでおくべきなのか。何を知っておくべきなのか。誰につなぐべきなのか。
教員志望者が減りつつあるという状況であれば、より充実した養成が求められているような気がしています。