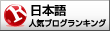日本語教育学入門という1年生対象の授業は、100名を超える受講生がおります。出席表を読み上げるのが大変なので、毎回、提出物を課していたりしたのですが、学生の書いてくるものがとても面白いのです。
日本語教育を専攻している学生だけじゃありませんから、書かれているものに?という内容のものも当然ありますが、自由な発想で見ていて楽しい。
たとえば、「Vたほうがいいです」という文型の説明をした後で、この文型を自然に使える、また、この表現以外を使うとおかしいと思う会話例を作ってください、という指示を出したことがあります。3往復くらいの会話でできますか?と。
場面設定が、占いを聞いた後の友達との会話だったり、色恋沙汰だったり、さまざまです。ある学生が手を挙げて、紙が足りないかもしれないといいます。様子を見に行くと、その学生が、
先生、大河ドラマが始まってしまいました
・・・まあ、いいんだけどさ、授業でそれだけの場面を作って話すつもりかい?
他にも、学生の条件を(ニーズ分析やレディネス分析で分かるような内容)与えて、学習に割ける時間や、授業時間の全体像を示して、到達目標を考えてみようということをしてみました。正直に言うと、初級の学生、中級の学生等、どんな状態をいうのかを実際に見せていなかったので、学生には非常に考えにくかったと反省しているのですが、これも様々な考え方が出てきて面白かったです。アルバイトをしている学習者、ということにすると、「指示が聞けるのが大切だから」と考える学生、「同僚と雑談できるのがポイント」と考える学生、「標識が読めなくちゃ」と思う学生など多種多様です。
どれが正解、ということがないものだけに、一生懸命考えれば考えるほど、いろんな話題が出てきます。
この授業、とても好きです。
この授業もあと残すところは数回。
教授法の授業は2年生ですから、そんなに詳しいことはしないのですが、最後に向けて、歴史的な話、日本語教育が残してきたものについて考える時間を作りたいと考えています。
日本語教育を専攻している学生だけじゃありませんから、書かれているものに?という内容のものも当然ありますが、自由な発想で見ていて楽しい。
たとえば、「Vたほうがいいです」という文型の説明をした後で、この文型を自然に使える、また、この表現以外を使うとおかしいと思う会話例を作ってください、という指示を出したことがあります。3往復くらいの会話でできますか?と。
場面設定が、占いを聞いた後の友達との会話だったり、色恋沙汰だったり、さまざまです。ある学生が手を挙げて、紙が足りないかもしれないといいます。様子を見に行くと、その学生が、
先生、大河ドラマが始まってしまいました
・・・まあ、いいんだけどさ、授業でそれだけの場面を作って話すつもりかい?
他にも、学生の条件を(ニーズ分析やレディネス分析で分かるような内容)与えて、学習に割ける時間や、授業時間の全体像を示して、到達目標を考えてみようということをしてみました。正直に言うと、初級の学生、中級の学生等、どんな状態をいうのかを実際に見せていなかったので、学生には非常に考えにくかったと反省しているのですが、これも様々な考え方が出てきて面白かったです。アルバイトをしている学習者、ということにすると、「指示が聞けるのが大切だから」と考える学生、「同僚と雑談できるのがポイント」と考える学生、「標識が読めなくちゃ」と思う学生など多種多様です。
どれが正解、ということがないものだけに、一生懸命考えれば考えるほど、いろんな話題が出てきます。
この授業、とても好きです。
この授業もあと残すところは数回。
教授法の授業は2年生ですから、そんなに詳しいことはしないのですが、最後に向けて、歴史的な話、日本語教育が残してきたものについて考える時間を作りたいと考えています。