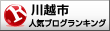喜多院から川越城へ向かう途中に浮島稲荷神社がある。
境内には、「片葉の芦叢生の所」という碑が立てられている。
この神社の裏手一帯は、昔は、「釜」と呼ばれる水の湧き出る所が七つあったところから、「七ツ釜」ともいわれ、萱や葦の密生する湿地帯だったという。
ここに生える葦は、不思議なことに片葉で、次のような伝説がある。
ある時、川越城が敵に攻められて、落城もあすに迫っていた。
その夜、一人の姫が乳母に導かれてそっと城から逃げのびた。ようやくこの七ツ釜のところまでやって来たが、足を踏みはずして釜の中へ落ちてしまった。乳母は懸命になって助けようとしたが、女一人の力ではどうすることもできなかった。 乳母は、大声で救いを求めたが、だれも助けにきてくれなかった。姫は、浮きつ沈みつ、ただもがくばかりであった。やっとのことで、川辺の葦にとりすがり、岸へはい上がろうとしたが、葦の葉がちぎれてしまった。姫はとうとう力尽き、葦の葉をつかんだまま、暗い深い水底へ沈んでしまった。
この沢地に生える葦は、姫のうらみによって、どれを見ても片葉であるという。

今は、かつて七ツ釜といわれた沢地のおもかげはほとんどない。
境内には、池があり芦の周りには緋鯉がゆったりと泳いでいる。