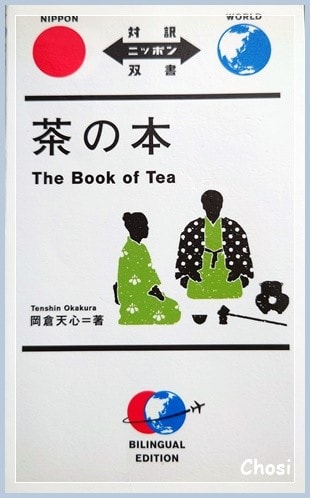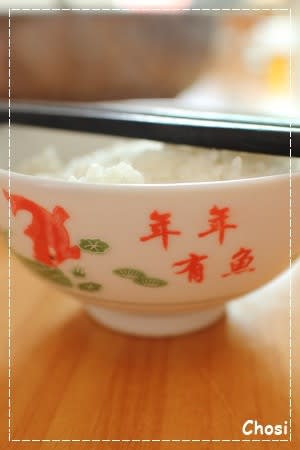9月21日に『
中国茶のこころ 茶味的麁相
』が発売され、
9月29日から10月8日まで東京での出版記念イベントを一気に駆け抜けて、今は抜け殻状態。
本の「一甲子の風格」の章に、老茶を十数煎飲んだ後、
その老茶は
「霓裳のような茶湯を脱いだ後、残ったのはしわしわの繊維になった皮であった」
という表現がある。
私の衣は霓裳ではなく、ピンクの中国通販で購入したひらひらの茶服であったが、
心と体はしわしわに干からびたような気がする。
今はただひたすら水を飲んでいる(夜になるとそこにアルコール分が加わったりするのだが)。
水と言えば前の記事で書き忘れたことがある。
今回の蔦屋書店とミナでの茶会では安藤雅信さんが足柄SAで汲んできてくださった富士山の湧き水を使った。
蔦屋の茶席ではジャスミン茶の後に白湯を飲んでいただいた。
甘くまろやかで身体に染み渡るようだった。
この本の翻訳編集チームに入れていただき、4年間携わってきたこと。
その4年の間に、李さんも含め、普通ならお付き合いできないような様々な分野での“才能あふれる”方たちに出会えたこと。
そしてイベントを通してたくさんのお客さまと交流ができたこと。
これから少しずつ咀嚼していきたいと思う。
こんな経験は本当に一生に一度きりかもしれない。

今、ひとつだけはっきりと言えることがある。
茶席の可能性は何と大きいことか。
蔦屋書店、ミナのプレスルームと茶会の会場が決まったとき、
「本屋さん?洋服屋さん?どんな茶席になるのかイメージが沸かない・・」と
最初は思っていた。
下見に行き、しつらえを考えている時も半信半疑だった。
しかし、当日会場に行き、設営をして茶席に座ってみると、何とも居心地がいい。
蔦屋では本に囲まれ、ミナでは秋冬物の洋服に囲まれ、いわば都会の真ん中での茶会。
これが妙に落ち着くのだ。
蔦屋はまるで図書館のような知的な雰囲気の中ですっきりとしたしつらえがマッチする。
ミナではショーケースにディスプレイされていたブローチをうらりんさんの提案で茶通置きにお借りしたり、
可愛いスツールが彩りを添えてくれたり、温かみのある茶席になっていたと思う。

李さんも本の中で書いている。
「茶席は暮らしの中に美学をもたらしてくれる。
(中略)
日常の生活空間でも、茶の雰囲気を醸し出すことはできるはずだ。」
日本の中国茶・台湾茶ファンの皆さまがこの本を読みながら、たくさんの気付きやヒントを見つけてくださったとしたら本望である。
私も水分を補給して干からびた心と体が元に戻ったら、また引き続き日常の中でお茶のシーンを編んで行こうと思う。
この本に携わる機会を作ってくださった安藤雅信さん、翻訳編集チームの仲間である浦川園実さん、田中優伊さん、
そして出版に関わってくださったすべての方々に心から感謝しています。
謝謝!