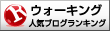今日のうまいもの
深川名物ウロコダンゴ
深川名物ウロコダンゴ
深川市といえば、日本でも有数の良質良食味米の産地、そして、お土産に買っていきたい深川名物といえば100年以上の歴史がある「ウロコダンゴ」です。

ウロコダンゴの外観は三角形で、側面はぎざぎざと波打っているのが特徴。手で持つとプルプルもちもちとして柔らかい団子状のものです。

色は白色、緑色、茶色の3種類、それぞれ、白あん、抹茶、小豆の3つの味を楽しめる。
原材料は、もち米、小麦粉、砂糖、水。添加物一切なしで、甘さ控えめで素朴な味わいが特徴。
▼ウロコダンゴ本舗・高橋商事


ウロコダンゴの歴史は道内のお菓子でも古いほうで、大正初期の1913年に誕生した。
深川~留萌間に旧国鉄留萌線が1910年に開通したことを記念して、高橋商事の創業者・高橋順治氏が製造・販売を開始した。実に100年以上の歴史があることになる。

登場当時の名称は「椿団子」。高橋氏が新潟県出身であったことから、新潟の椿餅を参考に、食べやすく三角形でギザギザのある形にアレンジした。
しかし、この「椿団子」というネーミングに待ったをかけた人物がいた。それが深川駅長椿修三だった。
曰く「どうも僕の苗字の下に団子をつけて大声で売られるのは変だ」。そこで駅長が代替えを考えたのが「ウロコダンゴ」だった。
当時日本海岸ではニシン漁が盛んで、留萌沿岸から来る貨物列車がニシンの鱗だらけだった。そして団子も側がウロコ状だった。その共通点をついた意外な発想だった。
ちなみに、ウロコダンゴにニシンは入っていない。故郷の餅、鉄道開通、ニシン漁、鉄道を使って運ばれてくるニシンたち、これらの要素が合わさって、現在の「ウロコダンゴ」という名物が出来上がったという。以来、深川駅で販売されてきた。
100年続く深川名物「ウロコダンゴ」、ネーミングに隠された鰊との意外な関係とは
白あん(白色)は発売当初から、昭和30年後半に茶色の小豆味が加わった。十勝産の小豆練りあんを混ぜ合わせて作られている。続いて昭和50年前半から緑色の抹茶味が登場。静岡産の抹茶を混ぜ合わせている。

作り方としては、原材料を混ぜ合わせ、高温高圧の蒸籠で蒸す。その後 冷ますが、この段階ではまだ平べったいまま。これを、特注の波型の包丁を使い、手作業で丁寧に三角形にカットしていく。
100年続く深川名物「ウロコダンゴ」、ネーミングに隠された鰊との意外な関係とは ウロコダンゴは、赤と緑のグラデーションで中央にウロコダンゴの三角形を模したパッケージが特徴。発売当初から基本デザインは変わっていない。
現在は、各味一つずつ合計3つが入った小サイズ、9個入りのもの、さらに倍の18個入り、長期保存に適したパック詰めした10個入りがある。
添加物や防腐剤は一切使用していないため、パック入りは10日ほど、それ以外は3日以内、夏は2日以内で召し上がっていただきたいという。