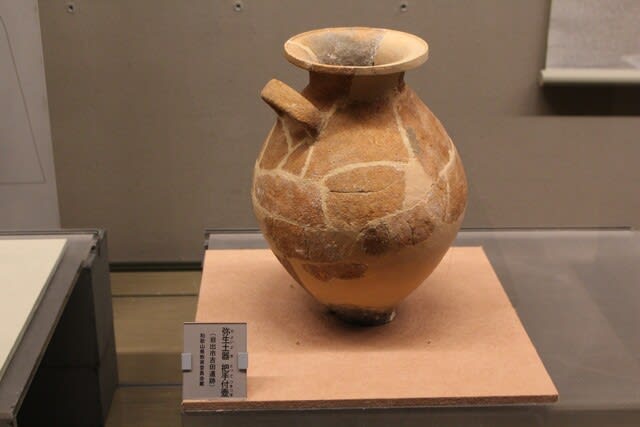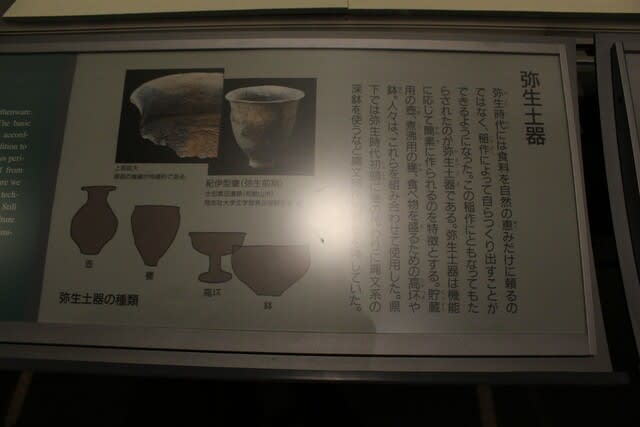今回から和歌山市立博物館の展示物を紹介する。訪問の最大目的は、大谷古墳出土の馬冑(ばちゅう・うまかぶと)と、騎馬民族につながる馬具類を見たいがためであった。

先ず、市立博物館展示の江戸時代後期の紀州の焼物から紹介する。前回は県立博物館展示の紀州の焼物であったが、今回は市立博物館の展示物である。

瑞芝焼 青磁菊透文手焙

南紀男山焼 染付不老橋絵鉢

清寧軒焼 輪花菓子鉢

偕楽園焼 交趾写二彩紫葉水差(永楽保全の指導によるという)

偕楽園焼 赤楽加賀光悦写茶碗(本阿弥光悦の加賀光悦を写した茶碗)
今回は、紀州の焼物の紹介で古代関連遺物の紹介は、次回以降とする。
<続く>