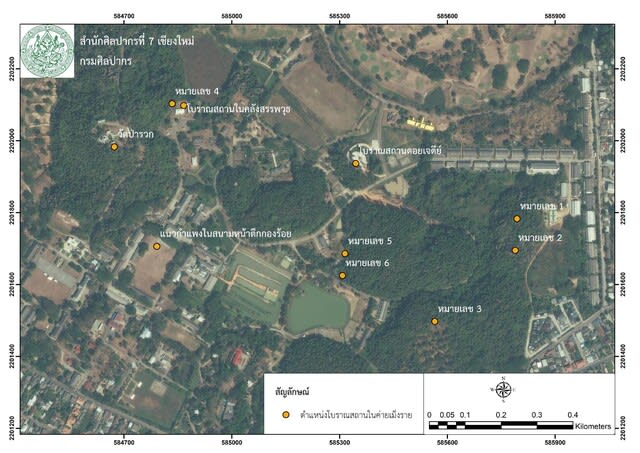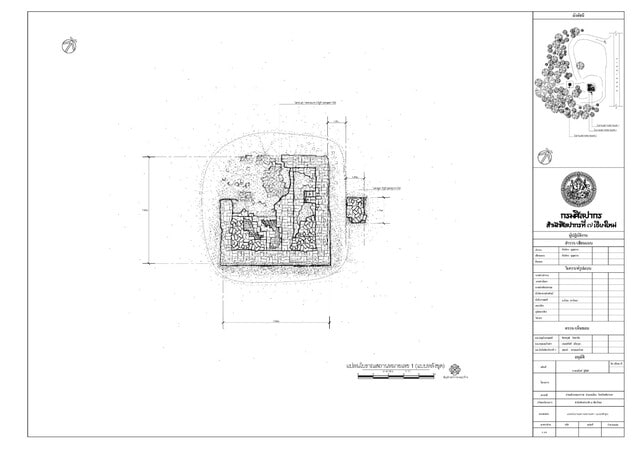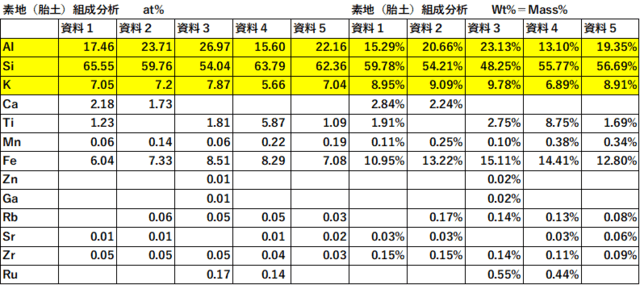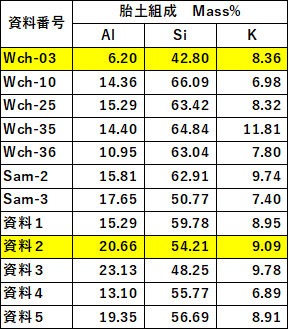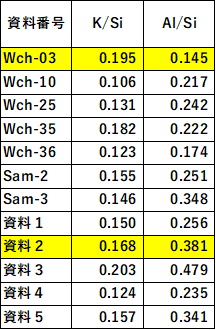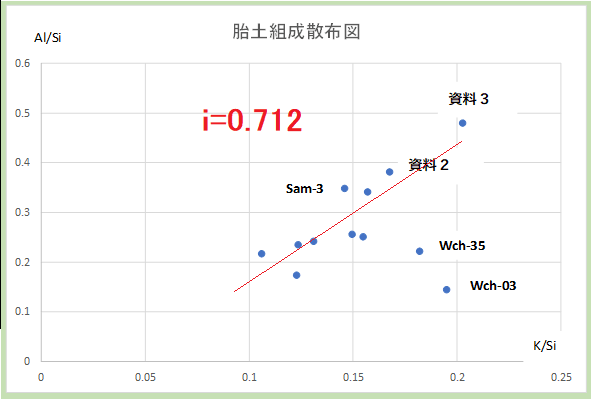ヤマタイコク所在地論は、大きく区分すると九州説と畿内説に分かれる。九州説も具体的地名となると、多数の御当地説が存在する。山門説もその一つだが、宇佐説も存在する。
「日本書紀」より、ヤマトと北部九州の関係をみていくこととする。先ず、崇神紀の四道将軍記事によれば、ヤマト王権の勢力範囲は、北部九州には届いていない。四道将軍の派遣は、せいぜい吉備・出雲くらいである。崇神紀によれば出雲征服の際、出雲振根は筑紫に行っていて不在だったと記す。
10代・崇神天皇六十年秋七月、天皇は出雲大神の神宝を見たく、武諸隅(たけもろすみ)を遣わしたが、出雲振根は筑紫に出向き不在であった。このことは当時、出雲と筑紫は同盟を結びヤマトに対峙していたであろうと想像させる。その時、弟の飯入根は皇命を承り神宝を奉った。出雲振根は弟の飯入根を責め、止屋(やむや)の淵で弟を切り殺した。朝廷は、吉備津彦と武渟川別(たけぬかわわけ)とを遣わして、出雲振根を誅殺した。出雲がヤマト王権に服するのは、この時である。
それでは北部九州はどうであろうか。12代・景行天皇のときに九州遠征が行われている。「日本書紀」によると、景行天皇十二年と十八年に遠征記事が記載されている。景行天皇は周防の娑麼(さば・山口県防府市)に至り、南を望んで煙りが立つのをみて賊がいると判断し武諸木、菟名手(うなて)、夏花を派遣して偵察させたところ、神夏磯媛(かむなつそひめ)という女首長が、磯津山(北九州市小倉南区貫山)の賢木(さかき)を抜き取り、上の枝に八握剣(やつかのつるぎ)をかけ、中枝に八咫鏡(やたのかがみ)をかけ、下枝に八尺瓊(やさかに)をかけ、いわゆる三種の神器を奉じ、白旗を船の舳先にたてて遣ってきて帰順した。その神夏磯媛は豊前の首長であったかと思われる。
神夏磯媛は、菟佐(宇佐)、御木(みけ・山国川)、高羽(田川)、緑野(北九州市紫川)の川上にいる賊を教えた。武諸木らは謀略でそれらを倒し、その後天皇が豊前の長峡(ながお)に至り行宮を建てた。さらに天皇は碩田国(おおきたのくに・大分市)を経て来田見邑(くたみむら・竹田市)に仮宮を設け、日向に高屋宮(宮崎市)と呼ぶ行宮を建て、熊襲征伐をした後、下図の行路により熊県(くまのあがた)から火国を転戦し、筑後の八女県の的邑(いくはのおむら)に到ったという。

『日本書紀』は、その後突然に景行天皇十九年九月条に「天皇、日向より至りたまふ」と記して、その帰還がどのような行程であったか記されていない。
先の的邑以降について「豊後国風土記」が記している。日田郡条によれば、生葉(的)行宮を発して日田郡に到ったとあるので、天皇の一行は的邑から筑後川の上流、日田川にそって筑後から豊前に抜けたとみられる。さらに「肥前国風土記」彼杵郡(そのきぐん)には、天皇が熊襲を滅ぼして凱旋し「豊前国宇佐海浜行宮」に在したと記すので、天皇一行は豊前の宇佐に進んだであろう。
以上をまとめると、景行天皇の九州遠征は、周防灘を横断して豊前国に上陸し、その後に南下して襲を平定、西に進んで熊国を治め、火国から日田川にそって豊前に抜ける行程であったかと思われる。
ここで上掲のグーグルアースをご覧願いたい。景行天皇一行の足跡を描いてみた。ここで注目すべきは、天皇一行の足跡から外れている二つの地域である。一つは、大隅・薩摩の隼人族の地域。二つ目は、筑前、筑後、肥前の旧・邪馬台国連合の諸域である。これは何を物語るのか。
1.大隅・薩摩の隼人族は、大きな勢力を擁しており、景行天皇一行は苦戦を避けるため、意識的に忌避したと考えられる
2.旧邪馬台国連合処地域へ足跡を残さなかったのも、意識的に忌避した結果と考えられる。邪馬台国の時代から時間は流れているものの、その地域には依然として勢力を誇る豪族が存在したであろう
以上の事どもが考えられ、更に三つ目の注目点は、豊前の女首長であった神夏磯媛の存在である。これはヒミコの後裔であったかと思われる。邪馬台国はヒミコ、トヨと代々女首長が国を治めていた、その後世は史書にあらわれていないが、女首長が治める伝統が続いたものと想像する。
神夏磯媛の帰順と九州遠征の出発点と終着点が豊前であり、特に宇佐に注目したい。その宇佐がヤマタイコクであった可能性は在りそうだ。宇佐八幡宮が意識的に、ヒミコの存在を抹殺しているのが、その証である。
その後、14代仲哀天皇の御代に到り、仲哀天皇八年春に筑紫へ到り、橿日宮(香椎宮)に滞在したと日本書紀は記す。旧邪馬台国連合諸国がヤマト王権の統治下に入るのは、仲哀天皇の時代からであった。
<了>