<続き>
今回は弥生時代から古墳時代にかけての展示品の中から、武器・武具類を紹介する。弥生時代にはすでに戦いが行われていた証である。弥生時代のヤジりは石鏃や銅鏃であったものが、古墳時代に至ると鉄鏃に変化する。古墳時代には鐵の精錬が一般化した背景による。




桜井茶臼山古墳からは弥生時代の銅鏃と古墳時代の鉄鏃が一緒に出土している。







<続く>
<続き>
今回は弥生時代から古墳時代にかけての展示品の中から、武器・武具類を紹介する。弥生時代にはすでに戦いが行われていた証である。弥生時代のヤジりは石鏃や銅鏃であったものが、古墳時代に至ると鉄鏃に変化する。古墳時代には鐵の精錬が一般化した背景による。




桜井茶臼山古墳からは弥生時代の銅鏃と古墳時代の鉄鏃が一緒に出土している。







<続く>
<続き>
今回は古墳時代の鉄製品・展示物を紹介する。最近の相次ぐ遺跡の発掘により、中国地方・山陽側では弥生末期に製鐵が始まっていたであろう痕跡が発掘されている。大和の古墳時代は朝鮮半島の鉄鋌を輸入していたようだ。






<続く>
<続き>
『しきしまの大和展』の展示品を紹介する前に、次の写真を御覧願いたい。管玉の穴あけ工法である。尚、資料は松江市・出雲玉作資料館の展示品である。

管玉の外面加工後、上下から穿孔したものと片方からのみ穿孔したものとが存在する。出雲では片面穿孔が存在する。この時のキリは鉄製であったようだ。

右下の細目の鉄製キリなどを下の道具を用いて穿孔したようである。このように管玉の製法は究明されているが、合子の場合はどうであろうか。

以下『しきしまの大和展』展示品の紹介である。いずれも島の山古墳出土品で文化庁所蔵の重要文化財である。










管玉の製法については先に触れたが、上掲の合子はどのように加工したのであろうか。別に悩む必要はないのだが、古代人は何らかの方法で穴刳りしたのであろう。脱帽以外の何物でもない。
<続く>
<続き>
今回は古墳時代の石製品を紹介する。毎度のことながら、このような石材加工品をみていると、加工機械はもとより十分な工具もないなかで、よくも作ったものだと感心する。よほどの腕前であろう。







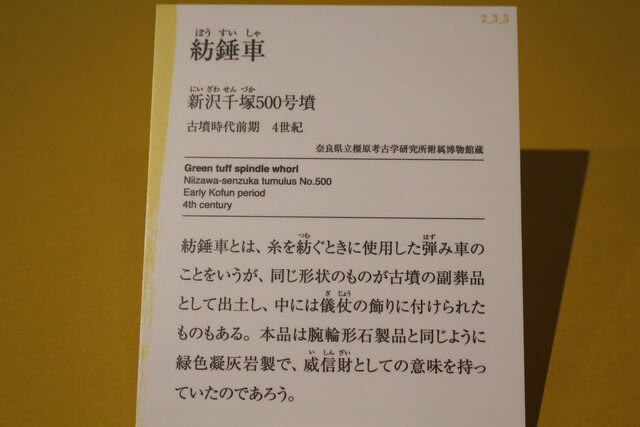




この合子など、どのようにして内側を刳り抜いたのか、腕と根気更には工具を工夫したであろう。脱帽です。
<続く>