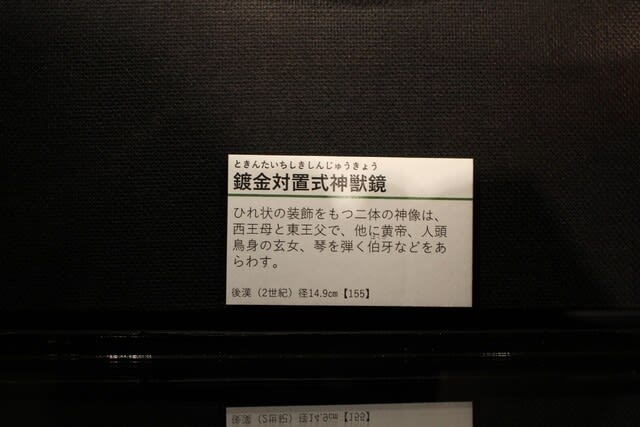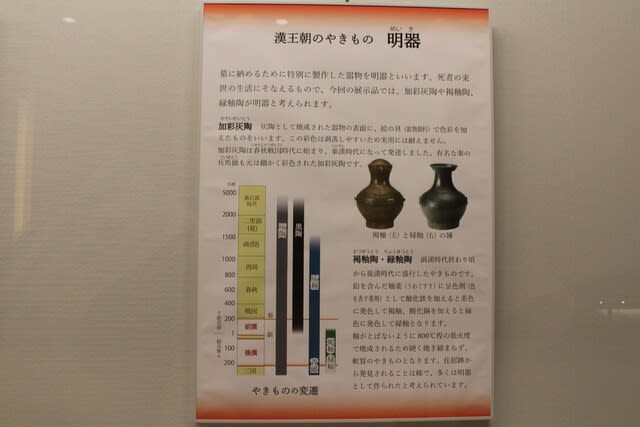<続き>
今回は、【古代中国金工の歴史】とのテーマの展示品を紹介する。時代は商から前漢時代までのモノである。
【古代中国金工の歴史】

乳釘文爵 商 高13.8cm
素文斝(か) 商 高20.1cm
獣面文觚(こく) 商 高19.8cm
弦文鼎(かなえ) 商 高17.7cm

鋸歯文鏡 商 径16.3cm

羽状地文扁壺 戦国 高24.7cm

四葉文鏡 戦国 径10.1cm

羽状地文鏡 戦国 径11.4cm


緑松石象嵌透彫鏡 戦国 径19.4cm

儀礼狩猟文壺 戦国 高32.2cm

金緑松石象嵌剣 秦 長53.2cm





鈁(ほう) 前漢 高36.5cm
以上で三国時代以前の展示品の紹介を終え、次回からは隋・唐時代の展示品を紹介する。
<続く>