午前中、重松清の「舞姫通信」読了。
午後から高校生のお芝居を一本だけ観てきました。
阿部順という作家の脚本が気になったからです。
昨日一部分だけ見たのが、阿部順作品でしたので。
さて、批評するときには
「脚本も演出も役者もすべて面白い」
「このうち一つか二つは面白い」
「全部面白くない」
の3パターンがあって、これに「かなり」とか「まあまあ」とか「そこそこ」という修飾が着きますが、基本はこの3パターンです。
静岡東高の「桜井家の掟」は「脚本はまあまあ面白く、演出はかなり面白くなく、演技はそこそこ面白かったものの不満が残りました」というものでした。
演出については、説明が面倒なので省略しますが、演技は一度ちゃんと指導を受ければ、簡単に手直しが出来そうです。それが、たぶんそのまま演出にもつながるはずなんで、ちゃんとした指導を受けるのがよさそうです。一回の指導で直ります。
具体的に言うと、同じ役者がしゃべっていても、音が台詞として聞こえるときと聞こえないときがあって、その原因が動きながら台詞をしゃべることにあるのです。
なぜか、舞台の上では動かないといけないような錯覚にとらわれている生徒が多いのですが、首を振りながらしゃべると台詞が台詞として聞こえません。音が安定しないのです。同じように下半身が安定していないと、台詞が台詞として聞こえません。音が聞こえるだけなんです。
そこで、動いてからしゃべるのか、しゃべってから動くのかを区分することからはじめるといいと思います。
さらに具体的な話は、酔っ払っていないいずれかのときに。
最新の画像[もっと見る]










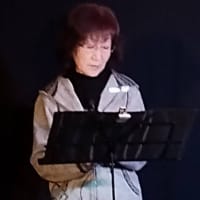









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます