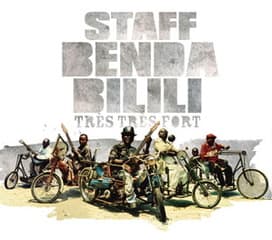今日は話題のジャズピアニスト、エリック・ルイスのインストア・ライヴを観に、渋谷タワーレコードに来ています。先程終わりましたけど、凄く良かったです。今、サイン会中です。私もサインが欲しいところですが、昨日ヘイリー・ロレンを買ってしまったので今日は我慢です…。ライヴの様子などは帰宅後に追記します。
帰宅後追記:
正直な話、噂に聞くだけで音は聴いたことがない状態で観に行きました。しかも勝手にジェイミー・カラムのような爽やか系を想像していまして、どんな白人の優男が登場するんだろうと思っていましたら、がっしりとした黒人さんが出てきて驚きました。もちろんブラック系が大好きな私はテンション上がりましたけどね。 そしていよいよ弾くぞ!という感じにエレピに向き合うエリック・ルイス、まずは足場から固めていきます。左足でペダルを踏み、右足をグイ~っと後ろに延ばす。アルバム「ROCKJAZZ vol.1」のジャケットに写るあの体勢です。はなから椅子なんかありませんよ! って言うかあのジャケ写は、それ用のポーズとか、もしくは興奮が頂点に達した瞬間を切り取ったものとか、そんな風に思っていましたが、まさか始めっからあの体勢とは!
そして弾き始めたのは、おそらくキラーズの「Mr.Brightside」だったかな?(記憶が曖昧…)。そしてブレイキング・ベンジャミンの「The Diary Of Jane」、ストーンズの「Paint It, Black」と続きます。「The Diary Of Jane」の後半辺りでははかなりアヴァンギャルドな感じで叩きまくり、もう既におでこから汗が滴り落ちる大熱演。とにかくその緊張感たるや凄まじいものがありました。そこにはジャズとかロックとかを越えた何処かスピリチュアルなエネルギーを感じましたね。ニルヴァーナの「Smells Like Teen Spirit」なんかのフリーキーさも圧巻。もの凄い形相で、鍵盤に挑みがかるかのようでした。
もちろんただ派手に叩いてばかりいる訳ではありません。コールドプレイの「Clocks」では、抑制の効いたタッチで研ぎ澄まされた旋律をスリリングに聴かせてくれました。「Paint It, Black」では静かに東洋的メロディを弾いたり、そんな静と動のコントラストも秀逸でした。そしてその表現力と、それに伴う弾く姿がまた格好良い! 音との一体感と言いますか。例の体勢も、足を前後に開くだけではなく、時には左右に開いてみたり、膝を付いて中腰のようになってみたり、その音と同時に変化して行く感じ。一口にロックのカヴァーというだけでは言い切れない、ある種のソウル・ミュージックですよ! 痺れましたね!
そして最後にはそれまでとは一味違う、スウィンギーな演奏も披露してくれまして、その確かなテクニックと、抜群のリズム感、ジャズならではの遊び心も魅せてくれました。ただ一つだけ難点を言わせてもらえば、今回はインストア・ライヴでしたので、アコースティックのピアノではなくエレピだったんですよね。やっぱりグランド・ピアノで聴きたかった! エリックの型破りのパワーはエレピでは受け止めきれない部分があり、これがピアノだったらもっともっと高揚感の高い演奏になっただろうなと思いました。ま、それはインストアではなく、ちゃんとお金を払ってライヴに行かなくては!ってことですよね…。ちなみにブルーノート東京でのライヴでは、ピアノをステージではなく客席の中央に配置して熱演を繰り広げたとか。観たかった~!
帰宅後追記:
正直な話、噂に聞くだけで音は聴いたことがない状態で観に行きました。しかも勝手にジェイミー・カラムのような爽やか系を想像していまして、どんな白人の優男が登場するんだろうと思っていましたら、がっしりとした黒人さんが出てきて驚きました。もちろんブラック系が大好きな私はテンション上がりましたけどね。 そしていよいよ弾くぞ!という感じにエレピに向き合うエリック・ルイス、まずは足場から固めていきます。左足でペダルを踏み、右足をグイ~っと後ろに延ばす。アルバム「ROCKJAZZ vol.1」のジャケットに写るあの体勢です。はなから椅子なんかありませんよ! って言うかあのジャケ写は、それ用のポーズとか、もしくは興奮が頂点に達した瞬間を切り取ったものとか、そんな風に思っていましたが、まさか始めっからあの体勢とは!
そして弾き始めたのは、おそらくキラーズの「Mr.Brightside」だったかな?(記憶が曖昧…)。そしてブレイキング・ベンジャミンの「The Diary Of Jane」、ストーンズの「Paint It, Black」と続きます。「The Diary Of Jane」の後半辺りでははかなりアヴァンギャルドな感じで叩きまくり、もう既におでこから汗が滴り落ちる大熱演。とにかくその緊張感たるや凄まじいものがありました。そこにはジャズとかロックとかを越えた何処かスピリチュアルなエネルギーを感じましたね。ニルヴァーナの「Smells Like Teen Spirit」なんかのフリーキーさも圧巻。もの凄い形相で、鍵盤に挑みがかるかのようでした。
もちろんただ派手に叩いてばかりいる訳ではありません。コールドプレイの「Clocks」では、抑制の効いたタッチで研ぎ澄まされた旋律をスリリングに聴かせてくれました。「Paint It, Black」では静かに東洋的メロディを弾いたり、そんな静と動のコントラストも秀逸でした。そしてその表現力と、それに伴う弾く姿がまた格好良い! 音との一体感と言いますか。例の体勢も、足を前後に開くだけではなく、時には左右に開いてみたり、膝を付いて中腰のようになってみたり、その音と同時に変化して行く感じ。一口にロックのカヴァーというだけでは言い切れない、ある種のソウル・ミュージックですよ! 痺れましたね!
そして最後にはそれまでとは一味違う、スウィンギーな演奏も披露してくれまして、その確かなテクニックと、抜群のリズム感、ジャズならではの遊び心も魅せてくれました。ただ一つだけ難点を言わせてもらえば、今回はインストア・ライヴでしたので、アコースティックのピアノではなくエレピだったんですよね。やっぱりグランド・ピアノで聴きたかった! エリックの型破りのパワーはエレピでは受け止めきれない部分があり、これがピアノだったらもっともっと高揚感の高い演奏になっただろうなと思いました。ま、それはインストアではなく、ちゃんとお金を払ってライヴに行かなくては!ってことですよね…。ちなみにブルーノート東京でのライヴでは、ピアノをステージではなく客席の中央に配置して熱演を繰り広げたとか。観たかった~!