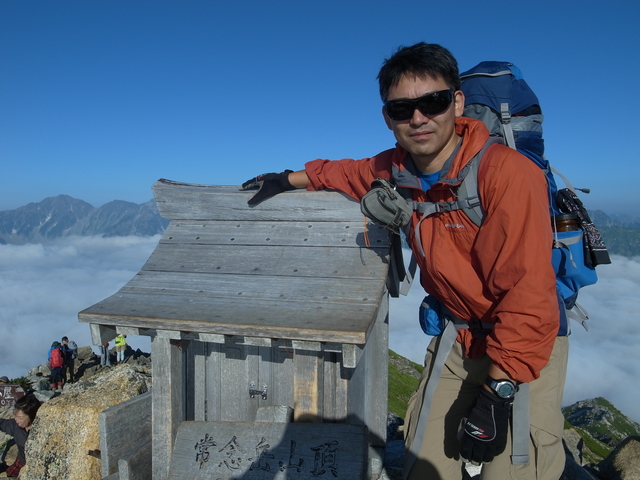内田樹氏の著作、死と身体の冒頭で、「あべこべことば」という項目がある。そこで「適当」という言葉について、面白い考察がなされている。
「適当な言葉を選べ」という場合の「適当」は、的確にとか正しくとかいう意味であるが、「適当にやってね」という場合の「適当」は、いい加減にという意味で、同じ言葉でも全く逆の意味になる。この変な使い方を、スイスのエリザベス君に質問されたそうだ。
なぜこういう面倒なことが起こるのか。
すごーく熱々で結婚した人たちを知っている。彼らは確かに愛し合っている。しかし、よく喧嘩もする。彼らは愛し合っていると同時に憎しみあってもいる。この二人の関係をどう考えるべきなのだろうか。
私たちは時間の流れの中で生きている。言葉もその流れの中で意味を持つし、感情も移ろい流れている。意味や感情を、ある一点に固定してそこだけ取り出して捉えることは難しい。そのように固定すれば、意味がねじ曲げられてしまう可能性がある。
流れていく状況を捉えていくには、その流れに逆らわず、流れのままに感じなければならない。「考えるな、感じろ」と誰か言ってたけれど。
考えるのは脳の機能かもしれないが、感じるのは脳より広い身体の機能である。感じるためには身体を十分に使わなくてはならないし、人の身体の微妙な動きにも敏感にならなくてはならない。
現代では、その能力は一種の超能力のようなものになってしまったのかもしれないが、それをいまだに持っている人がいる。そのような人を達人と呼ぶのかもしれない。