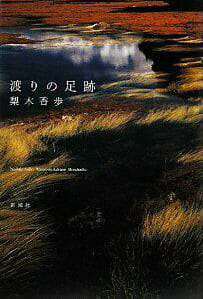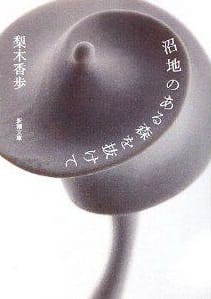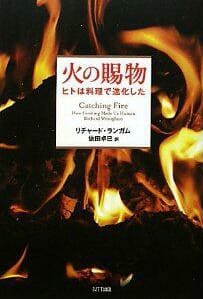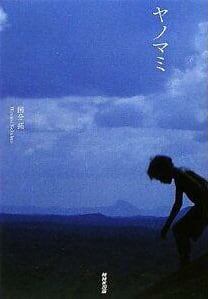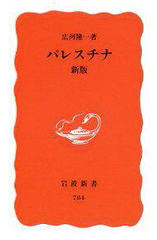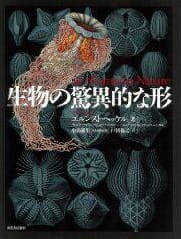読む本がなくて、あわてて本屋に。
新聞広告で見た『火の賜物 ヒトは料理で進化した』(NTT出版/リチャード・ランガム著)をゲット。
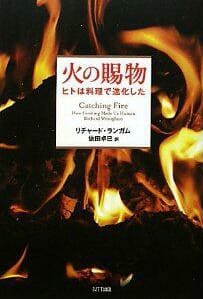
火を使って料理をすることが、
アウストラロピテクスをホモ・ハビリスに進化をさせたんじゃないか、
つまり、それが類人猿もどきをヒトに進化させた原因じゃないか、
ヒトがヒトたる所以は、火を使った料理にあるんじゃないか…という内容のようです。
こ、これはおもしろそう!
以前から、生物進化に対する漠然とした疑問があって、
だいたい生物の進化って形態の話ばっかりですよね。
そもそも進化って、形態の進化だけを指すのかな?
例えば、ある種の消化酵素が生成できるようになるとか、
新たな腸内細菌との共生によって、ぐっとエネルギー効率がよくなるとか…
そんなことによって、見た目同じだけど、それはもう別の生きもの、、、
なんて言わないのか。。。
つまり、目に見えないところの進化もあっていいわけだし、
それがたとえ「文化」であっても、その変化があるとなしでは全然ちがう生きものとも言える、、ことはないなのかな?
個人的にそんな考えというか、疑問を持っていたので、
この本の内容も興味津々です。
……が、読み始めたらあんまりおもしろくない。
第1章では、「生食主義者」(そんな人たちがいるんだ…)たちの事例・実験を紹介して、
彼らが痩せていたり、あるいは痩せてしまったり、
あるいは女性は生理が止まったりすることを指摘して、
だから火を使った料理がヒトには重要なんだ、、という主張をするのですが、
生食主義者たちの非科学性を指摘するわりには、
本人の主張もあんまり科学的ではないですね。
たんに説明不足なだけかなあ。。。
また、イヌイットなどの民族や冒険家や遭難者の事例を引き合いに出して、
「野生のものを生で食べてより長く生きのびた記録がないことから、
むしろ人間は極限状態においても食物を料理しなければならないことがわかる」って
断言しているけど、ぜんぜん分かんないよ!
むーん、、、。著者は人類学者のようで、ちゃんとした学者っぽいのにな。
科学的な説明をしているようで、ぜんぜん科学的じゃない感じは、
「生食主義者」と変わらない感じ。。。
うーん、、、2章以降に期待、、、するかな。
テーマはおもしろいはずなんだけどなあ。。。