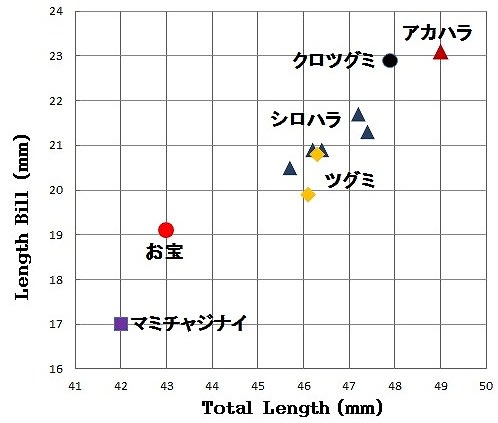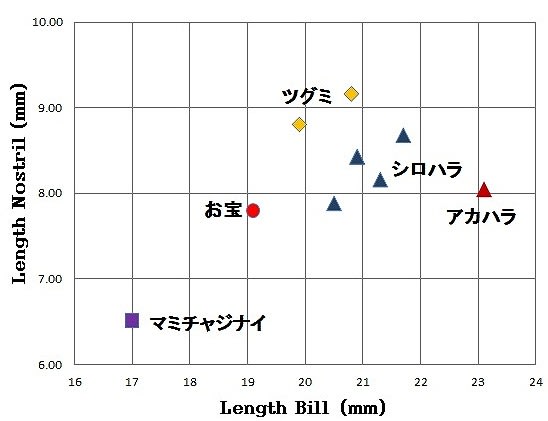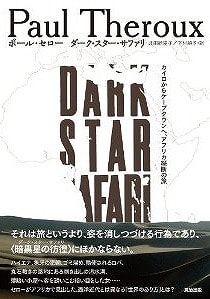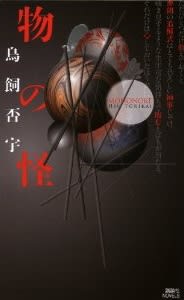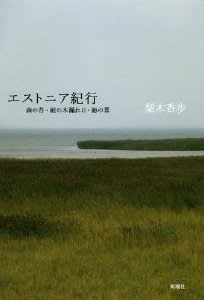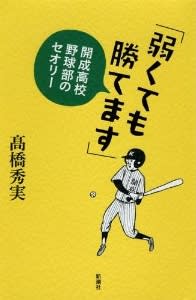秋が深まってきたのですが、いまだ夏の思い出がチクチクします。
最初のそのことに気づいたのはいつだったか。
喫茶店で、取っ手の小さなカップでコーヒーを飲んだときだったか。
取っ手に突っ込んだ人差し指が痛いのです。
「あれ? 指が痛い…」
どうも第1関節が痛いみたい。

なんで?
そう思うと、右の人差し指の第1関節も痛い。。。

なんだっけ?
冷静に考えます。思い出します。
夏だ。海だ。シュノーケルだ。
8月4日だ!
そう、ウェットスーツだ!!
夏に海に行ったときに、ウェットスーツがなかなか着られなくて、
それは太ったからなのか、太ったからなのか、太ったからなのか(くどい)、
とにかく指でぐーっと引っ張ったときに、グキッと同時にいったのだ。
いや、同時じゃなくて、1本ずつだったか。
とにかくこれは「ねんざ」だ。
両手、両人差し指第1関節のねんざ。。。
これが暑かった2012年の夏の憶ひ出です。
治んないね、ねんざは。
最初のそのことに気づいたのはいつだったか。
喫茶店で、取っ手の小さなカップでコーヒーを飲んだときだったか。
取っ手に突っ込んだ人差し指が痛いのです。
「あれ? 指が痛い…」
どうも第1関節が痛いみたい。

なんで?
そう思うと、右の人差し指の第1関節も痛い。。。

なんだっけ?
冷静に考えます。思い出します。
夏だ。海だ。シュノーケルだ。
8月4日だ!
そう、ウェットスーツだ!!
夏に海に行ったときに、ウェットスーツがなかなか着られなくて、
それは太ったからなのか、太ったからなのか、太ったからなのか(くどい)、
とにかく指でぐーっと引っ張ったときに、グキッと同時にいったのだ。
いや、同時じゃなくて、1本ずつだったか。
とにかくこれは「ねんざ」だ。
両手、両人差し指第1関節のねんざ。。。
これが暑かった2012年の夏の憶ひ出です。
治んないね、ねんざは。