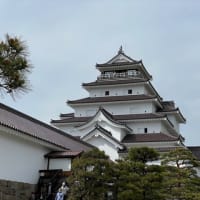一路、ダッチハーバーへ
カタパルトに仕掛けた炸薬が爆発します。
九五式水偵はロケットのように飛び出し、体にGのかかった私はシートの背もたれに押さえつけられました。
視野がきゅっと狭まります。
目の前の一点だけがはっきり見え、周囲の景色は川のように流れます。愛機はさっと左旋回して、弧を描きながら上昇しました。
どす黒い海を見下ろせば、二十・三センチ連装主砲をずらりとならべた『摩耶』が二十二ノット(時速約四十キロ)の高速を出し、荒波をものともせずダッチハーバーへ向けて走る姿が目に入ります。ダッチハーバーとの距離をすこしでも縮め、我々の帰り道を短くしようとしてくれているのでしょう。飛行機隊を全力で支えようとするそんな姿勢を見れば、いよいよ心が引き締まります。
エンジンの回転数を上げて勢いをつけます。回転数のメーターが上がるにつれて、スピードメーターも右へ振れ、機体の振動が増します。低く垂れこめた重い雲の底が迫ります。逆巻く雲へ突入しました。
こまかい灰をばらまいたような雲のなか、風のうなり声だけがあたりに響いていました。なにも見えません。
今度は風にもまれます。地上から眺めた時、雲はなんとも優雅で穏やかな姿に見えますが、なかへ入ってみれば、雲の激しさがわかります。雲はかた時もじっとしてなどいません。すさまじい気流が流れ、爆発的といっていいほどの速度で刻一刻とその形を変えているのです。まるで、その動きをとめてしまえば、世界全体が死んでしまうとでも言いた気に。
早く晴れた空へ突き抜けたいところですが、どれだけ高度を上げても雲ばかり。粘ついた乱気流に弄《もてあそ》ばれ、揺れるだけです。荒れ狂う風にさらわれて翼がふらつき、時折、ひっくり返りそうになります。愛機は、悪い夢にうなされてのたうつようでした。
こんな時は、意識して心を緩めてやります。按摩《あんま》を受ける時ように体の力を抜くのです。妙に力を入れてしまうと、うまく操縦できません。
乗馬の世界では人馬一体ということがよく言われるそうです。人が馬を操るのではなく、人と馬がひとつになってこそ、うまく馬を乗りこなせるのだとか。
水上機も似たようなものです。
私が飛行機を操縦するのではありません。私が九五式水偵とひとつになっていっしょに飛翔するのです。そうしてこそ、鳥のように自由自在に舞うことができるのです。
ゆったり坐りなおして、体を機体に任せます。
ついでと言ってはなんですが、心も預けてしまいます。
深く息を吸い、細くゆっくり息を吐きます。できるだけなにも考えないようにして雑念を追い払い、胎児が母のお腹で眠るように、羊水にたゆたうようにリラックスします。操縦桿にかけた手は、小指と薬指だけしっかり握り、あとは軽くそえるだけ。耳を澄ませて、心を澄ませて、なににもとらわれない自由な心を作ります。
心が溶け出すようでした。翼の端から端まで、機体の隅々まで、自分の神経が行き渡り、私は機体のすべてを感じ取っています。鳥になったようです。
なにをおかしなことを言っているのだろうと思われるかもしれません。
航空学校へ入って飛行機の操縦を習いだした頃、ベテランパイロットの教官がこんな話をしてくれたのですが、信じられませんでした。ほんとうにそんなことがあるものなのか疑問でした。ですが、訓練や日々の任務で何千時間も飛行するうちに、教官の言ったことが次第に理解できるようになりました。これは理屈ではありません。皮膚に染みこむようにして、体でわかるようになったのです。私がひとつになりたいと願えば、飛行機は私の気持ちに応えてくれます。ちっぽけな己を捨てて自分の心を無にした時、私はたしかに愛機とひとつになっているのです。
風を感じます。
雲の粒子を感じます。
気流の乱れを感じます。
心が揺れたら、ごく自然に操縦桿を引いたり倒したり、操縦ペダルを踏んだりします。うまくやってやろうとか、思い通りに動かしてやろうなどといきがってはいけません。心のままに、あくまでも自然に操縦するのです。
この雲を抜け出すことができるだろうかといった不安は、まったく感じませんでした。
無限の雲などありません。
雲には必ず果てがあります。
地球のどこかは晴れているものです。そして、どこかが晴れていたなら、他の場所では曇っていたり、雨が降っていたりするものです。それが世界の在り様なのですから。
私は、世界に逆らったりすることはできません。
九五式水上偵察機に乗って地球の片隅を飛ぶのが関の山です。
私は、風や雲といった自然の恵みをちょっとだけ拝借して空を泳ぎ、蒼穹《そうきゅう》の上から世界を眺めます。そうしていると、自分はこの世界の一部なのだとおぼろげながら胸にしみます。私はなんにも支配することはできませんし、そうしたいとも思いません。逆に、なにかに支配されたり、その言いなりになって生きるのもごめんです。私は、ただ風に乗って空を飛びます。そうして、すこしずつこの世界の在り様を学ぶのです。
太陽がまぶしくて、思わずまぶたを閉じました。
ようやく雲の上へ出ることができました。真っ青な空が広がっています。高度計は四千三百メートルを指していました。
『高雄』と『摩耶』の僚機が、白い雲の絨毯の上に小さな影をぽつりと落としているのが見えました。仲間たちはバンク(翼を左右に振って合図すること)してこっちへこいと誘《いざな》います。私は翼を傾け、彼らに追いつきました。首尾よく合流した四機の九五式水偵は雁行編隊を組みました。
第二次攻撃隊は、空母艦載機隊と水上機隊が別々に行動して爆撃を行なうことになりました。速度が違いすぎるので、九五式水偵が空母艦載機隊と行動をともにすれば足手まといになってしまいます。敵の航空基地があるのにもかかわらず戦闘機が護衛についてくれないのは、不安といえば不安ですし、作戦上もまずいことですがいたしかたありません。
すこし汗ばんできたので、電熱服《パイロットスーツ》の温度を調整しました。電熱線が埋めこんであるので、電気毛布を着ているようなものです。高い空は気温がとても低いですし、おまけに九五式水偵には小さな風防しかついていませんから、吹きさらしのまま飛ぶことになります。これがなければ寒くて凍えてしまいます。
風は冷たいですが、太陽のほのかなぬくもりを頰に感じます。私は雲の上を飛ぶのが大好きでした。晴れた空は気持ちがいいものですし、冷たい風はさわやかです。なにより、なんにもさえぎるもののないまっさらな陽光は、誰かが私を生きさせてくれている証のように思えてなりませんでしたから。
時折、なんともいえない不思議な気分にとらわれます。
こんなにきれいな光を放つ太陽はいったいどうしてできたのでしょう?
科学雑誌をめくればその答えは載っていますが、それだけではどうにも納得しきれません。人智を超えた何者かがある意図を持って太陽をこしらえたとしか私には思えません。陽光にあたためられ、生きとし生けるものはみな生きています。私は生かされています。当たり前のことのようですが、それがなによりもありがたいことだと思えるのです。
死と紙一重の危険を何度となく潜り抜けました。
嵐に見舞われたり、敵に襲われたり、突然エンジンが不調になったりと、死んでもおかしくないことが何度かありました。
もうだめかもしれないと思った瞬間、そのたびに不思議としか言いようのない力が働き、私は救われました。奇蹟とでも呼べばいいのでしょうか。これをなんと言えばいいのか、私にはわかりません。うまく言えなくてもどかしいのですが、ただ、自分を超えたなにかのはからいを感じることだけは確かです。空に命を預けてみれば、偉大ななにかの懐に抱《いだ》かれているような気がします。
一度でいいから、貴女を連れてこの蒼穹《そうきゅう》を翔《と》んでみたかった。
風に乗って緑の大地や青い海を見つめ、空の果てに高くそびえる入道雲を眺め、それから、私がスリル満点の曲芸飛行を披露したなら、貴女はきっと笑顔になってくれたことでしょう。
世に棲《す》む日々は、埃まみれの毎日です。
それが人間の悲しい性なのか、それとも業の深さなのか、どうでもいいようなことでついつい悩んでしまいますし、人を傷つけてしまいます。うわべだけは善良そうに振舞っていても、一皮むけば煤だらけの心をした哀しい人たちとも付き合ってゆかねばなりません。そして、かく言う私自身も、つまらない我欲を満たしたり、体面を保つために肩肘を張ったりしてしまいます。心のなかには消そうにも消しようのない暗い煩悩の火が燃え盛っています。他者を傷つけずには生きていかれません。自分自身を傷つけずに生きることなど、不可能です。地上は汚濁《おじょく》にまみれています。戦争とは、そんな煩悩の火が野火のように燃え広がり、この世をどこまでも焼き尽くす現象なのでしょう。
もしかしたら、この世は地獄かもしれません。いえ、あんなむごたらしい世界大戦を引き起こした人間の世界など、地獄に決まっています。人は哀しい生き物です。
そんなこの世で様々な現実や自分自身と折り合いをつけながら暮らすよりほかに手立てがないのですが、悪いことばかりではありません。ひとたび空を飛んだなら、すべてが変わります。
風が魂を洗ってくれます。
特別なことなどなにもしなくても、ただ翼を広げるだけで、風が勝手に心をぴかぴかに磨いてくれるので、煩わしいことや憂いを忘れて子供の頃のようなまっさらな気持ちへかえることができるのです。煩悩の火に焼かれた心の草原に新しい若草が芽生え、青々と甦るようなすがすがしい心持ちにさえなります。生きるということはこんなにうれしいことのなのだと、たとえ現世が地獄だとしても希望を抱きしめることができるのだと、空が教えてくれます。
太陽の光に誘われて、ふと思い出しました。
いつか白い日傘を差した貴女と二人で、江ノ島の海岸沿いを散歩しましたね。曲がりくねった線路をゆっくり走る江ノ電に乗り、小さな駅で降りました。九月の終わり頃だったでしょうか。青空が広がっていて、いささか汗ばんでしまうほどの陽気だったと覚えています。
あの日は、久しぶりの休暇でした。
艦隊勤務でずっと洋上にいたために、貴女と会う時間をなかなか作れなかった私は、艦《ふね》から陸《おか》へあがったその足で、すぐに貴女のもとへ駆けつけたのでした。
ふたりでただ散歩するだけで、くつろいだ気持ちになれました。私は、貴女と所帯を持ち、いろんな話をしながら夕餉《ゆうげ》をともにすることができれば、さぞ楽しいだろうなと空想したものです。あるがままの愛情を貴女へ注げたらどんなにいいだろうと。
大海原を見つめていた貴女は、思い出したようにくすりと笑います。口許をおおった貴女の白い指には、まだ誰の指輪もはまっていません。私は、ほっと胸をなでおろしました。
「ゆうべ、兄が面白いことを言いましたのよ。ソクラテスの言葉なのだそうですけど、『ぜひ結婚しなさい。よい妻を持てば幸せになれる。悪い妻を持てば私のように哲学者になれる』ですって。兄は変わり者ですから、悪妻をもらって大哲学者になるんだって言ってましたわ。稔さんは、どちらがよくって?」
「よい妻のほうがいいですね。哲学という柄でもないですし、考えるのは苦手ですから」
貴女と結婚することを考えていた矢先にそんなことを言われ、思わずどぎまぎしてしまいました。
「稔さんのようなやさしい方に嫁ぐ人は幸せね」
貴女は、まるで夢を見つめるようにまぶしそうに海の彼方へ目をやります。それから、ふと浮かない顔をしました。
「どうかしましたか?」
「なんでもありませんわ」
「話していただけませんか。私になにかできることがあれば、いくらでも力になりますから」
「わたしの願いが叶うことなんて、きっとないでしょうから。いつも、気持ちと逆の方向へばかり行ってしまいますのよ」
「そんなことはありませんよ」
「ごめんなさい。せっかく連れてきていただいたのに、しめっぽい話をしてしまって」
貴女はそっと唇を噛み、さびしそうに背中を丸めてしまいました。心なしか、貴女の瞳が潤んでいるように見えます。
喉が渇いたという貴女を連れて浜辺の茶屋へ入りました。店の婆やが冷えたラムネを二本持ってきてくれました。
きらめく波の向こうを九月の船が通り過ぎます。
――今しかない。
三日後には、私はまた海と空へ戻らなくてはなりません。今度貴女に会えるのは、ずっと先になってしまうでしょう。
ふんぎりをつけた私は、妻になって欲しいと思い切って胸の内を打ち明けました。貴女の手にしたラムネの瓶が震え、なかのガラス玉がかたかたと硬い音を立てます。貴女は、目を伏せて黙ったままでした。
「すみません。お雪さんを困らせるつもりはなかったのです。忘れてください」
てっきり、私はほかにいい人がいるのかと勘違いしてしまいました。
「忘れることなんてできませんわ」
貴女の白いうなじがとまどいがちに紅く染まります。
「稔さんほど、私によくしてくださる方はおりませんもの」
ぽつりと言った貴女は、恥ずかしそうに私にもたれかかります。私は、そっと貴女の肩を抱きました。ぬくもりだけが心に満ちあふれ、胸の奥にいつもわだかまっていたさびしさが消えました。貴女との未来に想いを馳せ、美しい花が心に揺れます。どんなことがあっても貴女の幸せを第一に考えよう。晴れた空を見上げながら、そう誓いました。
あのまま時間がとまってくれたら、どんなによかったでしょうか。
私たちの愛は、運命の糸にあやつられるままでした。
なにもかもがままならない時代でした。時代のせいにしたくありませんが、個人ではどうにもならない現実があったことも事実です。戦争は個々人の事情などおかまいなしに、人生のすべてを縛ってしまいます。生活のすべてを国家へ捧げることを求めます。個人の自由はありません。とはいえ、貴女との愛を守るために手を尽くしたのかと問われれば、やはり悔いが残ってしまいます。
貴女を連れて大空を飛ぶ夢は潰《つい》えてしまいましたが、それは後生に預けておきましょう。生まれ変わった後でもご縁があれば、きっと出会えるはずですから。
もし来世でお付き合いさせていただいたら、今度こそ、貴女を手放したくはありません。なにもかも振り切って、貴女との愛情を守りたい。ふたりで命の花を精一杯咲かせたい。心からそう思います。
太陽は輝いています。
陽光を照り返す僚機がまばゆく輝きます。
九五式水偵の編隊は、滞りなく一路ダッチハーバーを目指しました。