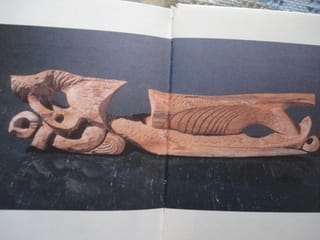今日やっとテレビとビデオが観られる環境へと。以前知人にあげたテレビデオを返したもらったばかりで早速ビデオを。
ついさっきまで観てたビデオは、ぼくの「子供が主人公の映画」ベスト1作品のー
①「犬のごとき人生」(スウェーデン、ラッセ・ハルストム監督)・・北海道の故郷を思い出すな。初恋をもまた・・相当古い映画だけど、詩情と笑いと哀しさに溢れた傑作
引き続いて観るつもりなのはー
②「運動靴と赤い金魚」(イラン、マジット・マジディ監督、1997)・・スウェーデン映画同様大好きなイラン映画だ
③「わが谷は緑なりき」(イギリス)・・全映画のベスト10に入れたい映画
④「太陽の帝国」(日英合作かな、大好きなSF作家バラードの自伝的作品)・・反戦映画として観てしまう
⑤「蝶の舌」(スペイン)・・詩情一杯のスペイン市民戦争でのファシズムの怖さを
⑥「ニューシネマパラダイス」(イタリア)・・最近の映画では何度も観返した映画
⑦「素晴らしきかな人生」(イタリア)・・貴重な歴史的証言
⑧「自転車泥棒」(イタリア)・・も忘れてた
⑨「わんぱく大戦争」(フランス)・・子供時代を思い出すな
⑩「泥の川」・・日本映画からも一つくらい選びたいので
ついさっきまで観てたビデオは、ぼくの「子供が主人公の映画」ベスト1作品のー
①「犬のごとき人生」(スウェーデン、ラッセ・ハルストム監督)・・北海道の故郷を思い出すな。初恋をもまた・・相当古い映画だけど、詩情と笑いと哀しさに溢れた傑作
引き続いて観るつもりなのはー
②「運動靴と赤い金魚」(イラン、マジット・マジディ監督、1997)・・スウェーデン映画同様大好きなイラン映画だ
③「わが谷は緑なりき」(イギリス)・・全映画のベスト10に入れたい映画
④「太陽の帝国」(日英合作かな、大好きなSF作家バラードの自伝的作品)・・反戦映画として観てしまう
⑤「蝶の舌」(スペイン)・・詩情一杯のスペイン市民戦争でのファシズムの怖さを
⑥「ニューシネマパラダイス」(イタリア)・・最近の映画では何度も観返した映画
⑦「素晴らしきかな人生」(イタリア)・・貴重な歴史的証言
⑧「自転車泥棒」(イタリア)・・も忘れてた
⑨「わんぱく大戦争」(フランス)・・子供時代を思い出すな
⑩「泥の川」・・日本映画からも一つくらい選びたいので