さて、久々に数値シミュレーション解析の話題を一つ。
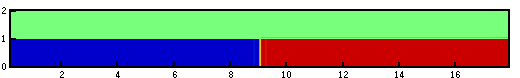
こちらは海陸風を簡単な構造で表現して計算した結果です。海陸風のシミュレーションはCFDの参考書籍でも良く取り上げられます。今回の計算では、計算領域の左半分を海上、右半分を陸上としています。初期状態では、左半分では既に海面からある程度の高さまで空気が十分に冷やされる一方、右半分では地面からある程度の高さまで空気が既に十分に熱せられており、ある程度の高さより上の層では温度は寒暖の中間の状態であると仮定しています。また、境界条件では海面上は冷源、陸面上は熱源であるとしています。
地面及び海面付近では、海からの冷気が陸上に流れ込み、上空では陸上の暖気が海上に流れ込んでいる事がわかります。これに伴って海陸間で鉛直循環が生成されるわけです。このような海陸風の影響が局地気象の解析で重要となるのは、例えばこんな数値シミュレーションを行う場合です。

これは私が今年の春の気象学会で発表した新潟県上越地方のフェーンに伴う高温域の解析事例です。沿岸部における気温の誤差が内陸地に比べて大きく、沿岸部ゆえの海陸間の熱容量の違いに伴う熱的条件の考慮・反映が今後の課題となっています。そこで、このような局地気象の地域特有の特性を形作る基本的な現象のメカニズムのモデリングの検討を進めています。
熱流体数値モデルによる解析を進める際に、どのような初期条件や境界条件を与えるか・・・すなわちどのようなメカニズムや気象場を与えるかが重要になってきます。
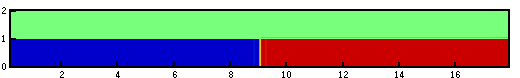
こちらは海陸風を簡単な構造で表現して計算した結果です。海陸風のシミュレーションはCFDの参考書籍でも良く取り上げられます。今回の計算では、計算領域の左半分を海上、右半分を陸上としています。初期状態では、左半分では既に海面からある程度の高さまで空気が十分に冷やされる一方、右半分では地面からある程度の高さまで空気が既に十分に熱せられており、ある程度の高さより上の層では温度は寒暖の中間の状態であると仮定しています。また、境界条件では海面上は冷源、陸面上は熱源であるとしています。
地面及び海面付近では、海からの冷気が陸上に流れ込み、上空では陸上の暖気が海上に流れ込んでいる事がわかります。これに伴って海陸間で鉛直循環が生成されるわけです。このような海陸風の影響が局地気象の解析で重要となるのは、例えばこんな数値シミュレーションを行う場合です。

これは私が今年の春の気象学会で発表した新潟県上越地方のフェーンに伴う高温域の解析事例です。沿岸部における気温の誤差が内陸地に比べて大きく、沿岸部ゆえの海陸間の熱容量の違いに伴う熱的条件の考慮・反映が今後の課題となっています。そこで、このような局地気象の地域特有の特性を形作る基本的な現象のメカニズムのモデリングの検討を進めています。
熱流体数値モデルによる解析を進める際に、どのような初期条件や境界条件を与えるか・・・すなわちどのようなメカニズムや気象場を与えるかが重要になってきます。


















