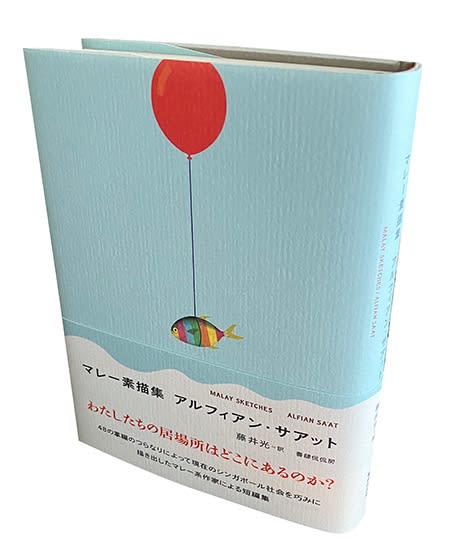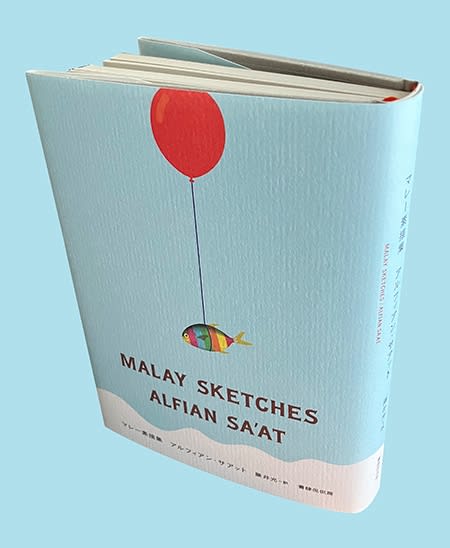ヒラール・キンタナ『雌犬』

表紙には、ジャングルの中じっと座る白い犬の姿。
警戒しているように見える。
本を裏にすると、表4には両腕を前に差し出す女性がいる。
それぞれを別々に見ると、犬と女性が向き合っているように思えるが、実はひと続きのイラストで、女性と犬は同じ場所にいるのに、お互いを見ていない。
生まれて間もない雌犬を、ダマリスがもらうシーンから物語は始まる。
母犬は毒物を食べて死んだばかり。
ミルクの匂いのする子犬を、胸に押しつけて彼女は家へと向かう。
長い砂の道の両脇に建つ家々は、壁や屋根に黒カビが生えていて、村の貧しさが窺われる。
断崖の上、急な階段を登った先にある別荘地の小屋に、彼女は夫と住んでいる。
別荘の管理をしているのだが、オーナーは忘れたかのように長年管理費を払ってくれない。
ダマリスは子どもができず、それがもとで夫との仲がぎくしゃくしている。
彼女にとって雌犬は、生まれてこなかった娘のような存在になる。
あるとき、犬はジャングルに逃げ、何日も戻らなかった。
痩せこけ帰ってきた犬を躾けようとするが、その後も何度も逃げ出してしまう。
そしてダマリスは犬が妊娠していることに気づく。
犬への愛情が落胆とともに憎しみに変わる。
それは人間に対するもののようで常軌を逸しているが、ダマリスの人生を覆う閉塞感が、彼女への同情を生む。
装画はPOOL氏、装丁はアルビレオ。(2022)