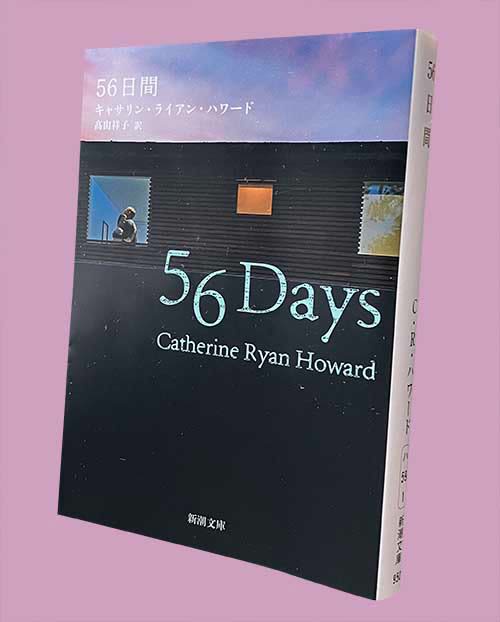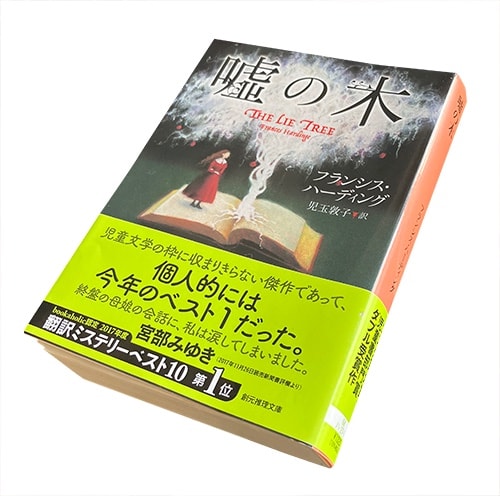ウィリアム・ケント・クルーガー『ありふれた祈り』

2人の男の子はなぜか憂鬱そうな表情だ。
彼らの後ろには青々とした芝生が広がり、近くの教会や遠くに見える高台の家、空と白い雲は美しいのに。
カバーの絵は、一見穏やかな世界を描いている。
しかし違和感を覚える箇所がある。
少年たちの前の路上に転がるビールの空き瓶と散らばるゴミだ。
1960年代、住人すべてが知り合いのような、ミネソタ州の小さな街に、語り手の13歳の少年が暮らしている。両親と姉、弟と。
少年フランクの日常が、丁寧に綴られている。
この物語の中には、好感を持てる人が何人もいて、少しずつ、この街の住人になっていくかのような気分に浸れる。
弟のジェイクは吃音があり、子どもだけでなく大人にもからかわれる。
辛さを身にしみて知っている彼が、自閉症で耳の聞こえないリーゼと信頼関係を築けるのは不思議ではない。
戦場での体験から牧師になった父は、厳しくも思いやり深い。
父に戦場で命を救われたというガスは、家族の一員のような存在。半端な仕事で食い繋いでいる。フランクとジェイクを子ども扱いしないところも好きだ。
彼らが幸せに暮らせればいいのにと願うのだが、事件は起こる。
装画はケッソクヒデキ氏、装丁は早川書房デザイン室。(2023)