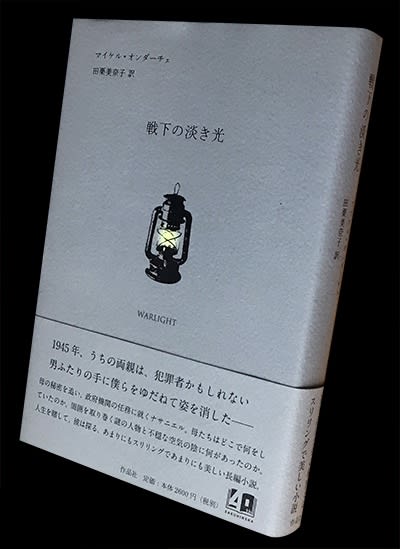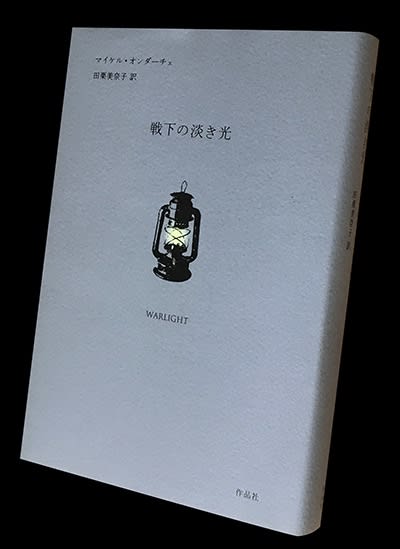ヘンドリック・フルーン『83 1/4歳の素晴らしき日々』

鮮やかなグリーンのカバーは、雑誌の表紙のように賑やかだ。
中央にあるのは若いモデルの写真ではなく、おじいさんの素描。意志の強そうな眼差しと、穏やかな口元、髪は跳ねているがダンディだ。
カバーをよく見ると、グリーンのほかには黒しか使っていない。2色のとてもシンプルなもの。
帯を外すと、周囲に散りばめられていた文字がなくなり、おじいさんが1人になる。パーティーが終わったあと部屋に1人残されたかのようで、同じイラストなのに、どことなく寂しげな表情に見えてしまう。
オランダのケアハウスに暮らす、83歳の老人が書いた1年の日記という体裁の小説。
はじめのうちは、もっと若い人が書いたものだろうと思っていた。しかし、読み進めるうちに、細かな人間関係やそれに対するおじいさん(ヘンドリック)の感情に親近感を覚え、本当に83歳の人が書いているのではないかと思えてきた。
1年の中に上手に収まるように書かれた構成を考えると、創作だと思えるのだが、これがもしも30代の人が取材をして書いたものだとしたら、少しがっかりする。
老人だからといって、悟りを開けたわけではないし、仙人でもない。この小説の中に卓越した知識を求めるのは間違いだ。
それでも「人生は五千ピースのジクソーパズルを見本なしに作るようなものだ」と老齢者に言われると、なるほどと深く納得する。
ケアハウスは俗世から隔絶された高潔な社会ではなく、ギラギラ、ドロドロしていて、ヘンドリックのユーモアが楽しい読み物にしている。
他の言語での表紙のデザインが気になったのでアマゾンで調べると、カタルーニャ語版ではおじいさんに色がついている。
血色よく、青いシャツに臙脂色のセーターとお洒落で、楽しそうな雰囲気が醸し出されている。
一方、ブラジルのポルトガル語版は、周囲を黒で囲んでいるため遺影のように見える。悪いジョークのようだ。
装丁は篠田直樹氏、装画はVictor Meijer氏。(2020)