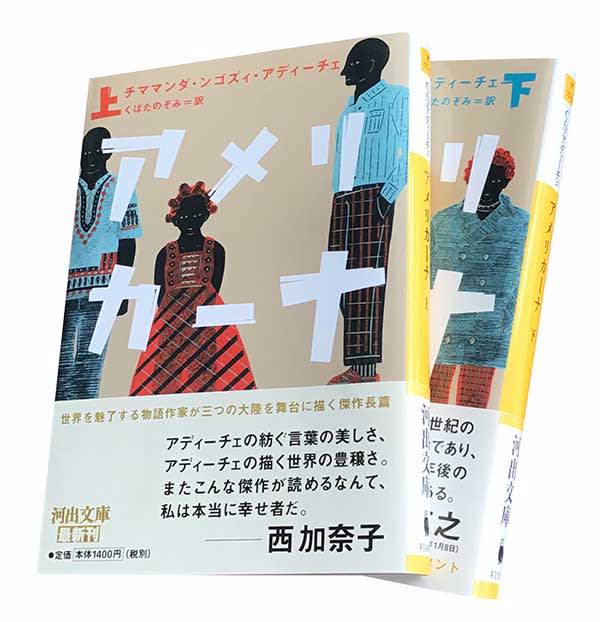ポール・オースター『サンセット・パーク』

蛍光ピンクが目立つ表紙のイラストは、レトロな感じをまとっている。
きっと古い時代の話か、あるいは現在を語りながら昔の話に自然と移行しつつ、気づくと現在にいるような物語なのではないか、そんなことを考えた。
ポール・オースターの自由自在で巧みな文章の流れに身を任せ、思いもよらない場所へさまよっていくことを楽しみにしていた。
ところが、そんな期待通りには進んでくれない。
細かく区切られた章ごとに、異なる人物の視点になり、物語の流れが途切れる。さあ、これからというところで差し込まれる別の人物は、先に登場した人物の違う側面を見せる。その繰り返しで、物語の世界は少しずつ厚みを増していく。
核となるのは、打ち捨てられた一軒家に不法に住む4人。経済的な困窮から、家賃を払わなくていいシェアハウスに集まってきた彼らは、それぞれにはずせない重しのような悩みを隠している。
そのうちの1人は、心に負った傷がもとで親と長年不通だったが、あることをきっかけに連絡を取ろうと決心する。
しかしそれは、シェアハウスに住んだことで傷が癒されたからではない。4人は少しずつお互いを理解していくものの、この場とは関係のない外との接触で彼らは変化していく。
そして肝心な場面は、どういうわけか読んでいる者の目に触れさせず、伝聞という形を取る。
考えてみれば、ポール・オースターがわかりやすい凡庸な小説を書くわけがない。ぼくが予想できるような展開になるはずがない。
そんなことを考えると、文中キーワードのように登場する映画『我等の生涯の最良の年』は、見ていないと片手落ちなのではと心配になる。
数多くの野球選手の名前も出てくるが、おそらく同好の士に共感してもらうためではなく、その話題の楽しさを感じてもらおうとしているのだと思う。だから、小説は理解するのではなく、ただ感じるだけでもいいかもしれないという気持ちにもなる。
装丁は新潮社装幀室、装画は西山寛紀氏。(2020)