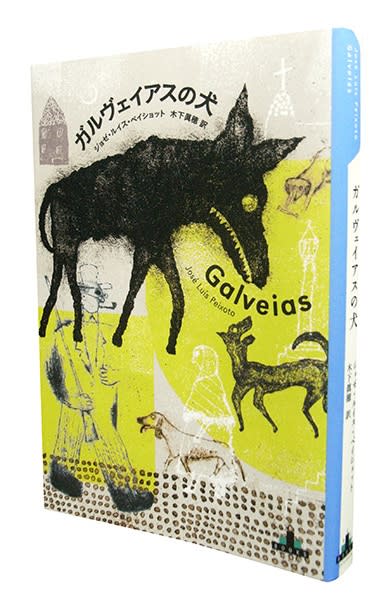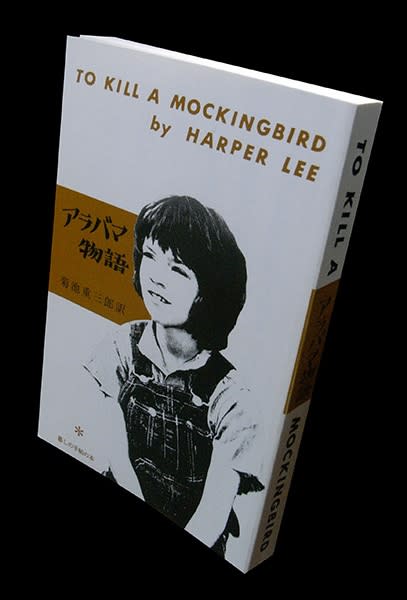ドナルド・E・ウェストレイク『さらば、シェヘラザード』

ドナルド・E・ウェストレイクの本が、絶滅しかけている。
そんな状況のなか出版されたこの本は、「ドーキー・アーカイヴ」というシリーズの中の1冊。
10人の作家の1人にすぎない。しかも少々色物扱い。
だからこんな色の表紙なのだろうか。
どぎつい赤に、紫色の唇。
唇の間に、英語のタイトルと著者名。
外国の本を思わせる作りだが、どうやら日本語版オリジナルのようだ。
ポルノ小説を書いている作家の話なので、こういう装丁になったのだと思うが、この作家を知らないと手に取りにくい。
この小説、ちょっと変わっている。
別の作家の下請けで、ポルノを書いて生活している主人公。能力の限界から行き詰まってしまう。
迫る締め切り。クビを切られる恐怖。
「1」と章番号を入れて、書き出したのは自分自身のこと。
ポルノを書かなければと思いながら、つい辛い現実を書いてしまう。
きっちり1章分(25ページ)で区切りをつけ、新たな章でポルノを書き始めるのだが、また途中で現実のことが混じってくる。
やがて現実と妄想と、ポルノの設定とがごっちゃになってしまう。
それでも悲しい習性からか、25ページで1章という設定は守り続ける。
実際の本のページ数は下にあり、主人公が書いている小説のページ数は上に同じ書体で入っている。
とても細かい仕掛けだが、物語の中に取り込まれていく感覚になる。
これを機に、ドナルド・E・ウェストレイクの復刊、または新しい翻訳が出てほしい。
装丁は山田英春氏。(2019)


ドナルド・E・ウェストレイクの本が、絶滅しかけている。
そんな状況のなか出版されたこの本は、「ドーキー・アーカイヴ」というシリーズの中の1冊。
10人の作家の1人にすぎない。しかも少々色物扱い。
だからこんな色の表紙なのだろうか。
どぎつい赤に、紫色の唇。
唇の間に、英語のタイトルと著者名。
外国の本を思わせる作りだが、どうやら日本語版オリジナルのようだ。
ポルノ小説を書いている作家の話なので、こういう装丁になったのだと思うが、この作家を知らないと手に取りにくい。
この小説、ちょっと変わっている。
別の作家の下請けで、ポルノを書いて生活している主人公。能力の限界から行き詰まってしまう。
迫る締め切り。クビを切られる恐怖。
「1」と章番号を入れて、書き出したのは自分自身のこと。
ポルノを書かなければと思いながら、つい辛い現実を書いてしまう。
きっちり1章分(25ページ)で区切りをつけ、新たな章でポルノを書き始めるのだが、また途中で現実のことが混じってくる。
やがて現実と妄想と、ポルノの設定とがごっちゃになってしまう。
それでも悲しい習性からか、25ページで1章という設定は守り続ける。
実際の本のページ数は下にあり、主人公が書いている小説のページ数は上に同じ書体で入っている。
とても細かい仕掛けだが、物語の中に取り込まれていく感覚になる。
これを機に、ドナルド・E・ウェストレイクの復刊、または新しい翻訳が出てほしい。
装丁は山田英春氏。(2019)