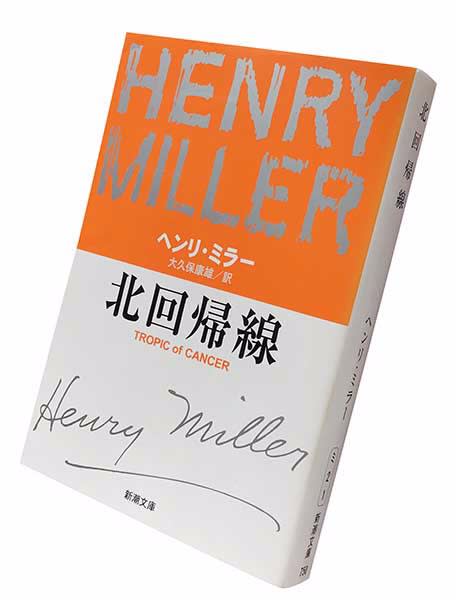ドナル・ライアン『軋む心』

表紙のモノクロ写真は陰鬱で、暗い物語を予感させる。
錆つき曲がった門扉と、ぬかるんだ深い轍。敷地はとても広く、門の造りはしっかりしていて、かつては裕福だったのに落ちぶれてしまった、荒んでしまったと告げている。
タイトルを大きく囲んでいる細い線の赤いハートが、荒れた心に手を差し伸べているようでもあるが、ところどころ欠けているのが気になる。
アイルランドが舞台の小説。
最初は建設業者ボビーの独白で始まる。
1人で暮らす年老いた父親をボビーは毎日訪ねているが、父とは憎み合っているようで、殺すことを考えている。最近、勤めていた会社の社長が社員の年金などを横領して逃亡、職を失った。自分のことを腰抜けで役立たずだと思っている。
この不穏な空気は、そのあとに続く20人のモノローグを読んでいるときにも忘れられず、何かが起こる気配を探してしまう。
ボビーの周囲にいる人たちが、断片的にそれぞれの生活を語る。そこにボビーの姿が見え隠れする。本人の内面の告白と、外から見えるものには差異があるもので、最初のボビーの腑抜けな印象が修正されていく。
1本の丸太を20人がナイフで削るように、ボビーという人物の形を作っていくのだろうと思っていた。
ところが、彼らの話は日常の細々した不満と生活の苦しさ。ボビーのことはそっちのけ、彼は端役でしかない。
ボビーと同様、仕事を失った男たちがいる。外国へ働きに行くことを考えているが、もっと貧しい国から働きに来ている男たちもいる。アイルランドの深刻な状況に息苦しくなってくる。
ボビーが関わる事件が発生するが、本人は相変わらず端に追いやられ、彼の姿はだんだん遠くなっていく。浮かんでくるのは、どこかで誰かが見ている小さな町の姿。
未来への展望がない物語だが、それでも小さな希望はある。一番最後、ボビーの妻の語りがそう思わせてくれる。
装丁は緒方修一氏。(2020)