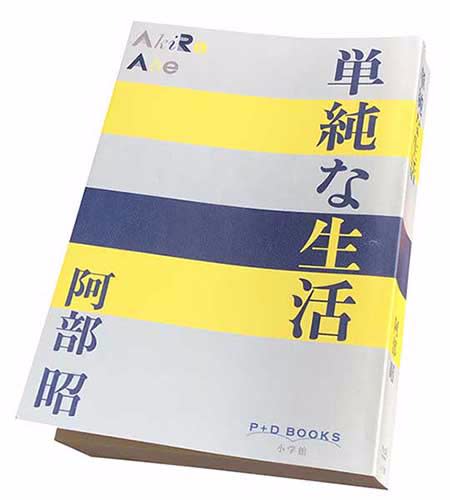フィリップ・ロス『ダイング・アニマル』
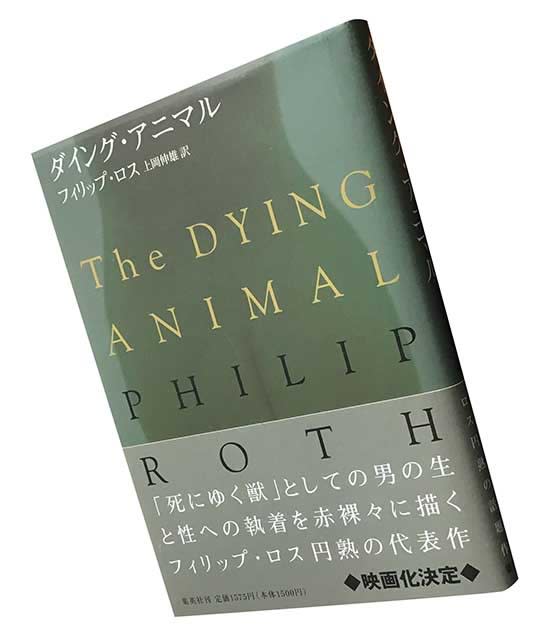
150ページほどの薄い本。
表紙にはぼんやりとした模様が入っていて、帯を外して初めてそれが女性の裸の臀部だとわかる。
こんな写真を使うのは、エロティックな描写があるからだ。
文化批評家のケペシュ氏は、大学でクラスを持つ62歳。テレビ出演もする彼の知的な授業は、多くの女子学生を魅了していた。
ケペシュ氏は、教師と教え子の関係でなくなったあと、彼女たちと性的な関係を持つ。それは何年も、何人も続いている。
そんな手練れでありながら、キューバ人の24歳の女性コンスエラと関係を持ったあと、彼女に夢中になってしまう。
ここまで書いて、この小説の魅力がまったく伝わらないことに気づいた。この短い小説には、無駄な箇所がない。細かい部分にも全体を形作る重要な要素があって、それを書いていくと100ページを越えてしまう。
ポルノまがいの描写がある。
扇情的な表現で、読む者を興奮させるのがポルノの目的であるならば、この小説は十分ポルノ的ともいえる。
ケペシュ氏は冷静に、若い女性の身体と性行為を事細かく描写する。
ケペシュ氏は、自分の息子がガールフレンドを妊娠させてしまったとき、身勝手な理屈を並べ、責任を取るなと説得した。
なんという男だろう。女性と真剣に向き合わない関係を、息子にも押し付けようとするとは。
決してケペシュ氏は女性を騙しているわけではない。何らかの罪があるわけでもない。だからケペシュ氏が断罪される理由はないのだが、コンスエラのことが頭から離れなくなり、まるで霊に取り憑かれてしまったように弱っていく姿を見せると、それは罰ではないのかと思ってしまう。
女性からすれば虫酸が走る存在かもしれない。でも老齢の男性から見れば羨ましい部分があるに違いない。
どちらにしても、最後は可哀想に。
装丁は米谷耕二氏。(2020)