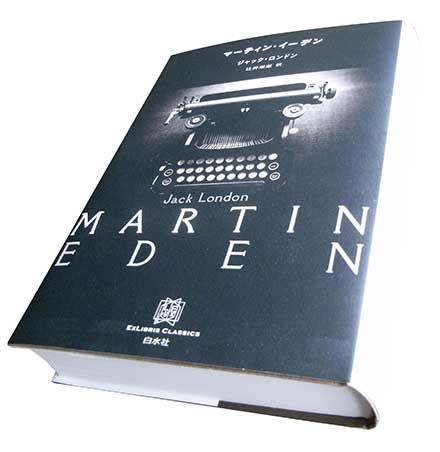ジャック・ロンドン『マーティン・イーデン』

タイプライターの写真が格好いいカバー。
大きな身体を折り曲げ、ジャック・ロンドンがこのタイプライターに向かっている姿が浮かぶ。
「自伝的」なので、本当のジャック・ロンドンの姿ではないはずだが、主人公マーティン・イーデンのほとばしる生命力が、実在した作家の姿と重なる。
これほど熱量の大きい人物、小説は思い当たらない。
ときに暑苦しく、鬱陶しいほど。
でも、パワー全開、全速力が若さなのだ。
10代で読んでいたら、しばらくは夜も眠れなくなったはず。
何かに夢中になりたいと焦り、がむしゃらに家の前を走るか、図書館で読み切れないほど本を借りてきただろう。
どんなに頑張っても結果が伴わず、貧困の底に落ち、周りの人間からも理解されない。
それでも希望を失わず、成功を手にしたハッピーエンド。と、ならないところが、この作者の心の傷を感じさせる。
装丁は緒方修一氏。(2019)
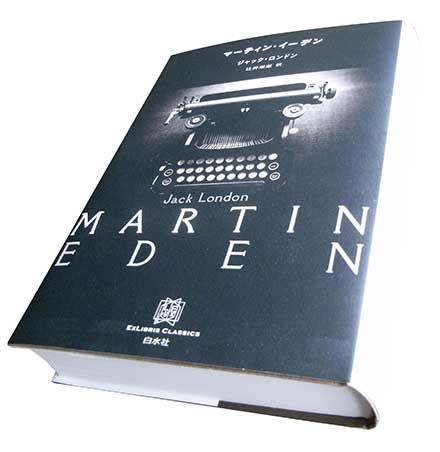

タイプライターの写真が格好いいカバー。
大きな身体を折り曲げ、ジャック・ロンドンがこのタイプライターに向かっている姿が浮かぶ。
「自伝的」なので、本当のジャック・ロンドンの姿ではないはずだが、主人公マーティン・イーデンのほとばしる生命力が、実在した作家の姿と重なる。
これほど熱量の大きい人物、小説は思い当たらない。
ときに暑苦しく、鬱陶しいほど。
でも、パワー全開、全速力が若さなのだ。
10代で読んでいたら、しばらくは夜も眠れなくなったはず。
何かに夢中になりたいと焦り、がむしゃらに家の前を走るか、図書館で読み切れないほど本を借りてきただろう。
どんなに頑張っても結果が伴わず、貧困の底に落ち、周りの人間からも理解されない。
それでも希望を失わず、成功を手にしたハッピーエンド。と、ならないところが、この作者の心の傷を感じさせる。
装丁は緒方修一氏。(2019)