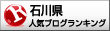寒中お見舞申し上げます。
寒の入りとともに、列島は広く雪模様。
拙ブログをご覧の皆さまは、お変わりございませんでしょうか。
くれぐれも健康にご留意のうえ、ご自愛くださいませ。
さて、僕は「雪」に対し畏敬の念を抱いています。
それは北陸で生まれ育ったせいかもしれません。
とは言え、当初はいいイメージではありませんでした。
厚い鉛色の雲に閉ざされた空から舞い落ちる冷たい雪は、
草木を覆い尽くし、色彩をモノトーンで蹂躙する「白い死神」。
子供だった僕には、この世を滅ぼす恐ろしい存在に思えたものです。
ところが、ある科学読み物をキッカケに一新しました。
<土の中にはたくさんの目に見えないび生物がいます。
その一部は、冬も生きていてかつどうしています。
秋、地面に落ちた葉っぱなどには栄養がいっぱいあり、
び生物たちが冬のあいだに土のようぶんに変えます。
じつは、そのかつどうをたすけているのが雪です。
気温がマイナス0度いかになっても、雪の下の地面はこおりません。
雪がふとんになってび生物を寒さからまもっているのです>
(※< >内出典不明/記憶の中の文面)
驚きました。
雪は生活を脅かすだけではなく、大地を育む役割を担うのだと知り、
印象が「恐れ」から「畏れ」へ変貌した時、
心の奥からあのクールビューティーが浮かび上がってきたのです。
ほんの手すさび 手慰み。
不定期イラスト連載 第二百四十四弾「雪おんな」。

現在の東京~埼玉~神奈川の一部に跨る「武蔵国」に
「巳之吉(みのきち)」という若い樵(きこり)がいた。
彼の仕事場は川向うの森、そこへ年老いた同僚と出かけるのが日課だった。
ある冬、帰り途で猛吹雪に見舞われ、渡し舟の小屋で一夜を明かすことに。
粗末な室内には火鉢も囲炉裏もない。
蓑(みの)を被り、嵐が過ぎるのを待つうち2人は寝入ってしまった。
夜半、顔に吹き付ける雪に気付いた「巳之吉」は目を覚ました。
頭をもたげると、きつく閉めたはずの戸口が開いているではないか。
老人が心配になり首を回すと、そこには白装束の女が。
息を呑むのと殆ど同時だった。
やにわに振り向くや、こちらを覗き込んできた。
不気味な光を湛えた瞳に射すくめられた。
指一本動かせず、喋れないのは恐ろしかったからだけではない。
見惚れてしまっていたのだ。
しばらく男を凝視していた女の口角が僅かに上がる。
青白く冷たい呼気に混ざり、凛とした声音が言葉を紡いだ。
『お前はまだ若くかわいい。 仲間と同じ目に合わせるのは止めよう。
だが忘れるな、今夜見た事は胸の中だけに留めておくのだ。
誰かに--- たとえそれが母親でも話をしたら、お前を殺す』
言い終わるや否や、女は踵を返し音もたてず出て行った。
慌てて飛び起き外へ出たが、白装束は烈しい吹雪に紛れて見えない。
諦めて戻った屋内に、凍りついた亡骸が横たわっていた。
一年後「巳之吉」は樵を続けていた。
独りで森に入り、木を伐り、適度なサイズに小分けする。
それを背負い母の待つ家へ帰る日々。
単純だが大変な労働で生計を立てる暮らしは、性に合っていた。
何より自然相手だから余計な話をしないで済む。
特に「あの夜」の事とか---。
そんなある日の帰り途、スラリとした一人の若い女に往き合った。
追いつき横に並んだ男の挨拶に答える声は、凛として可愛らしい。
歩きながら話をするうち「雪」と名乗る美少女の境遇が少しだけ知れた。
先頃、両親を亡くし、親類を頼って江戸へ行くところで、
向こうではどこかの大店か料理屋の女中の職を世話してもらえるはずだという。
男は思い切って尋ねた。
『お雪ちゃん、誰か“いい人”でもいるのかい?』
『いいえ、何の約束もありませんよ』
笑いながらそう言った彼女の整った横顔にどことなく懐かしさを覚えた。
今度は女が質問する。
『巳之吉さんは、どうなんです?』
『俺ぁ独り者だ。母ちゃんと暮らしている。まだ若いから嫁っ子の事は考えてもいねえ』
互いに身上を打ち明けた後、2人は押し黙り、寄り添って歩いた。
しかし、相手を憎からず思っているのは以心伝心。
村に着いた時、男は家で休んでいかないかと提案。
はにかみ躊躇いながらも申し出を受ける女。
息子が女性を連れてくる珍事に、母は大喜び。
旅程を延ばしてはどうかとまで勧めるのだった。
こうして縁が生まれ、彼女が江戸の土を踏むことはなかったのである。
五年後「雪」は美しいままだった。
男女10人の子を儲けたが、始めて村へ来た日と変わらず瑞々しい。
きめ細かな肌は、名前のように白く透き通っている。
大概、田舎の嫁は早く年を取るのに、何故?
村人たちは、彼女に常人とかけ離れた不自然さを感じ「畏敬の念」を禁じ得ないのだった。
もっとも当の夫は、露ほども気にしていなかった。
別嬪の恋女房と可愛い子供たちに囲まれ、毎日が幸せだった。
----- 好事魔多し -----
行燈の光の下で針仕事をしている女に、不意にこう切り出した。
『お前がそうしているのを見ると、18の年に遭った女を思い出す。
お前のように色が白くて。そっくりだったよ』
刹那、針が止まった。
ついに禁を犯した男はまったく気が付いていない。
手元を動かしながら目線を落としたまま、女が話の穂を継ぐ。
『--- へえ、初耳。続けてくださいな』
舟小屋で過ごした恐ろしい一夜。
凍死した相方と、白装束の美女。
洗いざらい打ち明けてしまった。
『あれは人間じゃなかった。
およそこの世のものに思えないほど恐ろしく、綺麗だった。
もしかしたら、夢か幻、かもしれないと考えてしまうんだ』
眉根を寄せ、哀し気に歪む女の顔。
涙で潤んだ瞳は、暗く沈んでいた。
その奥に不気味な光が湧き上がる。
確かに「あの夜」に見た、赤目だ。
『夢でも幻でもない、現(うつつ)だ!
それは私!「雪」です!
誰かに話したら殺すと言ったはず!
--- この子達さえいなければ ---』
枕を並べ寝息を立てている小さな命の方を振り返った途端、
憤りで沸騰寸前の感情に慈愛が水を差した。
いや、我が子だけじゃない。
何度も身体を重ね、苦楽を共にしたこの男も愛しい。
「あの夜」に岡惚れしたのは、私だ。
『今度こそ忘れないで。 もし、子供たちが不幸になったら。
今度こそ巳之吉さん、あなたを ---』
まだ結末を言い終わらないうちに、凛とした声はか細くなっていった。
そして輪郭が曖昧になり、光を照り返す細氷となって霧散していった。
それきり「雪」の姿を見た者は、唯の一人もいない。
原典は、明治37年(1904年)に出版された有名な一冊、
「ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)」著「怪談」の一節。
その大筋は変えず、脚色/演出したのが上掲拙文である。
こうした雪おんな伝承は日本各地に残っているが、
「ハーン」版の元になったのは、彼の家の奉公人から聞いた昔話といわれる。
ストーリーテラーの出身は、現在の東京都西奥部。
埼玉・栃木・山梨と境を接するだけに、いずれ山深い地域の奇譚だろう。
ここから先は全くの推測・想像だが---
著者が、物の怪と人間の異類愛憎物語に惹かれたのは、
自身の背景と無縁ではない気がするのは僕だけだろうか。
「ラフカディオ・ハーン」は、ギリシャ生まれ、アイルランド育ち。
複雑な家庭の事情から実父母と離別し、
不幸な事故により隻眼となってしばらく後、養育者が破産。
学業を中途で諦め、遠縁を頼りに渡米。
赤貧に洗われながら勉強を続け、新聞記者の職に就く。
その頃、英訳『古事記』を読んで興味が募り日本行を決意。
明治23年(1890年)太平洋を渡った。
島根県・松江に英語教師として赴任した「ハーン」の世話役に雇われたのが、
旧松江藩家臣の娘「小泉セツ」。
2人は辞書を片手にコミュニケーションを重ね、言葉の壁を乗り越え結婚。
「ハーン」は日本に帰化し小泉家に入夫。
『古事記』にある和歌から引用して「八雲」を名乗るようになった。
思うに「雪おんな」は彼の分身だ。
時は19世紀末。
当時のヨーロッパ人にすれば、江戸の面影を留めた日本は一種の“異世界”。
歴史・習慣・文化の違う日本人は異類とも言える。
また、武門出身の女性が夫に対し似たニュアンスを抱いていて不思議ではない。
結婚に至るまでには多くの困難があり、その後も大小様々な戸惑いがあっただろう。
だから「八雲」は魔界人に己を重ね合わせたと考える。
「巳之吉」と幸せを築きながらも、いつか綻びが生じ、
別れが訪れるかもしれないと不安を抱えた彼女に。
そして、彼女は愛する伴侶の化身だ。
何故なら「雪」は「セツ」とも読めるのだから。