いまどきの三月人形。
小黒三郎作。
遠方の孫の三月人形で楽しむ。

曲げわっぱに収まります。
作る方はどうやって納めるかが問われるそうです。
1段に1つの曲げわっぱに収まります。

40年前の
いのしし宅の三月人形。
当時はこれが主流でしたが。
流れはどんどん変わる。
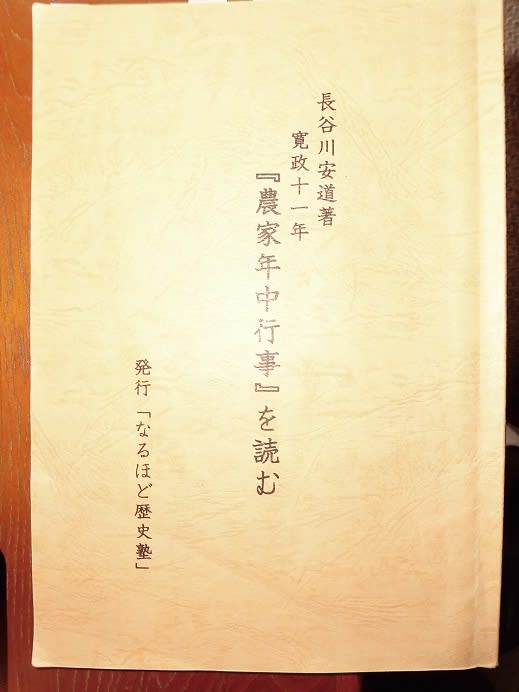
217年前(1799年)の長谷川さんの書かれた
三月節句のことが書かれています。
いわきでも永く続けられてきました。
217年前のいわきの暮らしぶりを
いのししの歴史サークル(なるほど歴史塾)で現代訳にしました、
寛政十一年農家年中行事・・・長谷川安道著より
ひも解いて見ますと
一.三月三日の雛事とは、
子供の節句として、草もち、白酒、あさつきや
乾し大根のなますなどは、第一の献立である。
その他、いろいろな備え物は
分量にしたがって思い思いのおくりものとしては
内裏雛、小山人形行列の箱入りなどあるいは、
菓子・せんべい等見つくろってやるのである。
一.桃、桜の花盛りにて、面白おかしく花見、遊山など百姓は、
そんな風には、やるものではない。
と子供のお祝いとして
行われていました。
これからも形が変わろうと
続けていきたい行事です。
日めくりカレンダーより
☆幸せって種みたい
北海道 主婦の方
種だから、
芽が出ないこともあるし、
丈夫に育って実がなることもある。
何より土に埋まっているから
見えないし気付けない。
と筆者が。















