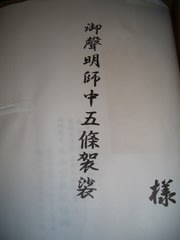先日、あるお寺にお邪魔した時のこと。
座敷用のテーブルの足の下に30センチはあろうかと思われる木材があてがわれていました。
これ何ですかとお尋ねすると、椅子に座ってちょうどいい高さにするための改造なのだそうです。
確かに、お寺の客殿は畳敷きで座布団に座るスタイルですから当然テーブルの高さも低いものになります。
しかし、最近は正座のできない人が増えて椅子を用意しなければならないことが多いのだそうです。(うちも同じですが)
それに、お寺の客殿で法事のあとにお斎をする方も増えてきましたから、椅子に座って食事をするための苦肉の策なのだそうです。
そんなことしなくても新しく買えばいいじゃないかって?
お寺の什器というのは檀家さん方の浄財によってそろえられたものですから、粗末にはできないんですよね。
普通お寺では座布団や高さの低いテーブルは什器として用意してありますが、さらに椅子をそろえたり、椅子用のテーブルを用意しなければならなくなってきたようです。
そこで困るのが収納場所、椅子は座布団と違ってかさばりますし、ある程度の数が必要ですから。椅子に合わせてテーブルもそろえるとなると・・・収納場所だけでなく費用の面でも結構大変です。
そして、この新しい客殿の使い方については「客殿で食事をするとなると普段の使い方と違うのでセッティングが大変だし、食事の後、食べこぼしもあるし食べ物の臭いがつくのですぐに掃除をなければならない。檀家さんに喜んで貰うためにやっているんだけれど気づいてくれる人も少ないし、モチベーションが上がらないな」というのが大かたのお寺の感想ではないでしょうか。
大抵この準備や片づけは黒子であるお寺の奥さんの仕事でしょうし、特に年配の方には重労働にもなりますしね。
確かに当寺でも客殿で食事をしている時は気がつかないのですが、食事の後の掃除の際に刺身の臭いやら、固形燃料を使った鍋物の臭いなんかが結構すごくてびっくりすることがあります。
でも、お年寄りに「よかったわ、移動しなくてお寺で食事ができるなんてありがたい。年を取ると場所を移動するだけでも大変なのよね。それに誰かの車に乗せてもらわなきゃならないと思うと肩身が狭くて気兼ねしちゃうし。」
とか、県外から来た方に、「遠くから来たので移動しなくて済むのはありがたいですね。移動時間がない分早く終わって帰れるし、しかもお寺は駅(甲府駅)に近いからそのまま歩いて帰れるから便利だし」
なんて喜んでもらえると励みになりますね。おそらく他のお寺さんも檀家さんの笑顔を見るためにがんばっているんでしょうね、きっと。
下駄をはいたテーブルの話からだいぶ脱線してしまったようですが、これも最近のお寺事情の一つでしょう。