「幸田露伴」1887-1947下町生まれ、電信技師で北海道へ、後文学に「風流仏」「五重塔」など男性的理想主義特異な作品を次々発表、尾崎紅葉と文壇を二分する。「頼朝」「運命」「一国の首都」など。1937年第一回文化勲章受章。
谷中の五重塔をモデルに、「五重塔」作品の最後の部分。
上人は最後に「江都の住人十兵衛之を造り川越源太郎之を成す」と銘を入れた。この銘は十兵衛に五重塔の棟梁の座を譲り十兵衛に助力した源太への報いである。
五重塔を建てたことと棟梁を譲ったことは同じ比重があると考えられている。
十兵衛は五重塔を建て偉大な棟梁として認知されたにもかかわらず、功績を源太と分けるのを許すとされている。
五重塔を建てても手柄を独り占めにしない十兵衛の姿勢が高く評価されている。
これだけの大きな仕事をやり遂げると、次の仕事への大きなステップがあるはずである。しかし十兵衛には五重塔の建立の後に新しい仕事が残っていない。
十兵衛が世間に称賛されることで仕事が終わっている。十兵衛が報われることを解決とすると、その過程を二度描くことはできない。報われることが終点である。
十兵衛は棟梁になって世間から注目され金も地位も得られる棟梁の座を手に入れた。
しかしそれに驕らない態度が貧しい人間とも金持ちとも区別される個性として高く評価されている。
特に谷中五重塔は、その付近で子供の頃遊んでいたので、思い出と寂しさは、一入である。
谷中五重塔放火心中事件は、1957年早朝に「五重塔」が、心中による放火で 焼失した。 この五重塔は、1908年(明治41年)に...。



「天王寺」谷中墓地は、開創時から日蓮宗であり早くから不受不施派に属していた。
不受不施派は江戸幕府により弾圧を受け、日蓮宗15世・日遼の時、1698年 強制的に改宗となり、日蓮宗14世・日饒、日蓮宗15世・日遼が共に八丈島に遠島となる。
廃寺になるのを惜しんだ輪王寺宮公弁法親王が寺の存続を望み、「慶運大僧正」を天台宗1世として迎え、毘沙門天像を本尊とした。
1833年 法華経寺の知泉院の日啓や、その娘で大奥女中であった専行院などが林肥後守・美濃部筑前守・中野領翁らを動かし、感応寺を再び日蓮宗とする運動が起きる。
しかし、輪王寺宮舜仁法親王の働きにより日蓮宗帰宗は中止となり「長耀山感応寺」から「護国山天王寺」へ改号した。
「富くじ」1700年(元禄13年)徳川幕府公認の富突(富くじ)が興行され、目黒不動、湯島天神と共に「江戸の三富」として大いに賑わった。1728年 幕府により富突禁止令がだされるも、興行が許可され続け、1842年 禁令が出されるまで続けられたという。
谷中七福神、毘沙門天・天王寺



東叡山輪王寺の住職である「公弁法親王」が、廃寺となるのを惜しみ、 天台宗寺院として存続することを幕府に説いて認められ、 願主は輪王寺宮公弁法親王、
大檀那は5代将軍 徳川綱吉、 台宗第1世に千駄木大保福寺の慶運大僧正、のちの長野善光寺中興 を迎え、本尊も、 当山が寛永寺の北方に位置するところから、
やはり延暦寺の北方にある鞍馬寺が毘沙門天を奉安して国家安穏・仏法護持を祈願しているのにならって、 比叡山飯室谷円乗院より伝教大師親刻とされる
毘沙門天立像を移して新本尊とした。
ちなみに本尊は明治になって現在の阿弥陀如来坐像にかわりましたが、 この毘沙門天は江戸の昔より、「谷中七福神」の1つとして信仰を集めている。
本堂 受付


幸田露伴の小説『五重塔』のモデルとなった五重塔は、1908年に天王寺より寄贈されたものであった。1957年に谷中五重塔放火心中事件で焼失するが、都が史跡に指定した。
五重塔跡は児童公園(天王寺公園)内にあり、公園に付随する形で駐在所がある。
「谷中墓地」と称される区域には、都立谷中霊園の他に天王寺墓地と寛永寺墓地も含まれており、徳川慶喜など徳川氏の墓は寛永寺墓地に属する。
また、谷中霊園は桜の名所としても親しまれている。中央園路は通称「さくら通り」ともよばれ園路を覆う桜の枝に花が咲くと、まるで桜のトンネルのようになる。
現在、公園型霊園を理由とした霊園内再開発の途上にあり、公園スペースにするための更地化のため、使用料の払われていない箇所の無縁仏への改葬や
スペースの障害となる大木など木々の伐採が進められている。
著名人の墓が多い、天津 乙女(1908〜1980)宝塚歌劇女優・鳥居 栄子、南摩 羽峯(1822〜1909)国学者、中村 中蔵(1809〜1886)
歌舞伎役者、福知 櫻痴(1841〜1906)、劇作家・福知源一郎、高橋 お傳(1850〜1879)古着屋吉蔵殺し、川上 音二郎等


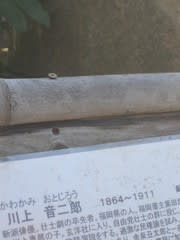
「徳川慶喜」1837-1913 最後の15代将軍 大政奉還を泰上し、徳川幕府の終幕を引いた。長州の水戸孝允は「家康の再生を見るようであった」評している。



「長安寺」臨済宗妙心寺派寺院の寺は、大道山と号し、老山和尚禅師(1724年寂)が開山、長安軒として安藤右京亮屋敷内に創建、1712年 大道山長安寺の寺号が認められ、
当地に移転したという。上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場22番札所、谷中七福神の寿老人。
七福神、寿老人・長安寺



「板碑」は、開基をさかのぼることおよそ400年も前で、長安寺開基以前、この地には真言宗の寺があったと伝えられ、これらの板碑と何らかの関連があったと思われる。
「狩野芳崖墓」明治初期の日本画家で、1828年 長府藩御用絵師狩野晴皐の長男、長門国長府(下関市)に生まれ、19歳の時江戸に出て、狩野勝川院雅信に師事。
橋本雅邦とともに勝川院門下の龍虎とうたわれた人物。
その代表作「悲母観音図」「不動明王図」(ともに東京藝術大学蔵)は、いずれも重要文化財である。
明治21年、天心・雅邦とともに東京美術学校(現東京芸術大学美術学部)の創設に尽力したが、開校間近の同年11月、61歳で没した。
妻ヨシとともに眠る。
長安寺本堂前、山号大道山

「瑞輪寺」は、日蓮宗・由緒寺院。山号は慈雲山。 天正19年-日本橋馬喰町に創建。 慶長6年-神田に移転した。
慶安2年-谷中の現在地に 明治元年-上野戦争により全山焼失するが以降再建を図る。
平成18年中本山から本山(由緒寺院)に昇格され、 塔頭として浄延院、躰仙院、正行院、久成院、本妙院がある。
江戸十大祖師の一つとして、除厄・安産飯匙の祖師と称され、 江戸時代は身延山久遠寺の江戸触頭であった。



次回は、寛永寺・上野へ









