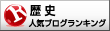加賀藩の隊長は、永原甚七郎と言った。甚七郎は、水戸浪士の疲れ切った様子を見て、敵とは言え、同じ武士として見るに忍びないと、白米二百俵、漬物十樽、銘酒二石、スルメ二千枚を新保の陣中に送った。
食べ物だけではなく、酒やつまみまで提供された水戸浪士は、感激したに違いない。
さらに、敦賀に送られてからも、士分には一日一汁三菜、士分以下には一汁二菜のほか、薬用として一日酒三斗(1斗=18リットル=10升)、鼻紙、煙草、衣類などを供給したという。正月になると鏡餅や饅頭、酒樽などが与えられた。この金額は一日二百数十両にも及んだ。
さらに、甚七郎など金沢藩士は、公卿や慶喜に対し、助命運動まで行っている。
このような寛大な処置が一変したのは、田沼玄蕃が幕府総監として敦賀に赴いてからである。田沼は、水戸付近における天狗党との戦いで、天狗党に苦汁を舐めさせられていることもあり、天狗党を悲惨な境遇に陥れた。
五間に八間(約9M*15M)の真っ暗なニシン倉庫十六棟に浪士を押し込め、朝夕に焼きむすび1個づつにぬるま湯だけしか与えなかった。
甚七郎たちは、この処置に腹を立て、田沼の命令は受けたくないと、600名の藩士とともに金沢に引き上げてしまったくらいである。
時に、慶応元年一月二十九日。
この逆境も長くは続かなかった。
同年二月四日。武田耕雲斎以下24名が斬首にあったのを皮切りに、数日に亘り、353名が斬り殺されたからである。
近世に繋がる幕末を考えると、非常に人間の持つ残虐性の危うさというものを感ぜずにはいられない。
水戸の場合も、新撰組の場合も、イデオロギーを飛び越えて、結局は自派の都合のいいように各人が行動してしまったという面がある。
そこには、正義も悪もない。ただあるのは、自派と他派だけである。
水戸には、黄門さまがいて、烈公と呼ばれた尊皇攘夷の雄とも言える斉昭がいて、弘道館という日本一の藩校もあった。
だが、幕末は内紛でごちゃごちゃになってしまった。
内紛であるから争う複数の派閥がある。幕末の水戸の場合は、天狗党と諸生党であったわけだが、どちらがいいとか悪いとかいうことではない。
ルワンダにおいてツチ族がフツ族によって大量虐殺されたのは1994年。あまりに近年に起こった虐殺に驚いたのであるが、日本人においても一歩間違えば、水戸の内紛のように血で血を洗う政争が起こりかねない。
武田耕雲斎の辞世の句がそんな気持ちをよく伝えている。
討つもはた 討たれるもはた あはれなり
同じ日本の みだれと思へば
話は戻るが、斬首の前に簡単な聴聞があった。浪士は、「武器を取って戦ったか」と聞かれた。病死した24名を除く799名のうち、353名が武士の名誉のために、yesと答えたのである。否と答えれば、助かったのであるが。
最後に、山国老人という70を過ぎて、この行軍に参加して、斬首刑に処せられた人の辞世の句が少しばかり爽やかであるので、紹介して、結びにしたい。
ゆく先は冥土の鬼とひと勝負

既に風化してしまったかのような看板が更に哀れを誘う
幕末の水戸藩(山川菊栄)岩波書店
↓よろしかったら、クリックお願いします。

食べ物だけではなく、酒やつまみまで提供された水戸浪士は、感激したに違いない。
さらに、敦賀に送られてからも、士分には一日一汁三菜、士分以下には一汁二菜のほか、薬用として一日酒三斗(1斗=18リットル=10升)、鼻紙、煙草、衣類などを供給したという。正月になると鏡餅や饅頭、酒樽などが与えられた。この金額は一日二百数十両にも及んだ。
さらに、甚七郎など金沢藩士は、公卿や慶喜に対し、助命運動まで行っている。
このような寛大な処置が一変したのは、田沼玄蕃が幕府総監として敦賀に赴いてからである。田沼は、水戸付近における天狗党との戦いで、天狗党に苦汁を舐めさせられていることもあり、天狗党を悲惨な境遇に陥れた。
五間に八間(約9M*15M)の真っ暗なニシン倉庫十六棟に浪士を押し込め、朝夕に焼きむすび1個づつにぬるま湯だけしか与えなかった。
甚七郎たちは、この処置に腹を立て、田沼の命令は受けたくないと、600名の藩士とともに金沢に引き上げてしまったくらいである。
時に、慶応元年一月二十九日。
この逆境も長くは続かなかった。
同年二月四日。武田耕雲斎以下24名が斬首にあったのを皮切りに、数日に亘り、353名が斬り殺されたからである。
近世に繋がる幕末を考えると、非常に人間の持つ残虐性の危うさというものを感ぜずにはいられない。
水戸の場合も、新撰組の場合も、イデオロギーを飛び越えて、結局は自派の都合のいいように各人が行動してしまったという面がある。
そこには、正義も悪もない。ただあるのは、自派と他派だけである。
水戸には、黄門さまがいて、烈公と呼ばれた尊皇攘夷の雄とも言える斉昭がいて、弘道館という日本一の藩校もあった。
だが、幕末は内紛でごちゃごちゃになってしまった。
内紛であるから争う複数の派閥がある。幕末の水戸の場合は、天狗党と諸生党であったわけだが、どちらがいいとか悪いとかいうことではない。
ルワンダにおいてツチ族がフツ族によって大量虐殺されたのは1994年。あまりに近年に起こった虐殺に驚いたのであるが、日本人においても一歩間違えば、水戸の内紛のように血で血を洗う政争が起こりかねない。
武田耕雲斎の辞世の句がそんな気持ちをよく伝えている。
討つもはた 討たれるもはた あはれなり
同じ日本の みだれと思へば
話は戻るが、斬首の前に簡単な聴聞があった。浪士は、「武器を取って戦ったか」と聞かれた。病死した24名を除く799名のうち、353名が武士の名誉のために、yesと答えたのである。否と答えれば、助かったのであるが。
最後に、山国老人という70を過ぎて、この行軍に参加して、斬首刑に処せられた人の辞世の句が少しばかり爽やかであるので、紹介して、結びにしたい。
ゆく先は冥土の鬼とひと勝負

既に風化してしまったかのような看板が更に哀れを誘う
幕末の水戸藩(山川菊栄)岩波書店
↓よろしかったら、クリックお願いします。