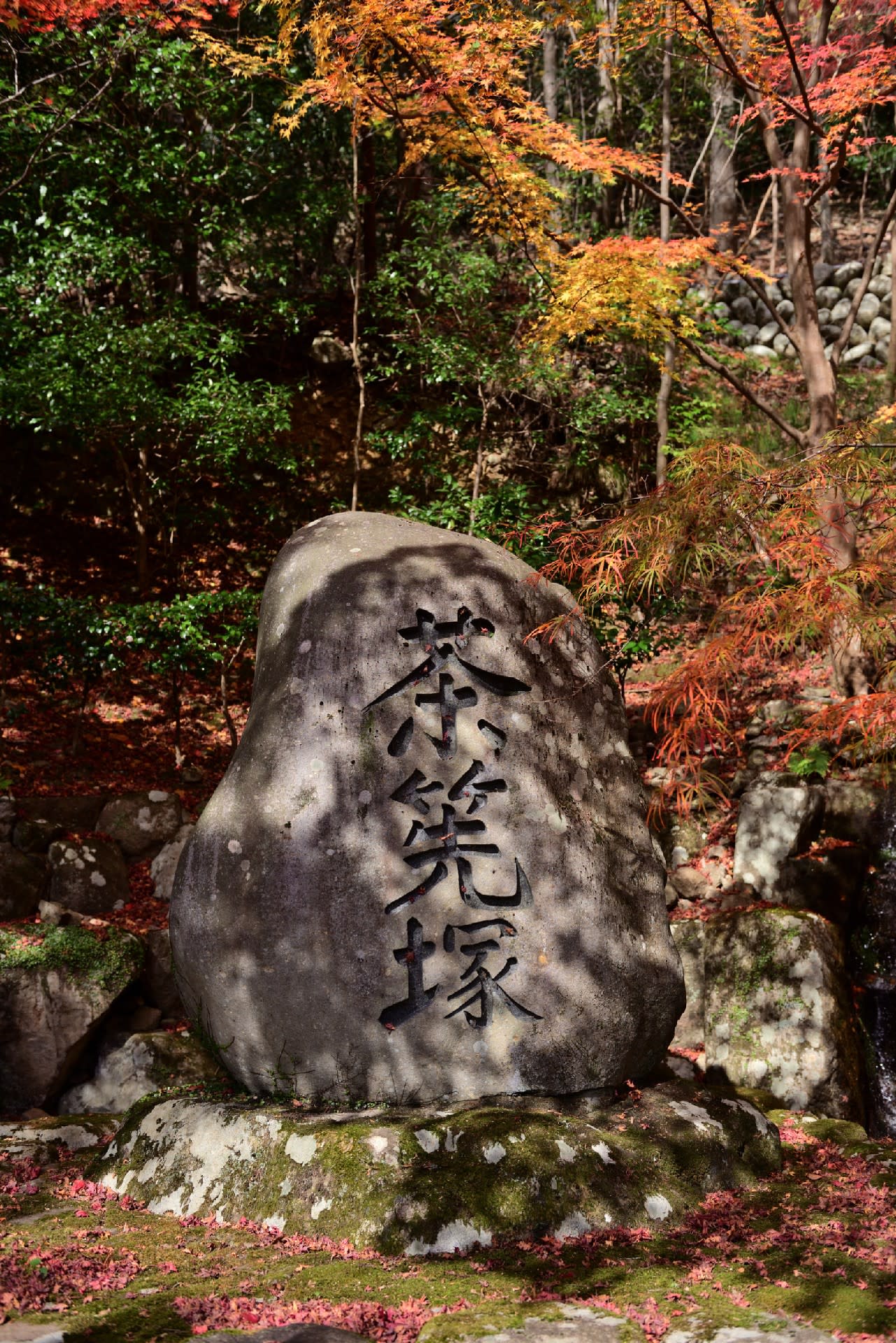(本堂 D810 AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED)
湖南三山の長寿寺からほど近い所に常楽寺があります。
長寿寺の「東寺」に対して、「西寺」と呼ばれており、長寿寺、善水寺とともに湖南三山の一つに数えられています。
今回は「西寺」、常楽寺の紅葉風景を紹介します。
常楽寺ではオールドレンズのAi Nikkor 135mm F2.0SとAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G EDを使用しました。
まずD4SとAi Nikkor 135mm F2.0Sでの撮影分
1

常楽寺は、滋賀県湖南市西寺にある天台宗の寺院。山号は阿星山、本尊は千手観音。
同じ湖南市に所在する長寿寺の「東寺」に対して、「西寺」と呼ばれています。
阿星山(あぼしやま)の北麓にある常楽寺は和銅年間(708~715)元明天皇の勅命よにり、
良弁(ろうべん)僧正が開基した阿星寺(あせいじ)五千坊の中心寺院として建立された。
また、紫香楽宮(742~745)の鬼門鎮護として栄えていく。しかし、延文5年(1360)火災で全焼する。
僧侶観慶によって再建されたのが現存する本堂で、明治31年国宝に指定される。
平成16年市町村合併で石部町と甲西町が合併して湖南市になり、翌年の平成17年秋に国宝を有する常楽寺、長寿寺、善水寺で湖南三山を立ち上げる。
御本尊(千手観音)は秘仏です。33年に一度御開帳をしております。次回は、令和18年(2036)の春頃を予定しております。(常楽寺HPより)
2

3
Ai Nikkor 135mm F2.0Sの柔らかなボケ味が気に入っています。

4

5

6
ツツジが咲いてました。

7
常楽寺は灯台躑躅が多く植えられていて、鮮やかな赤色は見応えがあります。

8

9

10

ここからはD810とAF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G EDでの撮影です。
11

12
三重塔(国宝)

13
本堂(国宝)

14

15
裏山に続く参道からは三重塔を高い位置から拝観できます。

16
灯台躑躅の赤が見事です。

17

18

19

20

21
本堂内で次回のご開帳が2036年という掲示板を見て、「その頃には二人とも極楽浄土やね?」なんて・・・

22

撮影日 2021年11月20日
撮影地 湖南三山 長寿寺( 滋賀県湖南市西寺)