
老人がコロナに感染を避け、
ニュース、外に出ない要請を受けて、
自室に籠り、頬杖4日、
買い出し、外に出ればコロナ忘れているのに、
テレビを見てしまう家の中では、
流石、立ち上がると足元が ❛よたり ❜
江戸期の成人男性は、旅の1日におよそ10里。
平地、自然を眺めながら歩いて、
8~ 10時間で約40kmを歩いた。
皇女和宮さんが中山道、2万人?の用心を、
引き連れて下向した時でさえ、おおよそ20キロ。
八王子の河童、一日の歩行距離、150m。
ニュース、外に出ない要請を受けて、
自室に籠り、頬杖4日、
買い出し、外に出ればコロナ忘れているのに、
テレビを見てしまう家の中では、
流石、立ち上がると足元が ❛よたり ❜
江戸期の成人男性は、旅の1日におよそ10里。
平地、自然を眺めながら歩いて、
8~ 10時間で約40kmを歩いた。
皇女和宮さんが中山道、2万人?の用心を、
引き連れて下向した時でさえ、おおよそ20キロ。
八王子の河童、一日の歩行距離、150m。
大人になってもガキ大将、
覗き込んで小心者に変える戒めのラブレター👇
覗き込んで小心者に変える戒めのラブレター👇
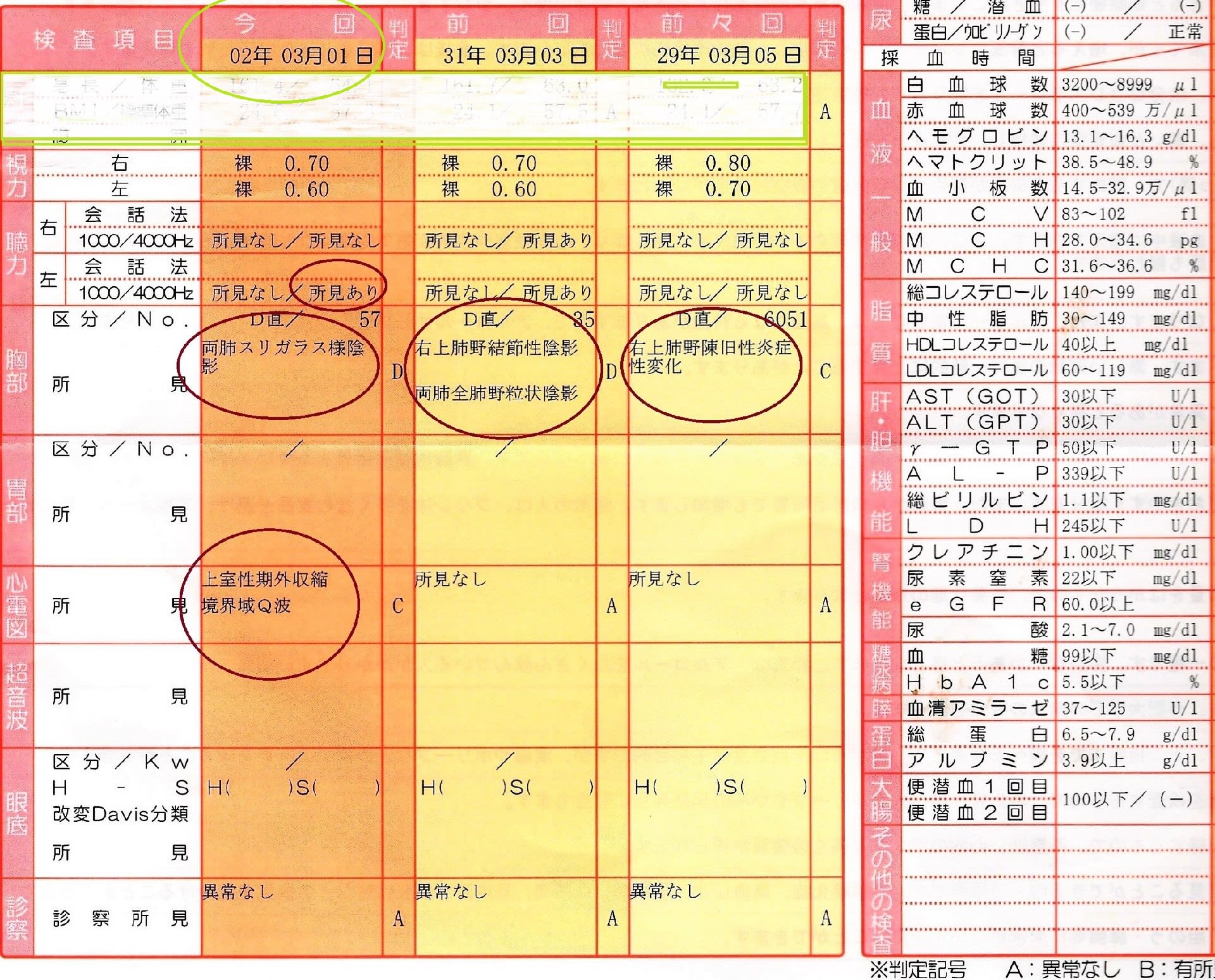
👆年々、肺機能が悪くなる診断。
👇その他はま~ぁま〜ぁと判断したのに、
結果報告には、なんと何項目もの指摘が・・・。
河童、首をうな垂れて、
ここでコロナに感染しては明日は無く・・と。
箱根の花の写真を眺めては、
サバの一夜干しをパク、パクリ。
明日の作戦は籠城、無手勝流で・・・
与太郎河童 vs コロナ。
👇その他はま~ぁま〜ぁと判断したのに、
結果報告には、なんと何項目もの指摘が・・・。
河童、首をうな垂れて、
ここでコロナに感染しては明日は無く・・と。
箱根の花の写真を眺めては、
サバの一夜干しをパク、パクリ。
明日の作戦は籠城、無手勝流で・・・
与太郎河童 vs コロナ。
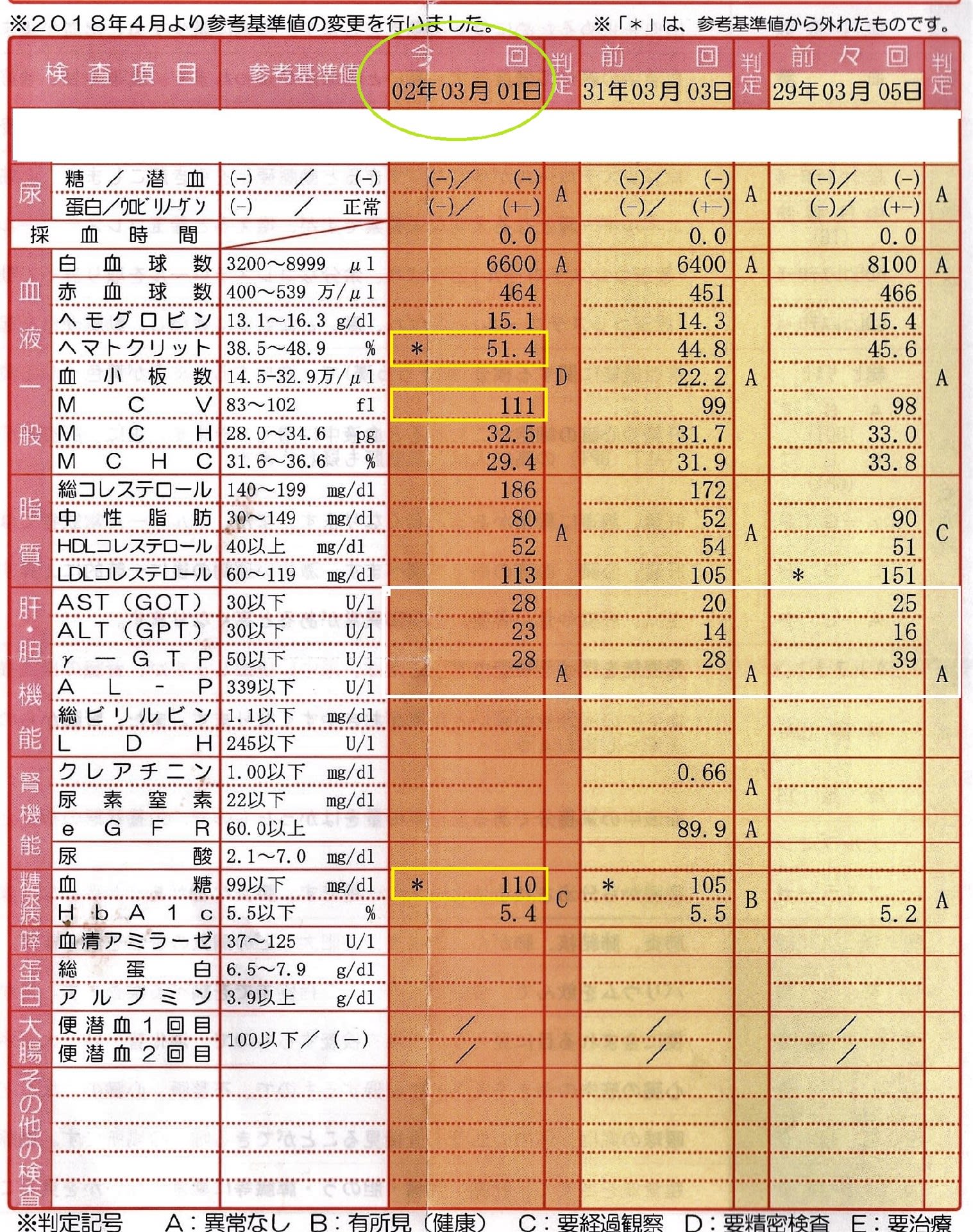
👆ヘマトクリックは、肥満、多汗症ではなく、
水分摂取が少ない人に現れる症状なのだとか・・・。
水分摂取が少ない人に現れる症状なのだとか・・・。







写真 2020.3.21 箱根にて





































































































































