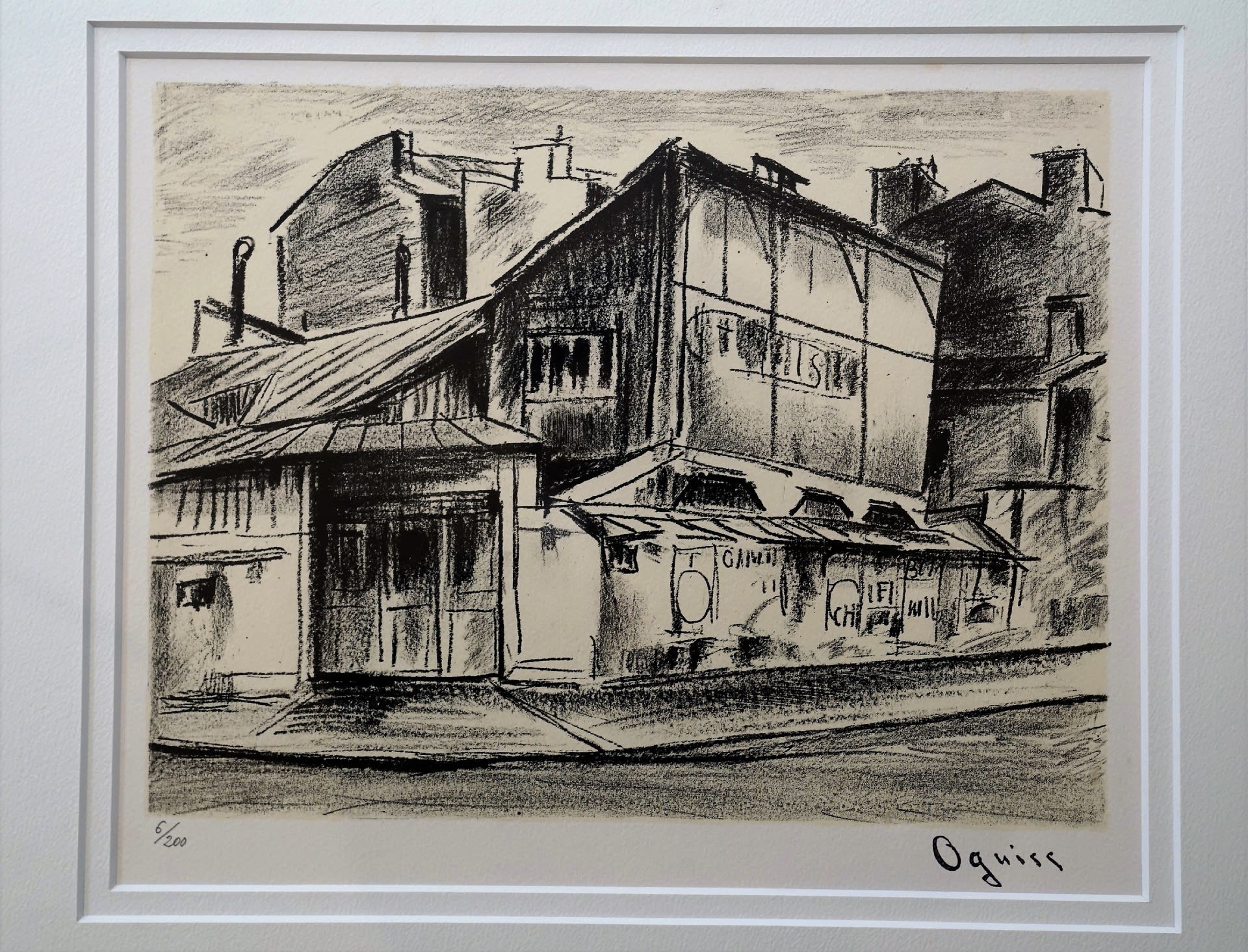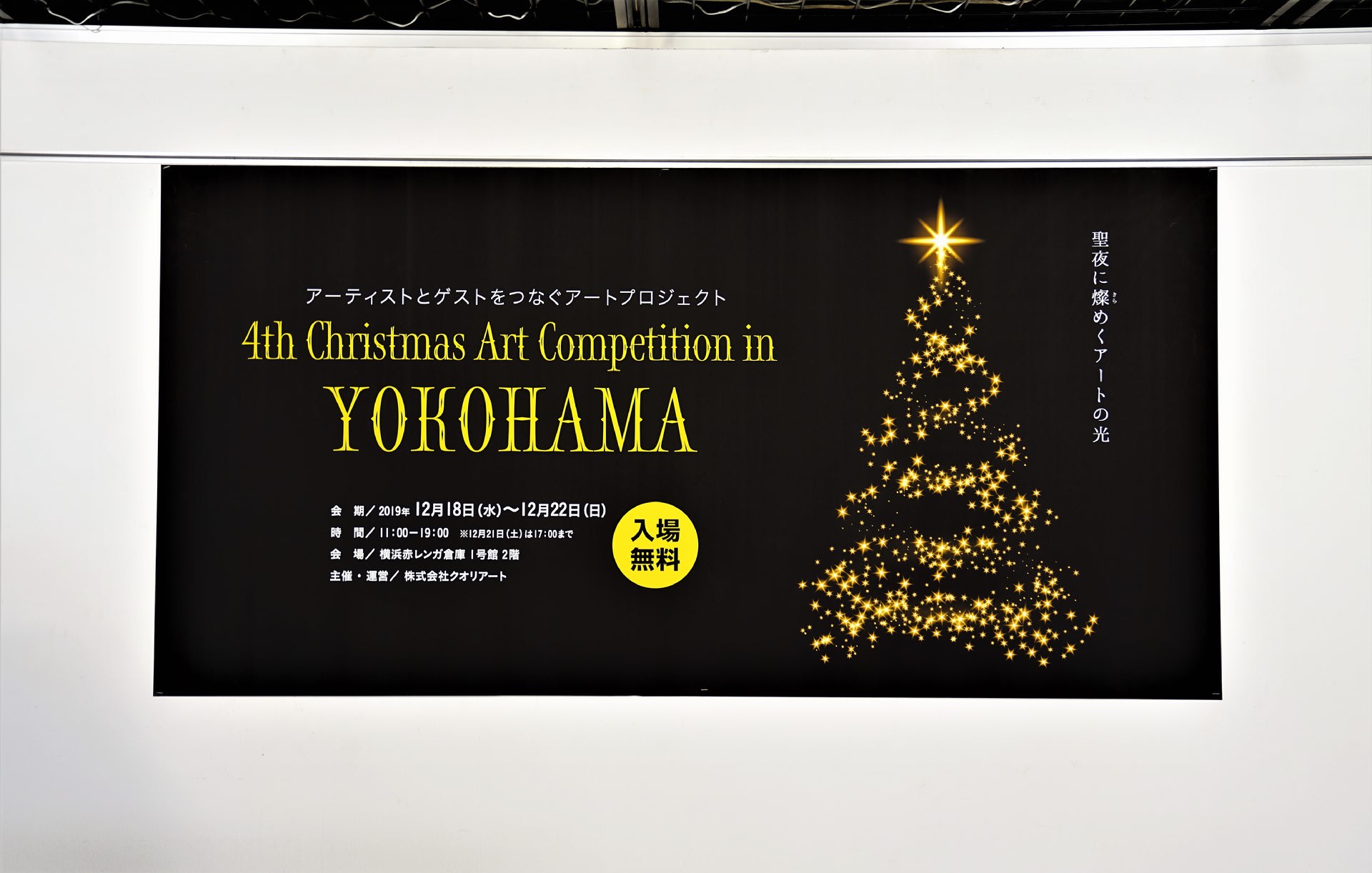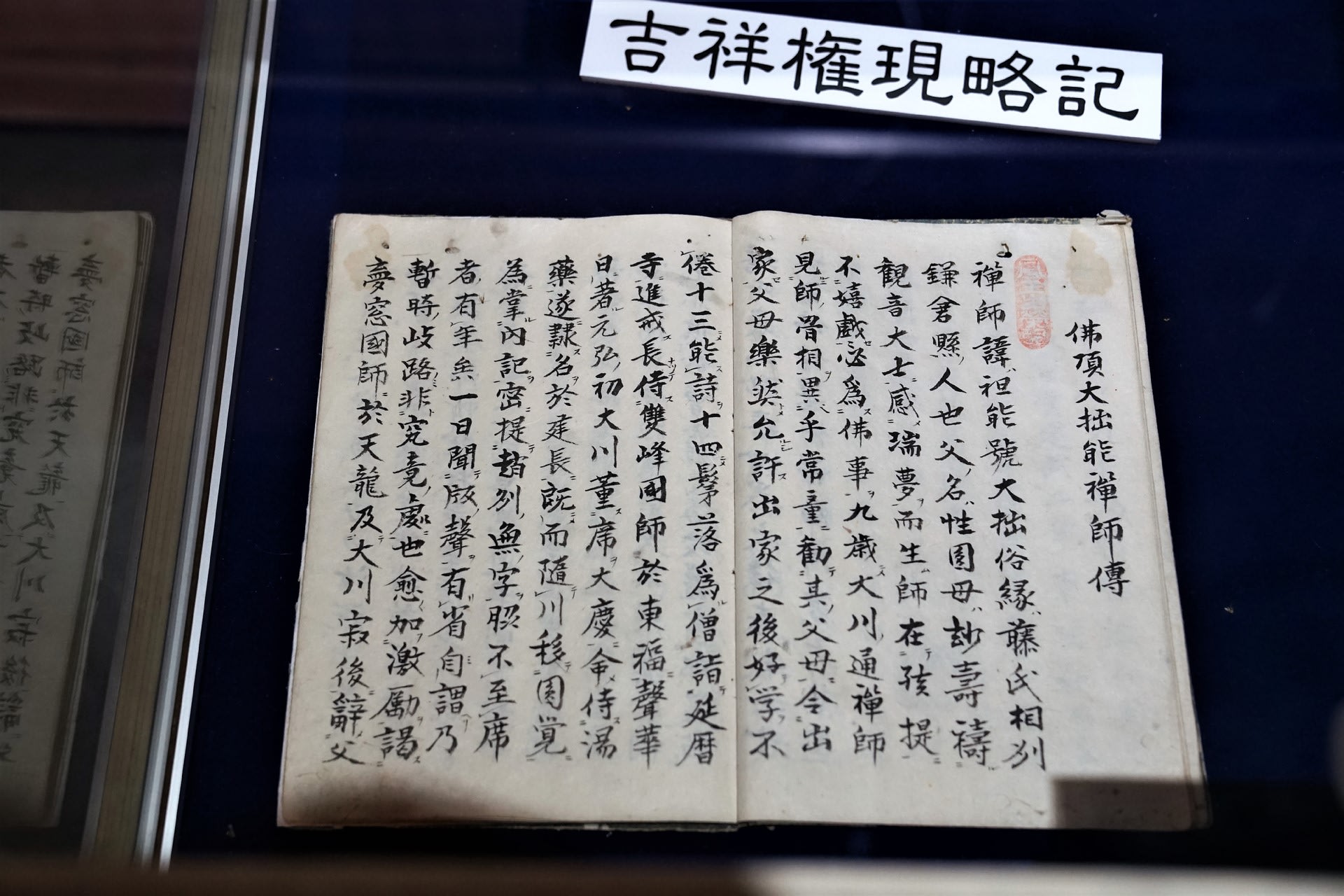身体の疲れが、思考能力の限界を過ぎて、
両手を伸ばし、横になったら3秒も持たず、
特効薬、「寝る」の世界を満喫した昨日。
目覚めて曇ってた眼鏡にをかけて、
「視力が弱くなった」と、ボヤキ・・、
気づいて「わしも、焼きが回った」と、
ぼ~っと、生きてる晴天の午後です。
誘いを受けて、
訪れた群馬県の川場村「吉祥寺」
禅宗、「壁のように動ぜぬ境地で真理を観ずる禅」となれば、
煩悩に生きる私には、
楼門迄、なんとなく歩幅が狭くなります。
禅宗の楼門は、聖地と俗界の境界。
入り口の両サイドに、金剛力士か、四天王を祀り、
楼上には16羅漢を祀っている。
👆吉祥寺の楼門も立派。
👇勅額「青龍山」は鎌倉時代の最後の天皇、
後光巌天皇(1338~1371年在位)の直筆なのだそうです。
👇金剛力士が、
👇楼上には、
仏の正しい法を長く世に居て、
迷う人々を導けと、お釈迦様を真ん中に、
煩悩をすべて断絶した最高の境地に達した16人。
頭を下げながら、煩悩、煩悩、煩悩無くなれば、困る。
今夜の「牡蛎雑炊」がいいと、決めたばかり。
楼門の階段で、
チョット嬉しい気分に・・。
木鼻の殻獅子が、ずり落ちないように支える かすがい が見えた。
大工棟梁と彫刻家の寸法取りの手違いか、
角の唐獅子がぴったり合わない施工。
精巧技術を誇るといわれる日本の技にあって、
不謹慎ながら、どこか親近感が生まれます。
👇唐獅子の指がクイット丸めたデザインも、
生まれたての赤ん坊の指を見た時の、
あの嬉しさが・・。
👇彫ったのは長野県小諸町から馳せた、
石工・小林虎之介さん。
長野県にはかなりの数の石工が、いたようですネ!
伊那高遠石工は集団化し、1187年、源頼朝から、
代々石細工職人として
日本国内で仕事が出来るとの許可をもらった、由緒書があり、
由緒に基づき、全国を行脚し、
青森県から山口県まで旅稼ぎをしている。
江戸城築城には、
八王子近郊にもかなり定住していた記録があります。
雪の武尊山の麓、頼朝と阿波姫の子、
大友能直の子孫が創建した吉祥寺は、
小高い山の向こうに・・。
👇川場かるた散策 ・え・ 枝分け巨(おお)き、姫子松。