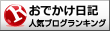明治45年、長男戍太郎は大忙しだった。
4月のタイタニック号が1512人の命を巻き添えにして北大西洋で沈没。
そのニュースは当初小さい記事でしかなかったが、ことの詳細が次々と日本に舞い込むと、冷たい海で、もがき苦しんで、息を絶えた姿にね自分を置き換えて、同情しきっていた。
その同情は半月後、死者276人を北海道夕張炭鉱の爆発に移行した。
小坂鉱山で働く抗夫達は、そのニュースを知ると、得体のしれぬ、巨大な空気に包まれた。
日々寡黙になり、鉱山事務所でも連日、この爆発事故を教訓にと、作業前に注意を促した。
抗夫たちの鉱山離れが生産を落とす、役員は必死であった。
事務所では、近隣の大館村から鉄道を利用して働く抗夫たちが、
「やめる」
と一言。
危機感を感じ始めていた。
人口二万人と六千人くらいの抗夫たちこの村で、去年村長に選任された小笠原勇太郎と、戍太郎を含めた五人の村会議員が鉱山を訪ね、役員と面会した
。
その帰り道、小笠原村長が戍太郎に
「義損金の責任者を太田さんと言ってしまったが、大変だろうが頼む」
「やまも他人ごとではないでしようから、な」
村では恩恵を施す鉱山のことを「やま」と呼び、「やま」という呼び方に誇りを持ち、親しみを感じていた。
戍太郎は、あくる日から、村の一軒一軒握り飯を背負って、「夕張の事故」を説明し、義損金を集め始めた。
陽差しが強くなり始めた五月、初めてのオリンピックに参加した団長が嘉納治五郎で、去年児玉道場に中山道博と共に訪れていた。
節三は「俺の稽古をずっと見ていたぞ」と、その日のことを戍太郎に得意になって説明した。
戍太郎の「義損金」集めは予想外の額になって、関係者を喜ばせた。
そんな折、とんでもない訃報が小坂村を震わせた。
明治天皇が崩御された。
そして九月の青山練兵場での大喪。
役場はてんてこ舞いであった。
輪をかけてコレラが全国的に流行りだした。戍太郎は、
「魚はダメ」「ワインでうがい、だ」「お守りを張れ」などとあわて、家中を駆けずり回った。
追い打ちの極め付きが間もなく年の暮れという日の「夕張炭鉱216名の死者」を報じた、新聞記事であった。
町長の小笠原勇太郎が戍太郎の家の門を沈鬱な顔でくぐった。
明治四十五年、大正元年は、町長の顔に象徴されたようにくれた。
雪が解け、泥の箇所をポン、ポン飛び越し、葉書を頭の上でくるくる回しながらミツが家に飛び込んだ。
勉強のできない、喧嘩好きの節三が大館中学受入許可を貰ったのだ。
「事件・事件だ、事件・・」
土間を小走りにミツは胸の中で嬉しくて思わず、そう叫んだ。
日野市の高幡不動へ出かけました。

仁王門をくぐります。
左に大きな土方歳三の青銅を見上げると

その後方に

五重の塔がそびえています
さらに奥へ、左手の石段途中に

弘法大師像が孤高を誇っています。
石段を昇りきると

大師堂が、隣に

聖天堂。さらに進んで、突き当りは

大日堂が・・・・
墓地へ行く前に左側の長い坂道を昇ると

高幡山金剛寺境内を隈なく見渡す、鐘楼があります。テクテクと坂道を下り
大日堂の横を

通り、土方歳三のお墓に行く途中

六体の地蔵が、行儀よく・・・可愛いいの なんのって・・・・
また後で・・・・
皆様のブログからは未知の世界を、 心の広さを、知ることができ、感性が豊かになり、
うきうきとしてきます。
あなた様のこれからがいい日々でありますよう、
お祈り申し上げます。
私も研鑽いたします。ありがとうございます。

弁慶と義経公(平泉・弁慶堂)
義経公 享年31歳 弁慶 享年38歳


弁慶が彫った像
高館城落城と共に義経と奮戦し衣川中で立ち往生悲憤の姿となります。
戦いに出る前、勝利の請願、三日三晩で彫り上げた自作像を地蔵堂に奉納
大男といわれる弁慶の繊細な胸の中を知らされる像。でしょうか・・・
腕を組み、歩幅を狭く歩く節三の顔からは、いつもの獲物を狙う精悍な顔つきが消えていた。
十五歳の少年が初めて経験する「大義名分のない他人の死」「相手の死を目的にしたのではない、結果としての死」
何もできない自分の力。得体のしれない圧力は節三を押しつぶし、節三は必死に圧力と対抗した。だが得体のしれない魔物は容赦なく節三を襲い離れようとしない。
雲間の朝陽が一面灰色だった靄を白く照らし変え始めたが、節三はすり減った高下駄の尾がジワリと冷えて来るのを感じながら、もやの向こうに消えていった。
謹慎三日目、新助と戍太郎が節三の喧嘩相手を見舞に行ったその夜、節三は二人に呼ばれた。
破れた袴の裾を手繰り上げ、いつもはドスンドスンと音を立てて歩く節三であったが、今日は神妙な顔つきになり、音を消して部屋の中に入った。
部屋に入ると、酒の匂いがする。新助と戍太郎が一杯ひっかけていた。
新助の盃に酒を注ぎながら戍太郎が
「節三、お前はこれからも喧嘩をするか」聞いた。
あっけにとられている節三に戍太郎がさらに
「相手が弱いと思ったら、ほどほどにしろ、児玉師範も言っていた。相当の腕前だと褒めていた。一、二番を競っているそうじゃないか。今回のようなことをまたしでかしたら、好きな柔道もできないようになるぞ」
変だ。節三は戍太郎の口調についていけなかった。
喧嘩相手の様子が聞けない。後回しになっている。
「売られた喧嘩はする」
しないとは約束しない節三であったが、部屋で反省しろと言われ引き下がった節三を、母のクニとミツが待っていた。
いきなりミツが
「よかったな、節三。先方さんは生きているんだと。巡査が言っていた意識不明になった、というのは、ただ寝ていただけのことだと、ただ、足の骨が折れて、夜中には、吐き気がして、夜中ええらい騒ぎになったらしいがな、それを聞いた巡査が父さんからお金をだまし取る芝居を作ったらしい、父さんもどの位、渡したか言わなかったけど相当のお金だったんだろうね、巡査は少しだけ先方さんに渡すと、そのままいなくなったということだ。花輪村の駐在に行ってそれがわかってな、血が昇ってどなたらしいけど、バツが悪いと思ったのか分からないけど、お前や私らのことを考えるといくらかホットしたって訳だ。帰りはお前の道場へ寄って師範とお会いになり、お前を通わせますからよろしくと、お願いして来てね、道中父さんと兄さんは、節三にはお灸をすえるつもりで黙っていようと示し合わせてきたようだ、よ」
節三はくたっと腰を落とした。
クニが
「喧嘩はやめられねぇのか」
とつぶやいた。
「うん」その返事は、するともしないとも取れる低い声だった。
「明日から勉強も道場も真面目に通いなさいよ。今日は早く寝なさい」
ミツは立ち上がりながら上機嫌で節三の肩をポン、ポンと叩いた。
事の前後が理解できないまま、いつの間にか深い眠りに節三は、あくる日、相変わらずの破れ袴に二人分の弁当を持って学校に行ったが、先生の眼を盗み教室を抜けだし、道場に向かって一目散に駆けだした。
次姉ヤエが血相を変えて、夫一蔵のいる母屋に走った。
ヤエは小坂村に続く毛馬内村の大地主の豊口家に嫁いで9年になる。
児玉道場から小坂村に帰る途中に豊口家はあり、腹が減ると夕飯を食べて帰ることもあった。
要二という二歳のやんちゃな男の子がいて、めったに合わない節三を発見すると、両手を上げてすり寄り、空中へ投げてもらうのが好きだった。
急な坂道を登りきると毛馬内村が一望できる場所に、長女ウメが嫁いだ横田家があり、ヤエは身の回りを世話をする「てる子」と帰るところであった。
坂を下りきった十字路の右が節三がいつも帰る道なのだか、出会いがしら五、六人の男たちに囲まれて大通りの外れにある神社の陰に消えていった。
ヤエが「喧嘩だ」と叫ぶや否や、背中の要二をテル子に預けると一目散夫一蔵のもとへ駆け込んだ。
一蔵は相手が五、六人と聞いて少し怯んだが、ヤエの実弟とあれば、勇気を出さなければならない、節三のことだから間違いなく喧嘩なのである。
もてもての優男、喧嘩はあまり得意ではなく、膝から足もとまでの小刻みな震えを感じながら神社へ急いだ。
澄み切った気合の掛け声と、怒鳴り声が交互に聞こえる。
もっと近くになると、その声がぴたりとやんで、節三が鳥居をくぐって歩いてくるのが見えた。
゜「節三君」
声をかけたが節三は、背筋を伸ばして何事もなかったような顔で歩いてくる。
一蔵を見ると
「ちょっと、やらかしました。どうってことないです」とにっこり笑いながら答えた。
「今日は、帰ります。今度、寄ります」
節三の眼の下から二筋の血が流れていた。
神社では、節三に投げられたのたのだろう、境内の下で膝頭を両手で押さえている仲間が、思案に暮れていた。
一人が一蔵の気配に、
「なんでもありません。境内から足を踏み外して」
と言い訳をしたが言ってる本人の頭からも血が鼻につたっていた。
三日後巡査が太田家の縁側にサーベルを置いて座り神社の出来事を伝えた。
「毛馬内の豊口さんは親戚になりますかね」
「こちらのお嬢さんが向こうの内裏さんだとか」
奥歯にものを挟メタ言い方が新助を苛立たせた。
新助は腕を組み、太田池に視線を向けた。
「一蔵さんが節三さんの喧嘩相手を、自宅で、介護したは、したんですが、その日は仲間が連れて行ったらしいですよ・・錦木の在の若者なんですが、しかしなんで毛馬内まで来て喧嘩したものか、まあ、どっちでもいいんですが、夜中、急に様態が悪くなったまま、いままだ意識がないって相手の家が騒ぎましてな、それでわしらも見過ごす訳に行かなくなりましな・・」
茶を啜る巡査の横眼がちらりと、新助の顔を撫でた。
「このまま、もしものことがあれば、ただの節三さんの喧嘩だけでは済まなくなるのかな、と心配しているところで」と続けた。
新助は終始無言のまま身じろぎしなかった。
嫁入り前のミツは次の間で「理屈が合わない話」と思いながら巡査の話を聞いていた。
長い沈黙の後立ち上がった新助は、奥の間から風呂敷包みを持ってきて「帰りがけに、見舞金として、渡しておいてくれまいか」と云いながら巡査に渡した。
小坂鉱山 事務所(復元)
毛馬内は南部藩時代南部馬の産地で売買されていた。400年続く盆踊りは、路上に篝火を焚いて道路の両脇を踊る、呼び太鼓、大の坂踊りは優雅で、情緒溢れている。
襦袢に鴇色の蹴出し、黒紋付きに水色の蹴出しを着て、豆絞りのの手ぬぐいを頬被りをする。
その踊りを五尺程の大太鼓が打ち手と持ち手が一緒なって何台も先頭を行く。
その大太鼓の革が馬の革で、透き通るような音色が耳に優しい。

鉱山事務所を見上げる元職員の夫婦
節三の母、クニは55歳になった
「節三を読んで来い」
新助が新年早々怒鳴った。
広間には新年恒例の新助の挨拶が始まろうとしていたが節三がいないのである。
クニは三女の「ミツ」と目を合わせ、瞼をパチパチはじいた。
ミツは羽織をクルリとお尻の上まめくりあげ、節三を呼びに行きかけたが、白いた足袋をはいた足がぴたりと止まり、回れ右をした。
座りなおしたミツを新助は「きょとん」とした顔でミツを所作を見ながら隣の席のクニに「どうした」ときいた。
クニは戍太郎の子「昌男」に視線を向けたまま唇をとがらせ、首をくね、くね、くねと振るばかり新助の問いにどう答えたらいいものか
「どうしたんでしょう」と答えるのが精いっぱい。
間髪入れず、ミツは背筋をピンと張ると「節三はもう暗いうちから出かけましたよ」「道場へ行きました」
新助も戍太郎も昌男も一斉にミツのほうを向いた。
新助の機嫌が悪くなる誰もがそう思った。
「正月は道場も稽古休みだと言ってたではないか」
昌男が不善と呟いた。
同年代には違いないが、節三は自分にはない自由さがあった。その自由は昌男にとって威圧を感じるものだった。
昌男は節三より1歳年下であるが昌男の父は新助の長男、戍太郎、節三は叔父さんになる。
幼いころ、末っ子の節三は可愛がられたが、新助の心には戍太郎の子、孫の昌男の存在が大きくなっていくこのころでもあった。昌男は太田家の継承者である。
去年の正月、お神酒を飲んだあと、台所で盗み酒をし大の字に寝てしまった節三であった。
新助は、去年出来事が脳裏に鮮明に浮かんだ。
腿を掌でぽんと打ち当てると
「稽古ならしょうがないか」
「節三もだいぶ腕を上げたようだからな。物事真剣に取り組むことはいいことだ」
躾けにうるさい新助も簡単に納得した。
機嫌を取り戻したし助に戍太郎が
「父さん明けましておめでとうございます」と一例ををした。
勝ち誇ったようなクニとミツがお互いに顔を見合わせ「つん」と顎をしゃくり上げ、腹の中でにやりと笑った。「今年の正月は穏やかに過ごせそうだ」とお互いに思ったに違いない。
節三は上り框でミツが渡したおせちのお重を抱えて雪道を急いだ。
新年のご挨拶を申し上げます。
オーチャード・ホールの生中継
日本を愛したジルベスターバレエの女王、シルヴィー・ギエムのバレエの最後の舞台を見たばかりです。
50歳を区切りと新年のカウントダウンに選んだ曲は「ボレロ」
30センチ四方だけで魅せる手の動き、指の動き、下肢の動き、腰の動き、
もう見ることは出来ないのだろうか。
何秒かでも踊ってくれないのだろうか・・・・
今年のカウントダウンは身じろぎできませんでした。
全身から出た言葉
見事でした
道場から聞こえる「タアーウ、タアーウ」の掛け声は節三だと高慶はわかった。
正月三が日の稽古は休みにしていたのだが、節三は稽古相手に五人の仲間を、児玉道場へ集まるよう命令していたのである。
高慶は節三が通う児玉道場の主である。
父児玉猪太郎の後を継ぎ、今では「秋田の児玉」と言わせるほどの猛者である。柔道五段、剣道五段と勇名を馳せていた。今でも定期的に上京しては講道館、有信館で腕を磨いている。
道場に通って1年あまり、節三の腕前は児玉門下生の年少組では誰もが相手にならなかった。大人でさえ投げ飛ばされるほどである。
もともと、喧嘩が強くなる為の柔道であった。今でもその気持ちは変わらないが人一倍の負けん気は、ますます磨きがかかっていた。
稽古に拍車をかけたのは、もう一つ原因があった。
前年、児玉師範の師、講道館柔道の嘉納治五郎、有信館剣道の中山博道が児玉を訪ねてきた時のこと、稽古を見た二人が節三の素質を褒めていたことを児玉が伝えたからでもあった。
嘉納は二年前クーベルタンの誘いでオリンピックの委員に就任し、今年は5回ストックホルムで団長として参加することが決まっていた。
「近所のおじさん」が俺を見ている。そう思っていた。
稽古が中断され一門正座で二人を紹介されるとあっけにとられた。、
有名な武道家がこんな東北の田舎道場で児玉師範と親しげに話している。
児玉のすごさをまざまざと知らされた。出来事であった。
その有名な武道家が自分の柔道を褒めた。「どうってことないです」といったものの、体から汗が噴き出でいた。
休みの規則を破ることはいいことではないが、柔道を磨く姿勢に文句はつけられまい。
母屋の窓から道場を見ている妻の寿子の背中にぼそりといった。
高慶は知らんぷりを決めた。
雪解けが始まった三月節三はまたまた、また事件を起こした。
五月、桜の蕾が枝で踊っていた。
悌三は節三を養子にすることを新助に申し出た。

1911年アメリカ太平洋沿岸のシアトルに講道館の伊藤徳五郎が道場を開く。
1912年1月1日 夏目漱石「彼岸過迄」を朝日新聞に連載開始。