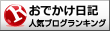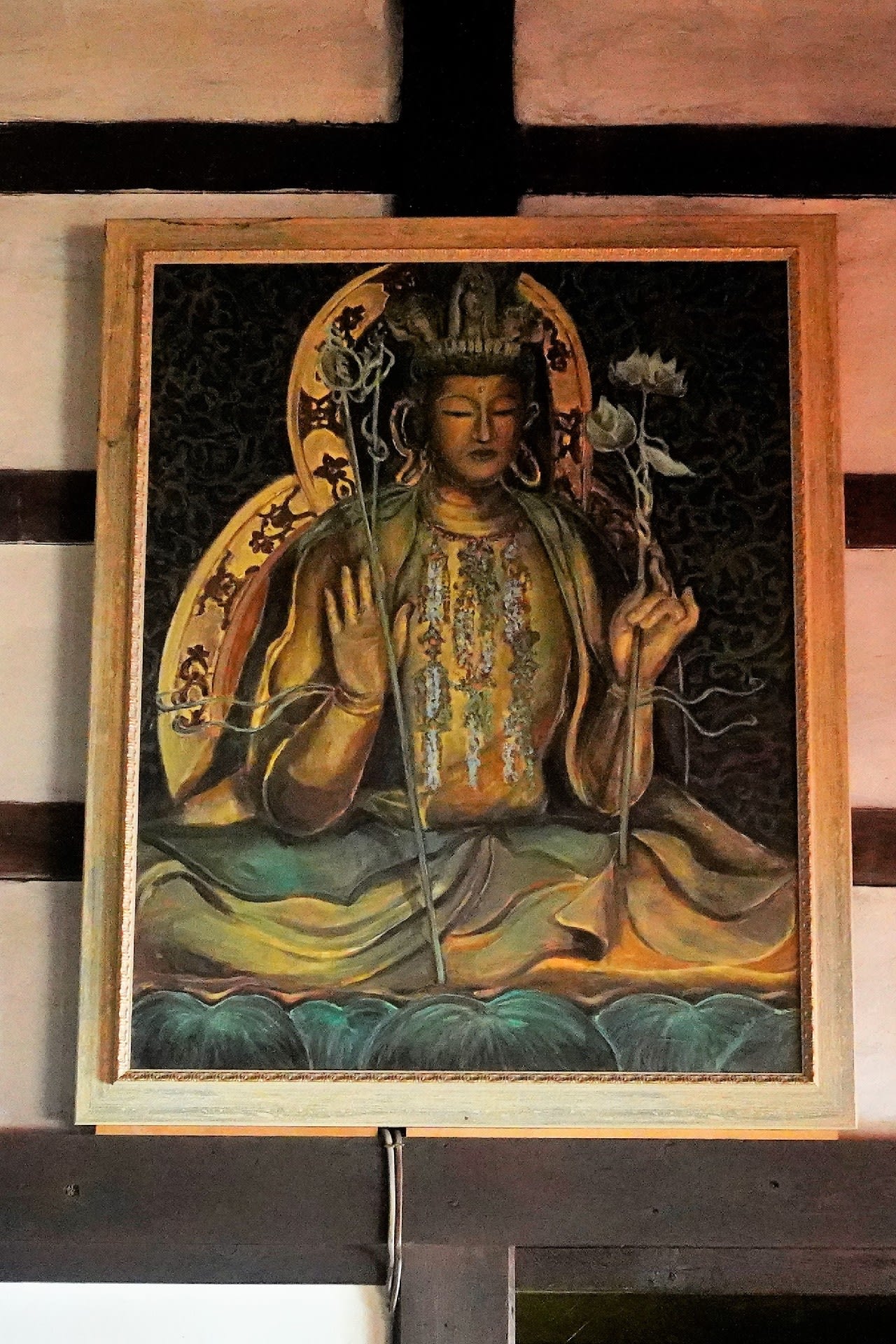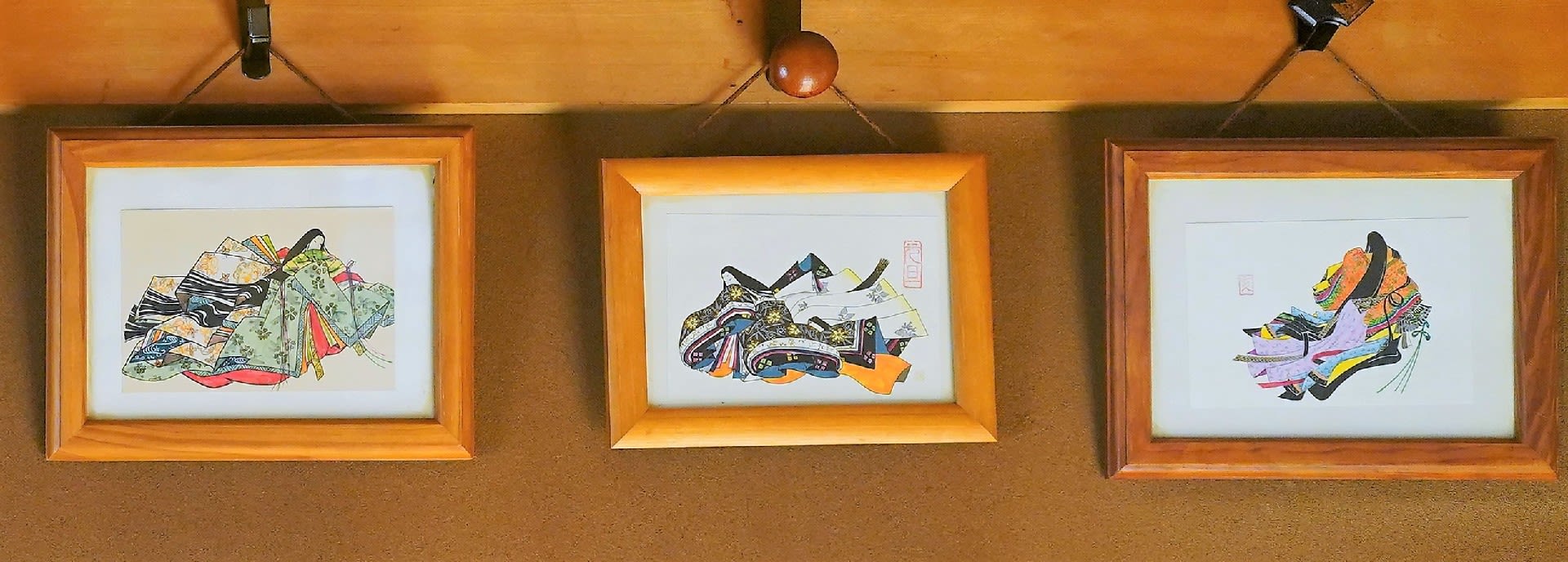👆相馬山(1411m)
榛名白川の水源に相当。「黒髪山」の異名をとる、
雷様が宿る神域でもあります。
私が見ている看板は、
暴れ川の異名をとった榛名山系から流れる、
車川の中流辺り、
暴れ川の異名をとった榛名山系から流れる、
車川の中流辺り、



この善地村👇に昔、彫り物師が居た。

車川は、下流は箕輪城の下あたり、
10月に『狐の嫁入り祭り』会場になる、
ふれあい公園の脇を流れる、榛名白川に合流する。
10月に『狐の嫁入り祭り』会場になる、
ふれあい公園の脇を流れる、榛名白川に合流する。
その白川も、昔は暴れてたよう・・。
1497年に箕輪城主が、
『狐の嫁入り祭り』会場の下方に創建した、長純寺、
のに、翌年には、白川の洪水で流され、後年、
『狐の嫁入り祭り』会場の下方に創建した、長純寺、
のに、翌年には、白川の洪水で流され、後年、
洪水を避けて、現在の地に再建したのは1557年。
白川の河岸段丘に建っている、箕輪城。
上杉謙信や、武田信玄・織田、北条との戦にも、
ひるむことなく、敵陣を唸らせた、
城主・長野信業、業政、代々の供養塔が、
長純寺にある。
ひるむことなく、敵陣を唸らせた、
城主・長野信業、業政、代々の供養塔が、
長純寺にある。
👇約束の午後1時30分、
2時間前には、車を乗り入れてしまった。
2時間前には、車を乗り入れてしまった。

👇 雨の日の奪衣婆・閻魔さん





そのお寺さんに、
1736年に彫った彫師の名の、棟札が見つかった。
建築学会に40年ほど前、論文を報告し、
1736年に彫った彫師の名の、棟札が見つかった。
建築学会に40年ほど前、論文を報告し、
調査団が入り、棟札を発見した、揺るぎない証拠。
上州彫り物師が一番最初に、記録に残した棟札。
住職の許可を得て訪ね、2週間前に撮った写真で、
頭はあっちにいったり、こっちにいったり。
頭はあっちにいったり、こっちにいったり。
後で気づく阿呆さ加減は、これからもで・・・。

鎮守様👇


彫師が彫ったのは👆の境内にある鎮守様の中の彫刻か
本堂外陣の👇欄間か・・
住職も苦渋の顔つき・・・。

早く白黒つけないと
彼らの棟札の行き場所が無くなる
👇
木崎小八・善地
小林又七守常・見崎
清水熊次郎・室田
赤見吉三郎・室田
久保政右衛門・室田
松本善助・室田
彫刻の画像は次回に
👇榛名山と向こう、とんがり帽子の相馬山
長純寺さん以外のファイルは
2017年です