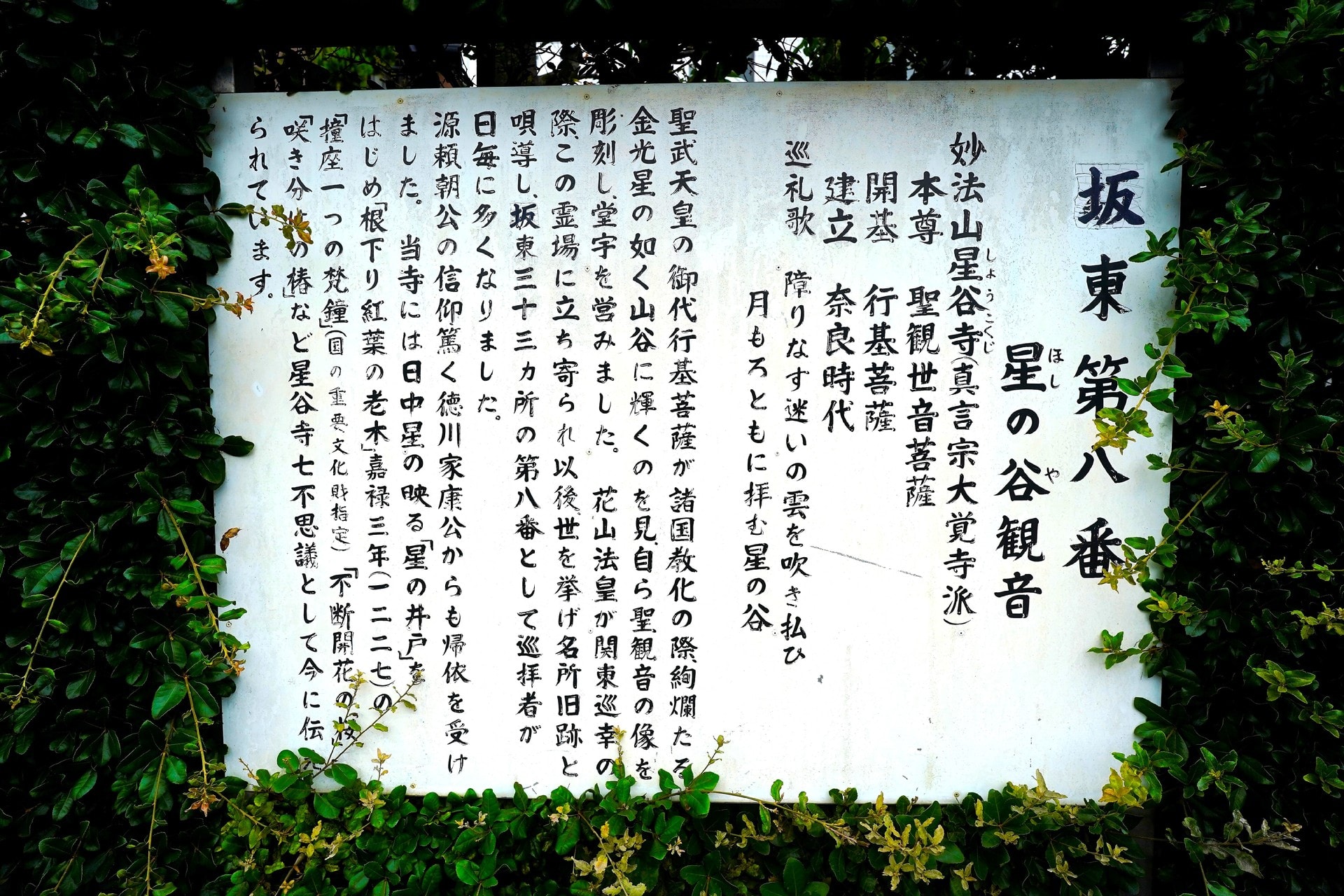しのぶれど・・・淡い思いの熱い心が顔に出るなら、
冷やかされても、腹も立たないけど、
昭和の日、人恋しさに調布の深大寺で見た薔薇👆・・・
風に揺れてた、藤青色の名は ♫ しのぶれど ♫
冷やかされても、腹も立たないけど、
昭和の日、人恋しさに調布の深大寺で見た薔薇👆・・・
風に揺れてた、藤青色の名は ♫ しのぶれど ♫
しのぶれど色あせて、世を忍び耐え・・・
源頼朝の異母弟、武将にして英知に長けた、源範頼、
頼朝の信頼関係も、忠誠心を疑われ伊豆に流され、
修善寺で討伐される・・・
のに、確かな記録は無く、範頼はひっそり、
ここ比企郡吉見町で、生きてた伝説・・
源頼朝の異母弟、武将にして英知に長けた、源範頼、
頼朝の信頼関係も、忠誠心を疑われ伊豆に流され、
修善寺で討伐される・・・
のに、確かな記録は無く、範頼はひっそり、
ここ比企郡吉見町で、生きてた伝説・・
平安末期の幼少期、範頼はここに身を隠していたという。
坂東札所十一番。岩殿山・安楽寺。
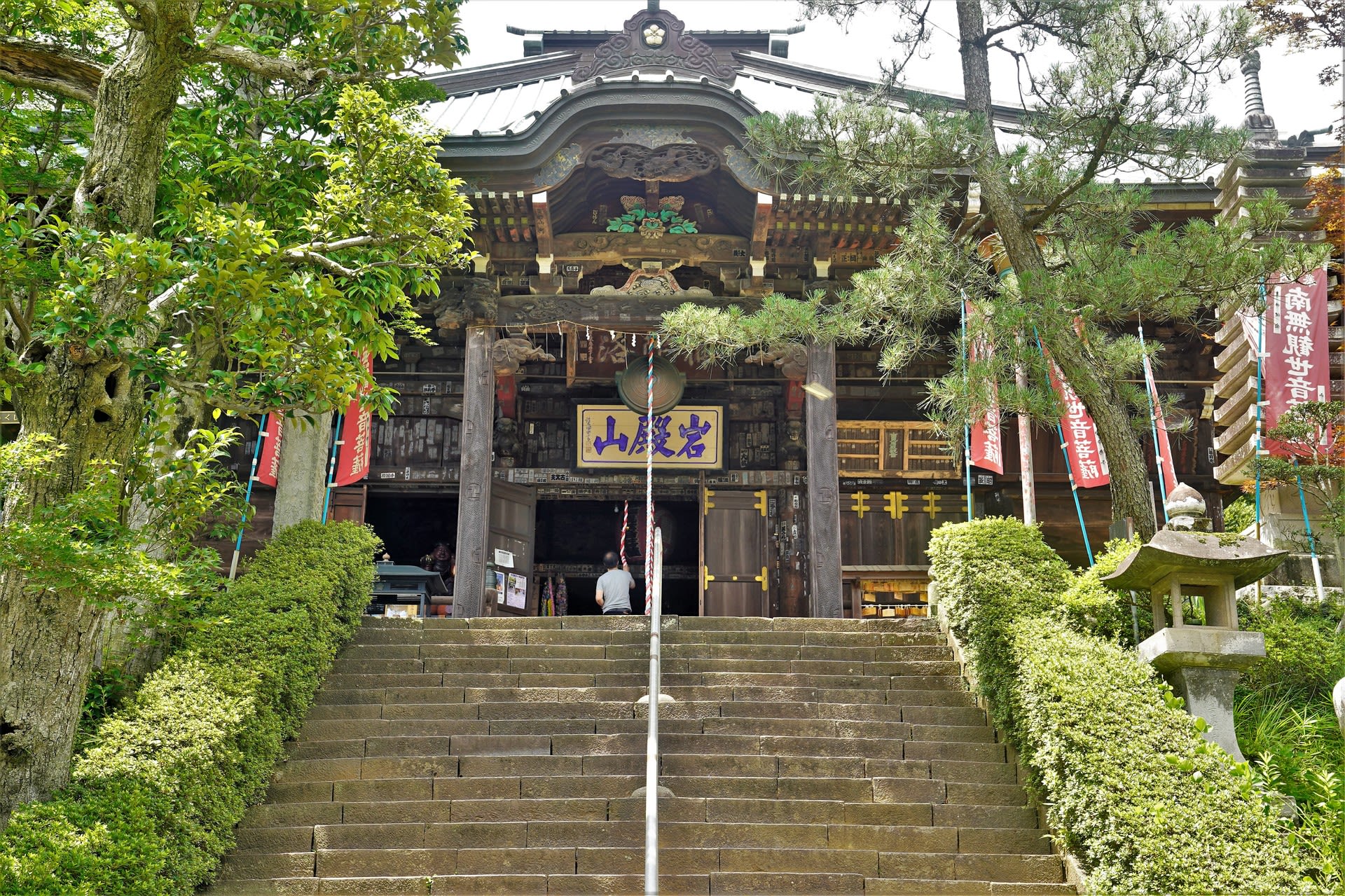


👇虎の彫刻は、左甚五郎の作と伝えられていますが・・

おばあさんに歩調に合わせる、
背筋が通った青年👇疲れが飛んだ、いいひと時だった。





👇範頼が寄進した三重の塔は、焼失し・・




吉見観音周辺は今
吉見町大字御所という地名
吉見御所と尊称された
吉見御所と尊称された
範頼にちなむと伝えられ
範頼の妻の祖母で
頼朝の乳母でもある比企尼の嘆願により
子の範圓・源昭は助命され
その子孫が吉見氏として続いたとされる