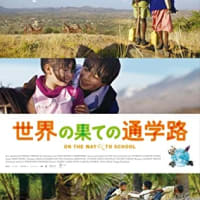昨日3才の男の子が、殴られて死んだ。
その前に熱湯をかけられて死んだのも3才の女の子だった。
幼い命を殺した者への憎悪と殺意の感情が私にもある。
だけど、憎悪と殺意の相手はその犯人個人だけじゃない。
大人同士の殺人事件とは違う。
相手は、1才とか3才だ。
幼い子どもを殴り殺せるまでの「感情」は、幼いころに暴力を受けた「感情」と同じものだ。
だから来る日も来る日も、私たち大人の中の誰か、歯止めを持たない誰かが繰り返し続けるのだろう。
虐待はいまの若い世代の人間が発明したものじゃない。
この社会に生まれて、「教えられた」ものだ。
この社会が教えていることのうちだ。
親も保育士も先生も、子どもを殴る。
子どもは、大人は子どもを殴る生き物だと、学んで育つ。
「体罰」も「虐待」も、子どもが死んだり、大ケガをしたときにだけ、問題にされるだけ。
死なずに、生き延びた子どもがどれだけいるか。
二十歳の男は、生き延びた子どもじゃないのか。
聖書にも、「子どもを鞭で叩け」という教えが書いてある。
教えは、まだ取り消されてはいない。
これは間違いでした、聖書から取り消しますとは言わない。
二十歳の男は、鞭と拳を間違えただけじゃないのか。
聖書の教えと、世界中で子どもをなぐる習慣は歴史を通してつながっている。
二十歳のころの私も、子どもをたたいていいと思っていた。
グーで顔や腹はだめでも、浜ちゃんのつっこみくらいの叩き方はOKだと思っていた。
学生のころ、スイミングや塾でバイトをしながら、子どもをたたいていた。
苛立ちや憎しみをぶつけるのはだめでも、普通にたたくのは悪いことじゃないと思っていた。
自分が何をしているのか気づけたのは、アリスミラーのおかげだ。
昨日、3才の男の子を殴り殺した二十歳の男と、二十歳の私は、
同じ憎しみの「感情」を抱えていた。
違うのは、私にはその憎しみの感情も含めて、
受け止めてくれる人がいたことだと、いまは思う。
◇
殴る、縛る、火(お灸)や熱湯、押入れや物置など暗い所に閉じ込める。
どれも人間の歴史のなかで受け継がれてきた、子どもの懲らしめ方だ。
私も子どもの頃、熱湯以外はどれも受けてきた。
「消えた子ども」たちが、「監禁」された子どもであるとき、
座敷牢という文化と、私宅監置という法律のあったこと、
そしてこの国の「隠すべき子ども」への扱いはつながっている。
「消えた子ども」とは誰か。
「隠すべき子ども」とは誰か。
「隠された子ども」とは誰か。
親が隠したい子どもは誰か。
社会が隠せと命じる子どもは誰か。
子どもを監禁という形を思いつき実行する人たちを、止めるためには、この社会で受け継がれてきた、虐待の文化を根底から見つめなおすべきだ。
この国の「隠すべき子ども」への扱いの一つが、障害児への「就学猶予・免除」という法律であり、差別であり、人々の常識だった。
それは、いま生きている人の、日常だった。
私が、この本と就学猶予免除にこだわるのは、ナミさんの次の言葉が頭から離れないからだ。
◇
【取材のなかで、ナミさんと一緒にある小学校を訪れたことがあった。
ナミさんは以前にもひとりで学校を訪れていたことを明かしてくれた。
「本当はこの学校に通うはずだったんです。見学させてもらえませんか、ってお願いしてみたんです」
ナミさんが勇気を出してそう伝えたところ、学校の教員は快く承諾してくれたという。
学校の廊下を進むと、教室の中から子どもたちの声が聞こえた。
授業をする先生と学ぶ子どもたちの姿があった。
「私も、もし学校に行けてたらあんなふうに勉強したのかな」
………
ナミさんは、今回、苦しい時間を思い出す作業を伴いながらも取材に応じてくれた理由をこう語る。
「普通の生活だったり、楽しい学校だったり、たくさん学んで、ちゃんと社会に出ていける子どもたちが一人でも増えるといいなと、本当に思います。
私自身、そういう経験がしたかったから。
閉じ込められたまま十八歳まで過ごしてきて、今、社会に出て九年経ちます。
その九年間でいろいろなことを学んで、いろんなことがありながらも頑張っている人たちにも出会いました。
でも、自分は……。
マイナス思考ばっかりで、よし頑張ろうと思って動いても、どこかでつまずいてうまくいかなくなることがすごく多いんです。
そういう意味では、もうちょっと早く逃げてくれば、助け出してくれれば、今の状況も変わっていたんじゃないかなって。
本当に『悔しい』という一言なんです。
十八年間っていうのは決して取り戻せないし、簡単に取り戻せとか言われてもできないので。
もう同じような思いをする子どもが生まれてほしくないんです】
『ルポ 消えた子どもたち 虐待・監禁の深層に迫る』
(NHKスペシャル「消えた子どもたち」取材班) NHK出版新書より
◇
ナミさんのいう「同じような思い」とは、どんな思いか。
「決して取り戻せない」、「子ども時代」を奪われた、「悔しい」思い。
その「思い」がどんな思いか。
真剣に考えなければ、自分の体験を話してくれた彼女に申し訳ない。
(つづく)
最新の画像もっと見る
最近の「この子がさびしくないように」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(517)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(401)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(162)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(92)
- ホームN通信(103)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(68)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(86)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(99)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事