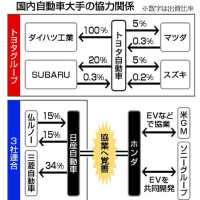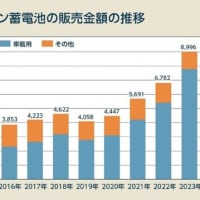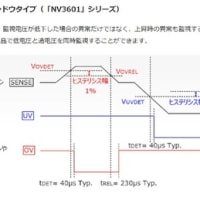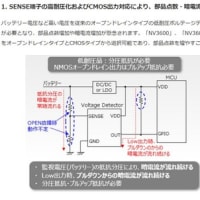空冷エンジンのエンジン温コントロールのこと
今でも小排気量小型エンジンには空冷エンジンは残存するが、少なくとも4輪車で空冷エンジンは途絶えた。市販車用空冷エンジンを最後まで使用していたのはポルシェ911シリーズだったが、それも最終型993型でお終いとなった。しかし、先の大戦の頃の軍事用兵器としてのエンジンは、航空機にしても戦車にしても空冷の方が多かった様だ。
このエンジンの空水冷論と云うのは、ホンダの歴史の中で語られることが多い。すなわち、「水冷であろうが(熱交換器:ラジエーターを介して)最終的には空冷なされるのだから空冷がベスト」とするガンコ親父の宗一郎氏の思いと、それは違う「絶えず変化するエンジンの発熱を水という媒介を通して恒温化するのがベスト」という中村(良夫)らエンジン開発者の意見の対立した話がよく語られる。
この話し、最終的には創業者である宗一郎氏が「オレの時代は去った」と自覚し、自らの引退を決めることになったのだろうと理解している。そこでホンダエンジンの空冷はすべて水冷に移行したのだが、それから10年程後までポルシェは空冷に固執しつつ、最終的には996型から水冷エンジンに移行した。
そのポルシェだが、空冷型の市販車と作り続けていたが、レーシングエンジンでも空冷であったが、その末期にはヘッドのみ水冷で、シリンダー部は空冷という半水冷というエンジンの時代もあった。これは市販車でも959など、極少量生産車においても使用された。
最終的に水冷エンジンに収束した理由は、排ガス規制と無縁ではなかろう。排ガス対策としては、空燃比など、燃焼を極狭い
範囲(理論空燃比)に収束させるのが主な解決手法だったのだが、それもエンジン温度の恒温化というファクターが欠かせない要件となる。幾ら空燃比だけを収束させても、エンジン温度が負荷条件などで上下に変化してしまうと、燃焼条件が変わってしまい、排気ガスの状態がバラついてしまい、触媒の高効率浄が低下してしまうと云うことだろう。
それと、トヨタS800などは空冷エンジンだったが、冬期のヒーターとして燃焼式という現在の石油ファアヒーターと同様の原理で、燃料(ガソリン)を別途燃焼させる方式だったのだが、それを付けないとヒーター暖房が困難もしくは不十分という欠点が空冷にはあった。
最後に表題のエンジン温度のコントロールだが、水冷式の場合は高負荷時の放熱を前提に設計したラジエータ放熱に対し、サーモスタットという温度コントロールデバイスを冷却水路に設置することで、定温(昔80→現在90℃辺り)に高温制御している。空冷の場合、どうしているのかと云うと、実のところ制御装置がないのが一般的だった。しかし、訓示兵器としては、厳寒の寒冷地だけでなく酷暑の熱帯地域でも冷却水なしでメンテフリーというところを重視していたのだろう。戦車などは、旧日本軍のディーゼルでも、ドイツや米国のガソリン大排気量エンジンでも空冷だった様だ。
ただし、航空機用の空冷星形エンジンでは、カウルフラップというのが付いていた様だ。これは添付写真の様にエンジンナセル(カバー)の後部が、開閉できる様になっており、シリンダー温度(昔の説明を読むと筒温計)をパイロットが見ていて、適正温度から上がり過ぎた場合、カウルフラップを開くことで、エンジン通過の空気量を増やすことでシリンダー温度を低下させていた様だ。航空機の場合、地上から高度が上がるに従って、気圧が下がるだけでなく温度が低下するという外部環境パラメーターの変化が大きく、こういう装置が取り入られていたのだろう。


空冷エンジンでシリンダー温度が上がり過ぎると、これはつまりオーバーヒートの状態だが、シリンダーの焼き付きだとか、デトネーション(異常燃焼やノッキング)により出力低下からピストンなどが溶損まで至るリスクがあり、この様な装置があったと思える。
それと、若干補足しておくと、特にガソリンエンジンの場合点火時期というのがエンジン回転や負荷条件に応じてベストにしないと出力に与える影響が大きいが、昔のレシプロエンジンでは手動で点火時期を調整するマニュアルアドバンスコントロールだった様だ。先のカウルフラップ調整と共に今では信じがたい程、めんどくさい調整をしながら飛行する要があった様だ。
今でも小排気量小型エンジンには空冷エンジンは残存するが、少なくとも4輪車で空冷エンジンは途絶えた。市販車用空冷エンジンを最後まで使用していたのはポルシェ911シリーズだったが、それも最終型993型でお終いとなった。しかし、先の大戦の頃の軍事用兵器としてのエンジンは、航空機にしても戦車にしても空冷の方が多かった様だ。
このエンジンの空水冷論と云うのは、ホンダの歴史の中で語られることが多い。すなわち、「水冷であろうが(熱交換器:ラジエーターを介して)最終的には空冷なされるのだから空冷がベスト」とするガンコ親父の宗一郎氏の思いと、それは違う「絶えず変化するエンジンの発熱を水という媒介を通して恒温化するのがベスト」という中村(良夫)らエンジン開発者の意見の対立した話がよく語られる。
この話し、最終的には創業者である宗一郎氏が「オレの時代は去った」と自覚し、自らの引退を決めることになったのだろうと理解している。そこでホンダエンジンの空冷はすべて水冷に移行したのだが、それから10年程後までポルシェは空冷に固執しつつ、最終的には996型から水冷エンジンに移行した。
そのポルシェだが、空冷型の市販車と作り続けていたが、レーシングエンジンでも空冷であったが、その末期にはヘッドのみ水冷で、シリンダー部は空冷という半水冷というエンジンの時代もあった。これは市販車でも959など、極少量生産車においても使用された。
最終的に水冷エンジンに収束した理由は、排ガス規制と無縁ではなかろう。排ガス対策としては、空燃比など、燃焼を極狭い
範囲(理論空燃比)に収束させるのが主な解決手法だったのだが、それもエンジン温度の恒温化というファクターが欠かせない要件となる。幾ら空燃比だけを収束させても、エンジン温度が負荷条件などで上下に変化してしまうと、燃焼条件が変わってしまい、排気ガスの状態がバラついてしまい、触媒の高効率浄が低下してしまうと云うことだろう。
それと、トヨタS800などは空冷エンジンだったが、冬期のヒーターとして燃焼式という現在の石油ファアヒーターと同様の原理で、燃料(ガソリン)を別途燃焼させる方式だったのだが、それを付けないとヒーター暖房が困難もしくは不十分という欠点が空冷にはあった。
最後に表題のエンジン温度のコントロールだが、水冷式の場合は高負荷時の放熱を前提に設計したラジエータ放熱に対し、サーモスタットという温度コントロールデバイスを冷却水路に設置することで、定温(昔80→現在90℃辺り)に高温制御している。空冷の場合、どうしているのかと云うと、実のところ制御装置がないのが一般的だった。しかし、訓示兵器としては、厳寒の寒冷地だけでなく酷暑の熱帯地域でも冷却水なしでメンテフリーというところを重視していたのだろう。戦車などは、旧日本軍のディーゼルでも、ドイツや米国のガソリン大排気量エンジンでも空冷だった様だ。
ただし、航空機用の空冷星形エンジンでは、カウルフラップというのが付いていた様だ。これは添付写真の様にエンジンナセル(カバー)の後部が、開閉できる様になっており、シリンダー温度(昔の説明を読むと筒温計)をパイロットが見ていて、適正温度から上がり過ぎた場合、カウルフラップを開くことで、エンジン通過の空気量を増やすことでシリンダー温度を低下させていた様だ。航空機の場合、地上から高度が上がるに従って、気圧が下がるだけでなく温度が低下するという外部環境パラメーターの変化が大きく、こういう装置が取り入られていたのだろう。


空冷エンジンでシリンダー温度が上がり過ぎると、これはつまりオーバーヒートの状態だが、シリンダーの焼き付きだとか、デトネーション(異常燃焼やノッキング)により出力低下からピストンなどが溶損まで至るリスクがあり、この様な装置があったと思える。
それと、若干補足しておくと、特にガソリンエンジンの場合点火時期というのがエンジン回転や負荷条件に応じてベストにしないと出力に与える影響が大きいが、昔のレシプロエンジンでは手動で点火時期を調整するマニュアルアドバンスコントロールだった様だ。先のカウルフラップ調整と共に今では信じがたい程、めんどくさい調整をしながら飛行する要があった様だ。