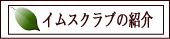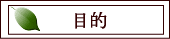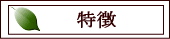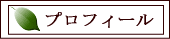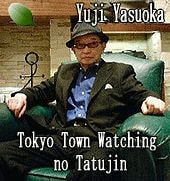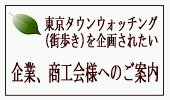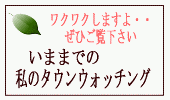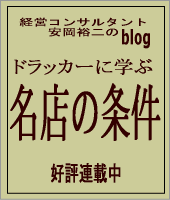「本仕込み赤味噌使用」…味噌いかのキャッチコピー
普段利用している横須賀線にはグリーン車が付いている。良く利用する東京駅から夕方缶ビールとつまみを買い込んでいっぱいやりながら帰るのが何とも言えない。沿線お仲間の毎日コムネット伊藤さん(JQ上場)によると、「至福のひととき」とか。
さて、酒のお伴になるあんちょこ的つまみの中に、「味噌いか」という一寸変わった品を見つけた。キャッチコピーに(本仕込み赤味噌使用)とある。
印象は、味噌で味付けしたいかの粗切りというイメージに、なにやら(本仕込み→年季の入った確からしさ)と(赤味噌→関東では一寸名古屋~関西の異国風)という言葉の持つイメージが重なってくる。
コピー感覚でいえば、惹きつけられるのは、「本仕込み」+「赤味噌」のキーワード。本仕込みの他に本醸造という言葉にも弱い。「本」は、源 、本物、伝統などをイメージさせる力があり、欠かせない複合語になっている。
脱線するが、最近受けているのが、(ふわふわ)(やわらか)というキーワード。なにやら女性の時代と重なっているようだ。
普段利用している横須賀線にはグリーン車が付いている。良く利用する東京駅から夕方缶ビールとつまみを買い込んでいっぱいやりながら帰るのが何とも言えない。沿線お仲間の毎日コムネット伊藤さん(JQ上場)によると、「至福のひととき」とか。
さて、酒のお伴になるあんちょこ的つまみの中に、「味噌いか」という一寸変わった品を見つけた。キャッチコピーに(本仕込み赤味噌使用)とある。
印象は、味噌で味付けしたいかの粗切りというイメージに、なにやら(本仕込み→年季の入った確からしさ)と(赤味噌→関東では一寸名古屋~関西の異国風)という言葉の持つイメージが重なってくる。
コピー感覚でいえば、惹きつけられるのは、「本仕込み」+「赤味噌」のキーワード。本仕込みの他に本醸造という言葉にも弱い。「本」は、源 、本物、伝統などをイメージさせる力があり、欠かせない複合語になっている。
脱線するが、最近受けているのが、(ふわふわ)(やわらか)というキーワード。なにやら女性の時代と重なっているようだ。