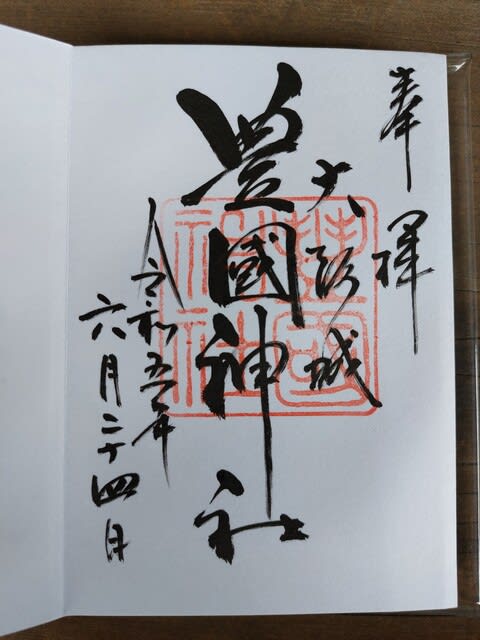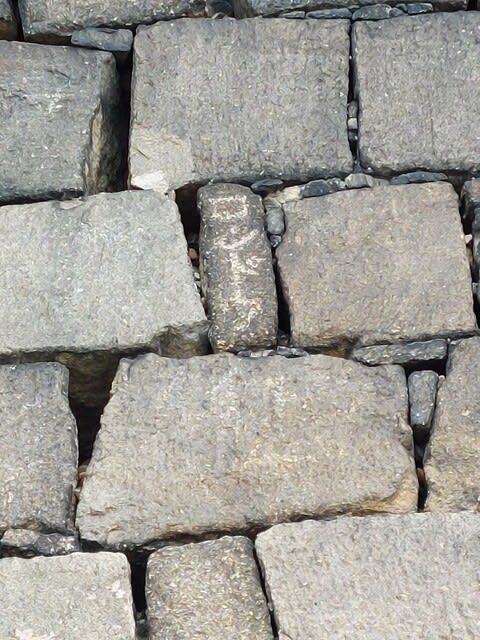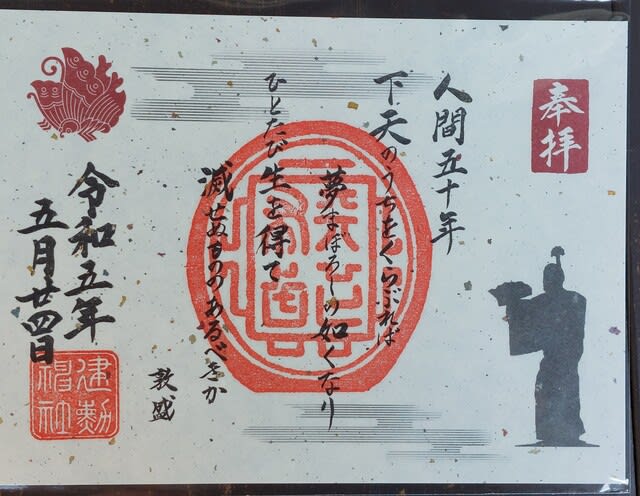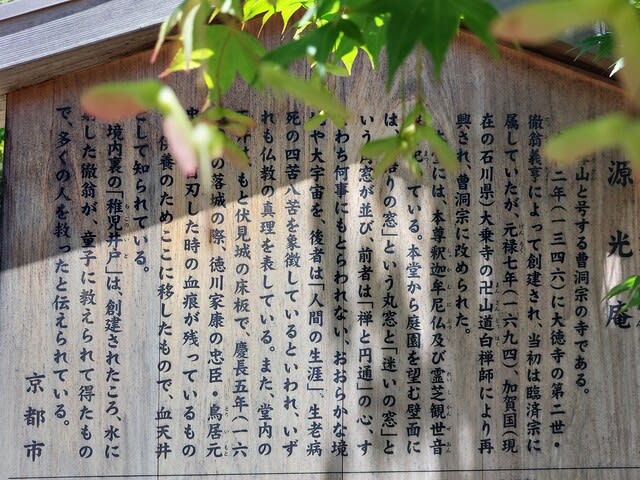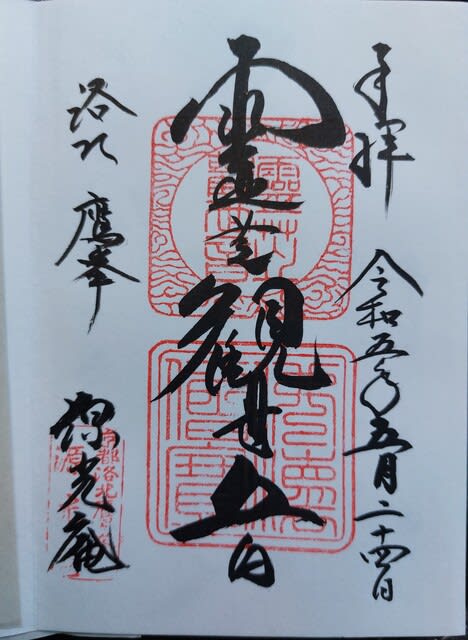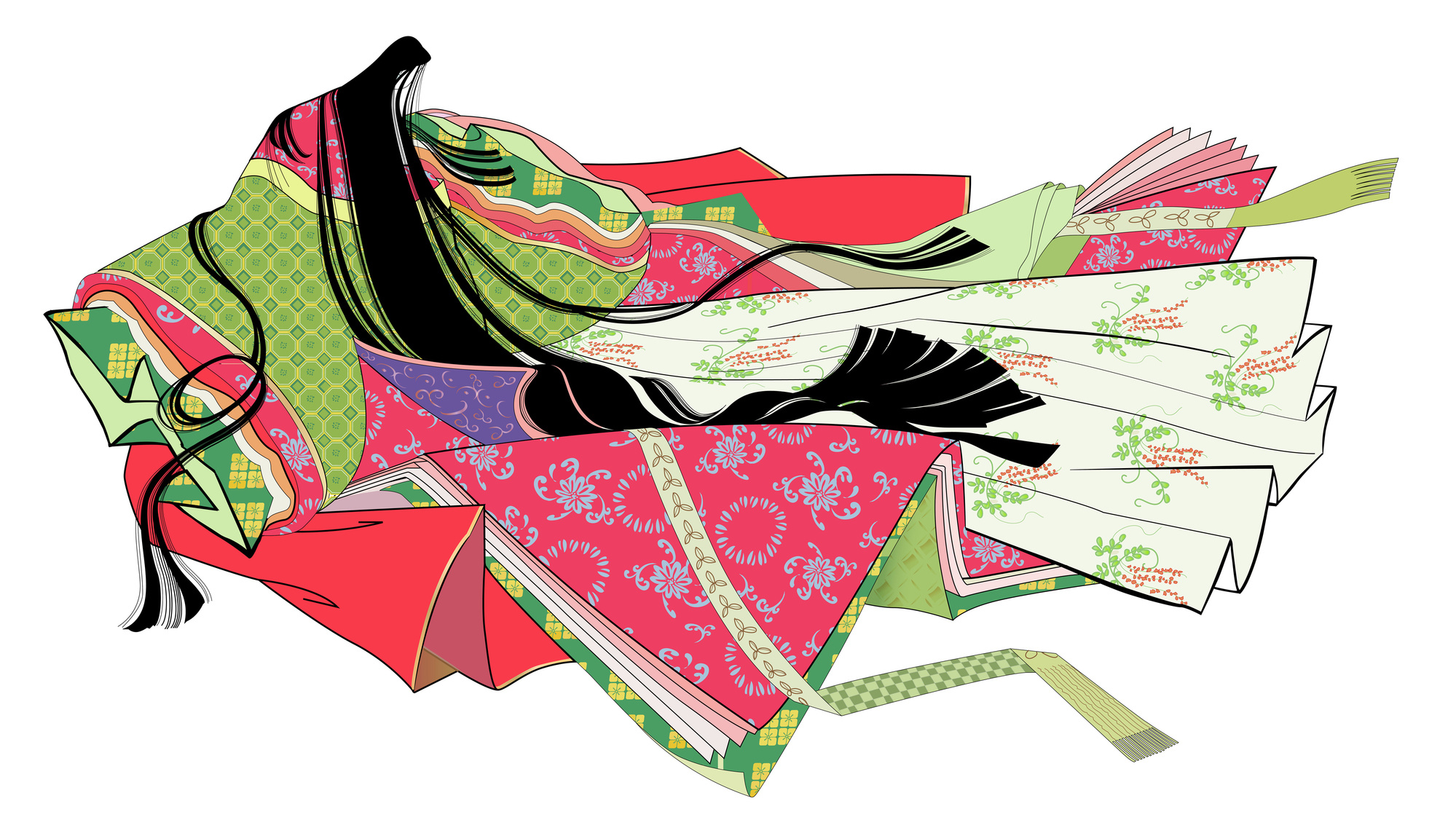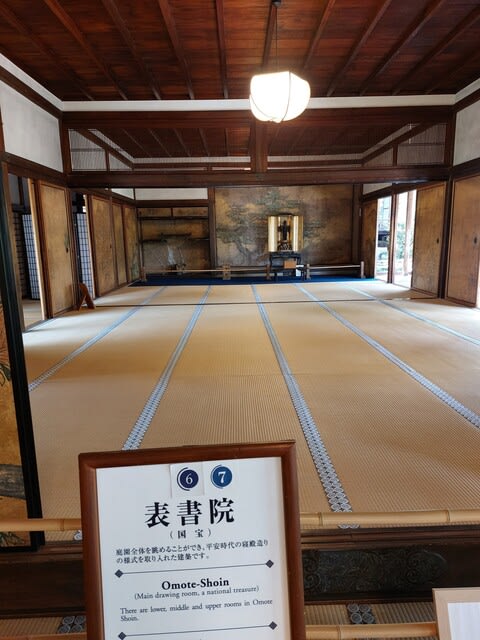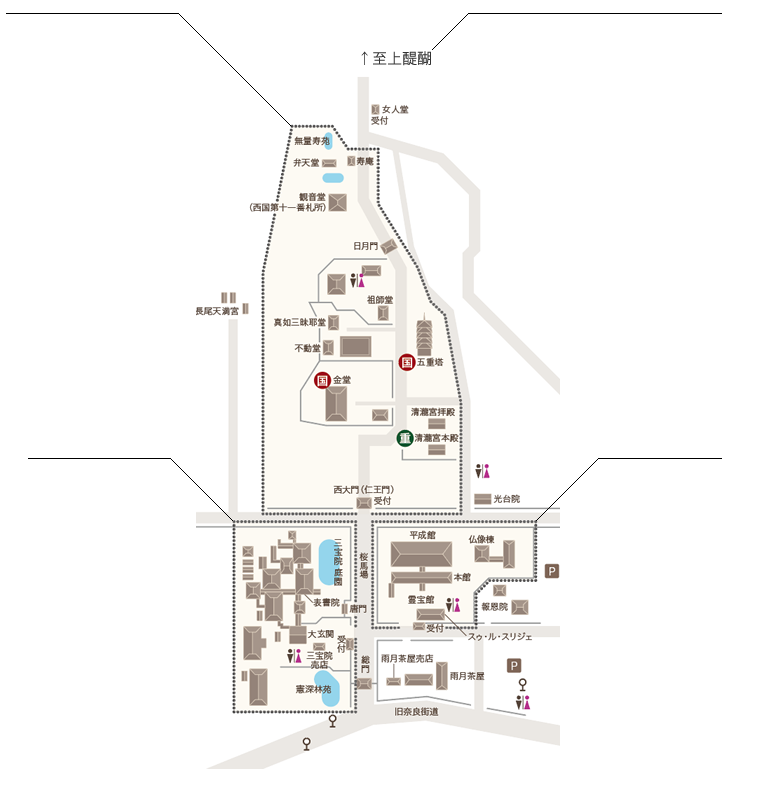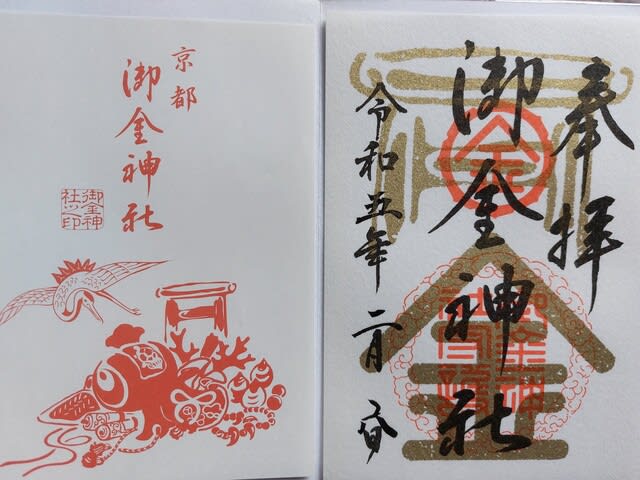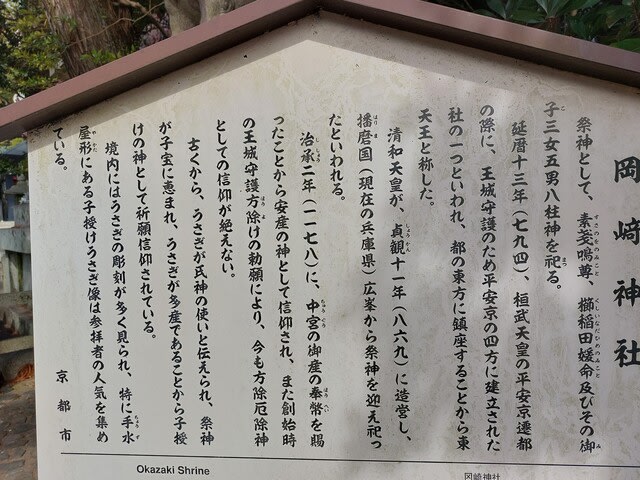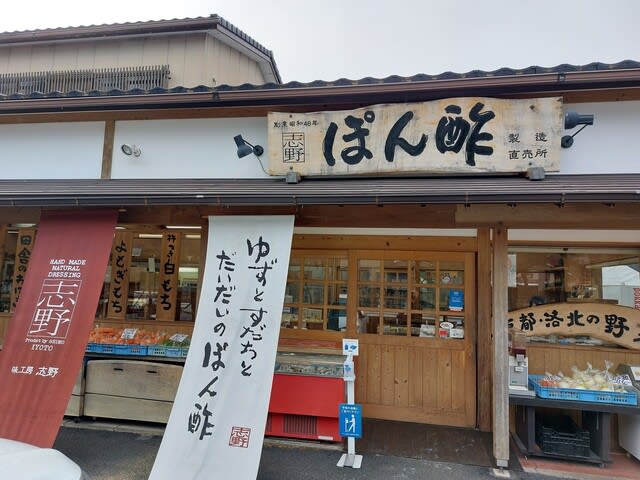1/10 10日ゑびすに京都ゑびす神社にお参りしてきました。

こちらは、商売繁盛と大漁祈願。
そして、他にもお参りです。
まずは、八坂神社。


時刻は、9時半ころなので、参拝者も少なかったです。

国宝のご本殿。
神妙に手を合わせます。

そして、御朱印を頂戴しました。

そして、次は、お寺です。
知恩院さんです。

こちらの三門、圧倒されます。


ちなみに一緒に行っていたH君。
まったく神社仏閣に関心なし。
歩くのが辛いなどと言い、参拝に行こうとしない。
そのため、八坂さんとえべっさんをお詣りして、次は釣具店。
そんなことを思っていたのですが、
珍しく知恩院さんに行こう、と言い出したのです。
理由は、瓦が見たい。
なるほど、瓦屋さんなので、関心があるらしい。
以前も御所などの仕事をしたこともあるとのこと。

この立派な三門。
屋根が二段になっています。

下の屋根の瓦です。
普通の瓦が一部敷かれています。

これは、屋根に樋がないため、上の屋根から雨が流れ落ち、
ましてや高いところからなので、落ちた下の屋根が傷んでしまう。
それを防ぐためにもう一枚瓦が上に敷かれているとのこと。

なるほど。
そんなところには、目が行っていなかった。
さすが瓦屋です。
それを聞いてから、他の建物を見てみると、なるほどそうなっていました。
それでは、御影堂にお参りします。

お寺さんのお参りは、心静かになります。

さて、こちらの大きな御影堂の屋根。

屋根は一段ですし、樋がついてます。
なんか屋根を見てしまうようになりました。
こちらは、阿弥陀堂。

知恩院さんは大きなお寺さんですので、いろいろと建物があります。

その中でも有名なのが鐘楼。

こちらの大きな鐘は、除夜の鐘で有名です。

デカいです。
確かに撞くのが大変ですね。

ちなみにこちらの自販機、南無阿弥陀仏の念仏が流れます。

御朱印です。

ということで、この東山周辺は、清水さんや高台寺さんなど有名どころがいっぱい。
しかし、瓦屋H君は関心がないため、とっと釣具店へと向かいました。
そして、買う予定もなかったものを・・・。
やっぱりお金が残りませんわ。