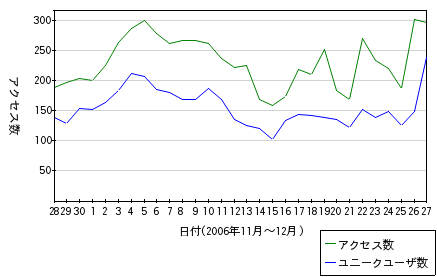■航空自衛隊車輌集
やあみんな!メリークリスマス!、今日はみんなが楽しみにしていた航空自衛隊の地上車輌集だぞ!、・・・、今回も小ネタ集です。
 航空自衛隊には、一般車輌/救難車輌/補給車輌/施設車輌など、総計6000の車輌が配備されている。航空機の整備を一つとっても、燃料補給車や牽引車、電源車が必要であり、弾薬輸送車、事故に備えての消防車や救急車、滑走路機能維持の為の各種車輌がその稼働率を支えており、華やかな航空機の飛行も、こうした車輌群を駆る整備員や管制要員の努力が無くては大空へ羽ばたくことはできない。今回はこの特集を行う。
航空自衛隊には、一般車輌/救難車輌/補給車輌/施設車輌など、総計6000の車輌が配備されている。航空機の整備を一つとっても、燃料補給車や牽引車、電源車が必要であり、弾薬輸送車、事故に備えての消防車や救急車、滑走路機能維持の為の各種車輌がその稼働率を支えており、華やかな航空機の飛行も、こうした車輌群を駆る整備員や管制要員の努力が無くては大空へ羽ばたくことはできない。今回はこの特集を行う。
 1/2㌧トラックV16BBRSTA、三菱自動車製で440kgを搭載、若しくは最大6名を輸送する。速度は135km/hである。もっともオーソドックスな車輌といえ、基地内の連絡輸送から山間部のレーダーサイトの物資・人員輸送にも対応する。基地やレーダーサイト警備に12.7㍉重機関銃や5.56㍉の搭載も可能であるが、航空自衛隊ではそうした運用は行っているのだろうか不明である。後方は高射隊が運用するタンク車。
1/2㌧トラックV16BBRSTA、三菱自動車製で440kgを搭載、若しくは最大6名を輸送する。速度は135km/hである。もっともオーソドックスな車輌といえ、基地内の連絡輸送から山間部のレーダーサイトの物資・人員輸送にも対応する。基地やレーダーサイト警備に12.7㍉重機関銃や5.56㍉の搭載も可能であるが、航空自衛隊ではそうした運用は行っているのだろうか不明である。後方は高射隊が運用するタンク車。
 1 1/2㌧トラックWB503.トヨタ自動車製で車輌重量3360kg、最大積載量は2000kgである。写真は基地防空隊のVADSを牽引している。各基地防空隊に16基が運用されており、基地防空の最後の砦として任務にあたっている。車輌には弾薬の他、操作要員を載せており、迅速な機動が可能である。陸上自衛隊では改良型に高機動車の車体を用いたものがあるが、航空自衛隊への導入はまだ開始されていないようだ。
1 1/2㌧トラックWB503.トヨタ自動車製で車輌重量3360kg、最大積載量は2000kgである。写真は基地防空隊のVADSを牽引している。各基地防空隊に16基が運用されており、基地防空の最後の砦として任務にあたっている。車輌には弾薬の他、操作要員を載せており、迅速な機動が可能である。陸上自衛隊では改良型に高機動車の車体を用いたものがあるが、航空自衛隊への導入はまだ開始されていないようだ。
 高射隊や基地業務隊において使用されているニッサンサファリ、この他トヨタランドクルーザやパジェロ(陸自の73式小型トラックとは異なり、市販車と同型のもの)なども使用されることがあるようだ。各国の軍隊でも使用されているようだが、自動車に詳しい方がいたらご教授願いたい。長い車列に際しては先導をする車輌が必要であり、こうした車輌が装備されている。基本的には市販車の色違いといって差し支えない。
高射隊や基地業務隊において使用されているニッサンサファリ、この他トヨタランドクルーザやパジェロ(陸自の73式小型トラックとは異なり、市販車と同型のもの)なども使用されることがあるようだ。各国の軍隊でも使用されているようだが、自動車に詳しい方がいたらご教授願いたい。長い車列に際しては先導をする車輌が必要であり、こうした車輌が装備されている。基本的には市販車の色違いといって差し支えない。
 制式化されているわけではないので、暫時新型に更新しているようだ。車輌は旧式のもの。こちらはメーカーも異なり、トヨタランドクルーザー。登攀性能や不整地突破能力、稼働率や巡航性能など、どれをとってもランドローバーやメルセデスクロスカントリーといった軍用車輌と遜色なく、ジェーン年鑑などでは軍用車として紹介されている。消防の山岳救助隊がこうした車輌を運用しているが、富士山の急斜面もすいすい登る。
制式化されているわけではないので、暫時新型に更新しているようだ。車輌は旧式のもの。こちらはメーカーも異なり、トヨタランドクルーザー。登攀性能や不整地突破能力、稼働率や巡航性能など、どれをとってもランドローバーやメルセデスクロスカントリーといった軍用車輌と遜色なく、ジェーン年鑑などでは軍用車として紹介されている。消防の山岳救助隊がこうした車輌を運用しているが、富士山の急斜面もすいすい登る。
 場外救難車1形KC-BXD20V,トヨタ自動車のメガクルーザ航空自衛隊仕様で、基地外の救難活動に使用される。このファミリー車輌に陸上自衛隊の高機動車があり、不整地突破能力は折り紙付である。人員輸送を目的としたものではない為、シートに収容することで人員は少なく、あくまでオフロード仕様の救急車である。なお、メガクルーザは市販もされているが、加速性能ではハンヴィーとは比較にならない性能を弾き出す、国産車最強の市販四輪駆動車である。
場外救難車1形KC-BXD20V,トヨタ自動車のメガクルーザ航空自衛隊仕様で、基地外の救難活動に使用される。このファミリー車輌に陸上自衛隊の高機動車があり、不整地突破能力は折り紙付である。人員輸送を目的としたものではない為、シートに収容することで人員は少なく、あくまでオフロード仕様の救急車である。なお、メガクルーザは市販もされているが、加速性能ではハンヴィーとは比較にならない性能を弾き出す、国産車最強の市販四輪駆動車である。
 大型破壊機救難消防車A-MB-3 FB630TN、大型の航空機火災用消防車で、乗員は五名、車内からの操作も可能であり、加えて11.15㌧の搭載量を有する。1989年より配備が開始された。大型車輌であるが、その筈、製造は鉄道車両の製造を行う東急車輛製である。100km/hの俊足で現場に向かう。重量31.5㌧、全長11.9㍍、C-130Hの機首が写っているが、これと比較するとその大きさが判る。公道で出会うことはまずないが、空港では同型車輌を良く見かける。
大型破壊機救難消防車A-MB-3 FB630TN、大型の航空機火災用消防車で、乗員は五名、車内からの操作も可能であり、加えて11.15㌧の搭載量を有する。1989年より配備が開始された。大型車輌であるが、その筈、製造は鉄道車両の製造を行う東急車輛製である。100km/hの俊足で現場に向かう。重量31.5㌧、全長11.9㍍、C-130Hの機首が写っているが、これと比較するとその大きさが判る。公道で出会うことはまずないが、空港では同型車輌を良く見かける。
 左から救難車E-FZJ80G-GCPNK,事故機裁断や乗員救出器材を搭載する。消防車KC-FT1JGBA,基本的に普通の消防車。破壊機救難消防車A-MB-1(FZ610LN),航空機火災や油火災に対応するもので、前述のA-MB-3以前に調達されていたもの。となりはA-MB-3、右端は破壊機救難車へ給水を行う1000G給水車FTS33F2,1000ガロンの消防用水を搭載する。また、非常時には給水運搬にも用いる。
左から救難車E-FZJ80G-GCPNK,事故機裁断や乗員救出器材を搭載する。消防車KC-FT1JGBA,基本的に普通の消防車。破壊機救難消防車A-MB-1(FZ610LN),航空機火災や油火災に対応するもので、前述のA-MB-3以前に調達されていたもの。となりはA-MB-3、右端は破壊機救難車へ給水を行う1000G給水車FTS33F2,1000ガロンの消防用水を搭載する。また、非常時には給水運搬にも用いる。
 20K?燃料補給車FY2FTAT,20K?ガロンの航空機用燃料JP4を搭載するもので、この種の車両としては航空自衛隊最大のものである。運用方式は航空基地の燃料タンクから補充を受ける。これまでは大型給油車はトレーラー式であったが、本型から一体単車式として安定を高めている。東急車輛製で毎分2270?の燃料補給が可能である。写真はT-4練習機に対して燃料補給をしているところで、航空機よりも大きいところが判る。
20K?燃料補給車FY2FTAT,20K?ガロンの航空機用燃料JP4を搭載するもので、この種の車両としては航空自衛隊最大のものである。運用方式は航空基地の燃料タンクから補充を受ける。これまでは大型給油車はトレーラー式であったが、本型から一体単車式として安定を高めている。東急車輛製で毎分2270?の燃料補給が可能である。写真はT-4練習機に対して燃料補給をしているところで、航空機よりも大きいところが判る。
 燃料補給を終えT-4列機の前を連なって走るFY2FTAT,この他、500ガロン燃料補給車や2000?燃料補給車、2000ガロン燃料補給車などがあり、ヘリや練習機、戦闘機、輸送機といった補給対象に合わせた運用が行われている。
燃料補給を終えT-4列機の前を連なって走るFY2FTAT,この他、500ガロン燃料補給車や2000?燃料補給車、2000ガロン燃料補給車などがあり、ヘリや練習機、戦闘機、輸送機といった補給対象に合わせた運用が行われている。
また、製造元も日野自動車、日産ディーゼル、三菱ふそうトラックバスなど多種多様である。
 中型バキュームスイーパVRS-1。
中型バキュームスイーパVRS-1。
写真は20㍉機関砲VADSの射撃展示後、滑走路を清掃しているところで、本来は異物除去に運用。エンジン部分に異物を吸い込めば航空機事故に繋がる為に導入。滑走路及び誘導路、エプロンなどの舗装部分の清掃を行う。たまに公道を自治体の同種のものが走っているが、基本的に車体もやっていることも同じである。
 航空機用2㌧牽引車2TG20。
航空機用2㌧牽引車2TG20。
車輌重量3.4㌧の小型ながら航空機を牽引する。最高速はは27km/hと決して速くはないが、この種の車両としては平均的である。基地外周道路を走っていることも多い。豊田自動織機と日産自動車が生産しており、航空機を牽引する他、弾薬輸送などにも用いる便利な車輌だ。写真は航空祭の関連器材を牽引して輸送している牧歌的な様子。後ろには帰る人々が写っている。
 航空機用3㌧牽引車3TG35.
航空機用3㌧牽引車3TG35.
入間基地で撮影したもので、写真遠景にCH-47J輸送ヘリが写っているが、C-1輸送機のような大型機が多数配備されている基地ならではの装備である。AWACSなどの大型航空機の牽引も可能で、航空自衛隊最大の牽引車である。2TG20よりも角ばっているのが外見上の特色である。 豊田自動織機社製。
 C-5電源車。神鋼電機社製のものと大阪精密電気工作所製のものがある。両社のものは重量や全高に若干の差異がある。直流28V・800Aの出力を有する。
C-5電源車。神鋼電機社製のものと大阪精密電気工作所製のものがある。両社のものは重量や全高に若干の差異がある。直流28V・800Aの出力を有する。
写真は整備員の服装を見てわかるように航空祭においてブルーインパルスのT-4練習機の整備支援に用いられているところだが、U-125級難機やMU-2救難捜索機のエンジン始動や整備用に用いられる。
 AE-3電源車。UH-60JやCH-74J、V-107といった回転翼機の始動や整備支援に用いられる。
AE-3電源車。UH-60JやCH-74J、V-107といった回転翼機の始動や整備支援に用いられる。
この他、戦闘機や偵察機に圧搾空気を送り込みジェットエンジンの始動に用いる起動車KM1(1,2,3,4とある)が航空機周辺にいることが多い。地味ながら不可欠な車輌で、陸上自衛隊でもほぼ同型の車輌が運用されていたように記憶する。
 かく座機収容器材KC200S,戦闘機などが滑走路で故障、若しくは大破した場合、これを滑走路から動かすことが基地機能維持に不可欠であるが、これを迅速に行うのがこの器材である。
かく座機収容器材KC200S,戦闘機などが滑走路で故障、若しくは大破した場合、これを滑走路から動かすことが基地機能維持に不可欠であるが、これを迅速に行うのがこの器材である。
鉄道車両を製造する日本車輌製で最大積載量は22㌧、従って自重12.97㌧のF-15Jも収容可能である、昨年その様子がマスコミに公開された。
 小牧基地航空祭において訓練展示において実際にT-1B練習機を収容しているところ、ちなみにこのT-1Bは昨年の航空祭の写真であり、この時点ではまだ現役の機体。
小牧基地航空祭において訓練展示において実際にT-1B練習機を収容しているところ、ちなみにこのT-1Bは昨年の航空祭の写真であり、この時点ではまだ現役の機体。
飛行展示の最中に実施した為、多くの観客が気付いていないところが見て取れる。小生もいつの間にか収容されていたのを気付き、慌てて望遠レンズにて撮影した。それなりに貴重な瞬間なのだが、観衆が肝心な部分を覆ってしまっている。
 以上の車両はほんの一部で、種類も区分が新旧多くあり、この他、滑走路を自前で舗装する施設器材や、降雪時に滑走路の除雪を行う器材、更に移動式管制塔や射爆場整備用の特殊車輌、レーダーサイト内での人員輸送用バス、輸送機用のカーゴローダー、アンテナ器材や移動式レーダーなどが配備されている。
以上の車両はほんの一部で、種類も区分が新旧多くあり、この他、滑走路を自前で舗装する施設器材や、降雪時に滑走路の除雪を行う器材、更に移動式管制塔や射爆場整備用の特殊車輌、レーダーサイト内での人員輸送用バス、輸送機用のカーゴローダー、アンテナ器材や移動式レーダーなどが配備されている。
流石に小生も全てを網羅できる写真はない、航空自衛隊の車輌は奥が深いのだ。
 航空祭では、カメラマンの多くはレンズを空に向けて航空機の撮影を行うが、こうした航空機は縁の下の力持ちにより支えられている。時には視線やレンズを下に向けてみてはどうだろうか。恐らく、今まで見たことのない車輌が航空機を支援していることだろう。
航空祭では、カメラマンの多くはレンズを空に向けて航空機の撮影を行うが、こうした航空機は縁の下の力持ちにより支えられている。時には視線やレンズを下に向けてみてはどうだろうか。恐らく、今まで見たことのない車輌が航空機を支援していることだろう。
HARUNA
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
■クリスマス特別企画
ここからはクリスマス特別企画、勝手に89式小銃2型!と勝手に89式短小銃!使い勝手の観点から気付いた点を反映させてあります。
 89式小銃であるが、本ブログでも先日、M-4といったエアソフトガンと比較した記事を特集した。そこで、画像補正ソフトを用いて少し遊んでみた。画像はM-4カービンのサイト部分とストックを移植した場合のモデル。小銃である為、89式はやや大きく、射手に併せて調整出来る様改良したのだが、この他、マガジンキャッチャー部分も少し下に延長し、再装填を迅速に行えるよう改良した。いわゆるコラージュ画像であるが、使いやすくなっているはずだ。
89式小銃であるが、本ブログでも先日、M-4といったエアソフトガンと比較した記事を特集した。そこで、画像補正ソフトを用いて少し遊んでみた。画像はM-4カービンのサイト部分とストックを移植した場合のモデル。小銃である為、89式はやや大きく、射手に併せて調整出来る様改良したのだが、この他、マガジンキャッチャー部分も少し下に延長し、再装填を迅速に行えるよう改良した。いわゆるコラージュ画像であるが、使いやすくなっているはずだ。
 携帯性を向上させた89式ブルパップモデル、自衛隊風に表現すれば短小銃であろうか、市街戦では長すぎる小銃は使いまわしが悪いとの指摘がある。普通に短くしてもいいのだが、あえてブルパップ。照準線が短くなるとの指摘がある為、ステアAUGのように光学照準装置を搭載している(無理やり画像を伸ばしたので無理があるのはご愛嬌)。
携帯性を向上させた89式ブルパップモデル、自衛隊風に表現すれば短小銃であろうか、市街戦では長すぎる小銃は使いまわしが悪いとの指摘がある。普通に短くしてもいいのだが、あえてブルパップ。照準線が短くなるとの指摘がある為、ステアAUGのように光学照準装置を搭載している(無理やり画像を伸ばしたので無理があるのはご愛嬌)。
以上はコラージュ画像であるので、欲しい方はプリントアウトしてカスタムショップに相談しよう!、くれぐれも豊和工業や東京マルイに問い合わせをしないようにお願いします。(本二枚のみ、著作権を一般に公開します)
北大路機関
 正月とは三箇日分の料理を御節料理として造り置いたものを食し、家庭内の労働を抑え、且つ店舗が初売りを始めるまでの間をのんびりと過ごすものである。北大路機関を更新する時間を除き、ほぼ一月初旬に予定されている発表や論文の作成、レポート執筆に費やさねばならない小生にあっても、いわば京都の味覚を楽しむくらいのせめてもの贅沢は許されてしかるべきであろう。錦の商店街は、100円均一などと比較されるご時勢に在って決して安価ではないが、平均的な支出でそれ以上のものを楽しむことが出来る。
正月とは三箇日分の料理を御節料理として造り置いたものを食し、家庭内の労働を抑え、且つ店舗が初売りを始めるまでの間をのんびりと過ごすものである。北大路機関を更新する時間を除き、ほぼ一月初旬に予定されている発表や論文の作成、レポート執筆に費やさねばならない小生にあっても、いわば京都の味覚を楽しむくらいのせめてもの贅沢は許されてしかるべきであろう。錦の商店街は、100円均一などと比較されるご時勢に在って決して安価ではないが、平均的な支出でそれ以上のものを楽しむことが出来る。 しかし、起床してみれば時間にしてはやや暗い、窓を開くと比叡山がみえないほど白さ、そして舞っているのは雪である。寒冷前線が南下中との報道には接していたが、前日に妙心寺と原谷越を実施した晴天の記憶も鮮やかであり、それは日本海側だけの話だろうと高をくくっていたが、一晩でここまで変るとは正直思いもしなかった。積雪、というほどではないが今年の初雪は舞ったというくらいに留まらず、特に北山方面では積もったという表現が相応しい雪景色である。
しかし、起床してみれば時間にしてはやや暗い、窓を開くと比叡山がみえないほど白さ、そして舞っているのは雪である。寒冷前線が南下中との報道には接していたが、前日に妙心寺と原谷越を実施した晴天の記憶も鮮やかであり、それは日本海側だけの話だろうと高をくくっていたが、一晩でここまで変るとは正直思いもしなかった。積雪、というほどではないが今年の初雪は舞ったというくらいに留まらず、特に北山方面では積もったという表現が相応しい雪景色である。 錦へは、新京極や寺町と十字路にて隣接している関係上、四条高倉や四条河原町といったバス停を利用するのが最短であるが、雪には滅法弱い地上交通網の混雑を避けるべく、京都市営地下鉄を利用した。京都駅からも北大路駅からも基本的に同じで、地下鉄烏丸線を烏丸御池駅にて東西線に乗り換え、京都市役所前駅で降り徒歩というのが妥当であろう。または少し遠いが烏丸線四条駅から阪急地下道を河原町駅へ歩いて移動するという手もある。また京阪三条駅や阪急河原町からも徒歩で行くことができる、便利なのはダイヤがしっかりしていればバス、電車ならば阪急である。
錦へは、新京極や寺町と十字路にて隣接している関係上、四条高倉や四条河原町といったバス停を利用するのが最短であるが、雪には滅法弱い地上交通網の混雑を避けるべく、京都市営地下鉄を利用した。京都駅からも北大路駅からも基本的に同じで、地下鉄烏丸線を烏丸御池駅にて東西線に乗り換え、京都市役所前駅で降り徒歩というのが妥当であろう。または少し遠いが烏丸線四条駅から阪急地下道を河原町駅へ歩いて移動するという手もある。また京阪三条駅や阪急河原町からも徒歩で行くことができる、便利なのはダイヤがしっかりしていればバス、電車ならば阪急である。 錦小路とは一言でいうものの、浄心寺から大丸裏まで実質700㍍続く商店街であり、1200㍍のアーケードが続く新京極通や寺町通ほどの長さではないが、逆にその幅は狭い。したがって、その移動は満員の電車やバスから降車するほどの労力が必要となる。電車は扉まで長くとも数㍍、バスでも後ろから前までは9㍍であるがこちらは700㍍、乗り過ごしは無いだろう、と思われるかもしれないが、こちらは目的が買い物、下手に人の流れに乗ってしまうと乗り過ごすこともある。
錦小路とは一言でいうものの、浄心寺から大丸裏まで実質700㍍続く商店街であり、1200㍍のアーケードが続く新京極通や寺町通ほどの長さではないが、逆にその幅は狭い。したがって、その移動は満員の電車やバスから降車するほどの労力が必要となる。電車は扉まで長くとも数㍍、バスでも後ろから前までは9㍍であるがこちらは700㍍、乗り過ごしは無いだろう、と思われるかもしれないが、こちらは目的が買い物、下手に人の流れに乗ってしまうと乗り過ごすこともある。 正月には栗金団やゴマメ、黒豆に昆布巻といったものは当然必要となるが、この他にやはり日本酒に合うものも必要となる。ここで鯛膾や蛸塩辛となるのだが、何分、夜半過に四条で呑んで帰るときとは異なるこの混雑、目標の店舗はどこか知っていても知らなくともさして変わりないほどの混雑に遭う、こうした中で調達予定にはなかった、お湯で戻して食する麩や湯葉などを調達したのだがここで体力の限界、西大文字町から一旦、四条通に離脱した。
正月には栗金団やゴマメ、黒豆に昆布巻といったものは当然必要となるが、この他にやはり日本酒に合うものも必要となる。ここで鯛膾や蛸塩辛となるのだが、何分、夜半過に四条で呑んで帰るときとは異なるこの混雑、目標の店舗はどこか知っていても知らなくともさして変わりないほどの混雑に遭う、こうした中で調達予定にはなかった、お湯で戻して食する麩や湯葉などを調達したのだがここで体力の限界、西大文字町から一旦、四条通に離脱した。 昼食兼朝食に丼ものを胃に収め、再度挑戦、人が多いはずで、観光ツアーのバッジを付けた人が次々と入ってきていた。それを避け小生は目的のものがありそうな区域へ瀬戸屋町から錦に入った。幾度か文字通り流されたり、間違ったりしながらも、目的のものを購入した。焼き牡蠣と日本酒の枡酒をその場のカウンターで楽しめる店を発見したが、ここでアルコールを入れては後の支障も考えられるので、牡蠣を諦めつつ、この他目的地であったジュンク堂書店に向かった。
昼食兼朝食に丼ものを胃に収め、再度挑戦、人が多いはずで、観光ツアーのバッジを付けた人が次々と入ってきていた。それを避け小生は目的のものがありそうな区域へ瀬戸屋町から錦に入った。幾度か文字通り流されたり、間違ったりしながらも、目的のものを購入した。焼き牡蠣と日本酒の枡酒をその場のカウンターで楽しめる店を発見したが、ここでアルコールを入れては後の支障も考えられるので、牡蠣を諦めつつ、この他目的地であったジュンク堂書店に向かった。 以上が錦小路への買出しの顛末である。近年ではこうした商店街も京都以外では少なくなったようだが、デパートやスーパーにての御節に更に幾品目か、今日は大晦日のまだ朝である、錦の味覚を加えてみられては如何だろうか。それでは皆さん、良いお年を!
以上が錦小路への買出しの顛末である。近年ではこうした商店街も京都以外では少なくなったようだが、デパートやスーパーにての御節に更に幾品目か、今日は大晦日のまだ朝である、錦の味覚を加えてみられては如何だろうか。それでは皆さん、良いお年を!