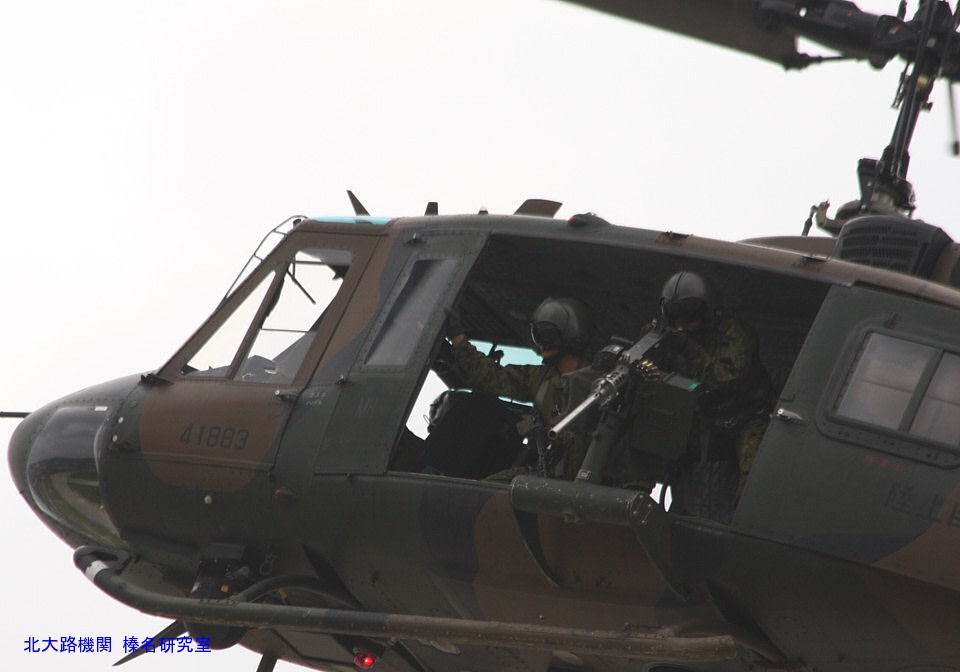◆US-2救難飛行艇輸出へ
インド国防省が26日に発表したところによれば、インド海軍が新しく導入する飛行艇に海上自衛隊が運用する救難飛行艇US-2が導入する方針が固まった、とのこと。

インド軍の装備調達は、二転三転し、いったん決定した命題についても変更することが時としてあるため一概に決定と記す事は出来ないのですが、インド海軍は海上自衛隊が運用する新明和US-2と、ロシアのベリエフBe-200を比較検討し、荒天海域での離発着能力の面でUS-2が優れており、結果的にUS-2が選定されたとのことで、機種は決定していなかったものの飛行艇導入の砲身あ固まっており、これを以てUS-2が実際に輸出される可能性がほぼ決定したといえるでしょう。

US-2は、3mから最大5m前後の波浪海面でも離水280m着水310mで運用した実績が多く、荒天時に運用される飛行艇としては世界最高性能を有しています、これは我が国周辺では波浪時の遭難事故が少なくなく、この際に運用できる性能が求められたためなのですが、ロシアのベリエフBe-200はジェット飛行艇として進出速度の大きさが特色ですが滑走距離が離水1000m及び着水1300mと長く、1.2m以下の波浪時の運用が前提、しかも離着水速度が非常に早いため波浪海域では転覆の危険性が高まり、洋上での運用能力ではUS-2が優れています。

US-2の難点は取得費用が非常に高い点で、インドではライセンス生産を希望しています。人件費の安さから取得費用が提言する可能性はあるのですが、治具調達費用は高く全体としてどうなるかは未定です。他方インド海軍は十数機の調達を計画しているとされ、新明和工業が生産した場合、自衛隊向けの機体を含め毎年1機の製造が限界、新工場を建設するか、2年で3機の生産程度ならば考えられるようですが、大量生産には完納後というリスクがあり、この点の調整が今後の課題になってくるでしょう。防衛装備品の輸出としては現時点で史上空前の規模となりそうで、今後とも注視したい命題です。
北大路機関:はるな
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
インド国防省が26日に発表したところによれば、インド海軍が新しく導入する飛行艇に海上自衛隊が運用する救難飛行艇US-2が導入する方針が固まった、とのこと。

インド軍の装備調達は、二転三転し、いったん決定した命題についても変更することが時としてあるため一概に決定と記す事は出来ないのですが、インド海軍は海上自衛隊が運用する新明和US-2と、ロシアのベリエフBe-200を比較検討し、荒天海域での離発着能力の面でUS-2が優れており、結果的にUS-2が選定されたとのことで、機種は決定していなかったものの飛行艇導入の砲身あ固まっており、これを以てUS-2が実際に輸出される可能性がほぼ決定したといえるでしょう。

US-2は、3mから最大5m前後の波浪海面でも離水280m着水310mで運用した実績が多く、荒天時に運用される飛行艇としては世界最高性能を有しています、これは我が国周辺では波浪時の遭難事故が少なくなく、この際に運用できる性能が求められたためなのですが、ロシアのベリエフBe-200はジェット飛行艇として進出速度の大きさが特色ですが滑走距離が離水1000m及び着水1300mと長く、1.2m以下の波浪時の運用が前提、しかも離着水速度が非常に早いため波浪海域では転覆の危険性が高まり、洋上での運用能力ではUS-2が優れています。

US-2の難点は取得費用が非常に高い点で、インドではライセンス生産を希望しています。人件費の安さから取得費用が提言する可能性はあるのですが、治具調達費用は高く全体としてどうなるかは未定です。他方インド海軍は十数機の調達を計画しているとされ、新明和工業が生産した場合、自衛隊向けの機体を含め毎年1機の製造が限界、新工場を建設するか、2年で3機の生産程度ならば考えられるようですが、大量生産には完納後というリスクがあり、この点の調整が今後の課題になってくるでしょう。防衛装備品の輸出としては現時点で史上空前の規模となりそうで、今後とも注視したい命題です。
北大路機関:はるな
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)