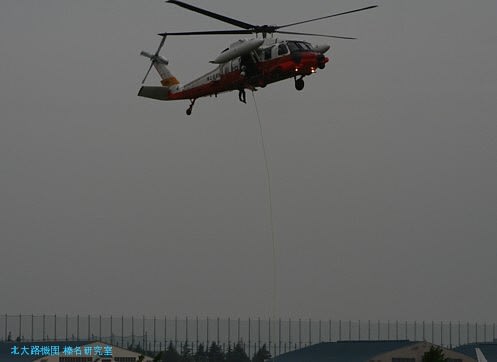■練習艦隊名古屋寄港の日
30日2330時頃、Weblog北大路機関はアクセス解析開始から31万アクセスを突破しました。ありがとうございました。さて、名古屋港に海上自衛隊の練習艦隊が寄港した当日、入港の様子を撮影した後、小生はジョニー氏の愛車にて艦艇見学のために名古屋港に便乗させていただいた。
 今回は、その道中に立ち寄った名古屋臨海鉄道の貨物列車とディーゼル機関車の写真を掲載したい。なんでも、ここで運用される旧国鉄DD13型ディーゼル機関車は今日的には数少ない貴重なものだとか。そもそも、ディーゼル機関車自体、京都界隈の路線では貨物輸送を含めてお目にかかれないので、そういった意味で小生には珍しいものである。
今回は、その道中に立ち寄った名古屋臨海鉄道の貨物列車とディーゼル機関車の写真を掲載したい。なんでも、ここで運用される旧国鉄DD13型ディーゼル機関車は今日的には数少ない貴重なものだとか。そもそも、ディーゼル機関車自体、京都界隈の路線では貨物輸送を含めてお目にかかれないので、そういった意味で小生には珍しいものである。
 名古屋臨海鉄道は、名古屋東港地区における貨物輸送を一手に引き受ける会社で、旅客輸送は行っていないとのこと。かつては、名鉄線を利用し、国鉄線から乗り入れていたのだが、名鉄線の旅客輸送量の増加と高度経済成長に伴う貨物輸送量の増大により、独立した貨物路線の必要性が認識されたことが背景にある。
名古屋臨海鉄道は、名古屋東港地区における貨物輸送を一手に引き受ける会社で、旅客輸送は行っていないとのこと。かつては、名鉄線を利用し、国鉄線から乗り入れていたのだが、名鉄線の旅客輸送量の増加と高度経済成長に伴う貨物輸送量の増大により、独立した貨物路線の必要性が認識されたことが背景にある。
 名古屋臨海鉄道と名鉄築港線は平面交差の部分があり(むかしの阪急神戸線西宮北口駅のような印象)、名鉄ファンにはこの部分で有名なのかな、と思ったり。貨物駅ということで、石灰などの輸送車輌や燃料など液体貨物を運搬する車輌などが並んでいる。日曜日ではあるが、この日も貨物輸送を実施していた。
名古屋臨海鉄道と名鉄築港線は平面交差の部分があり(むかしの阪急神戸線西宮北口駅のような印象)、名鉄ファンにはこの部分で有名なのかな、と思ったり。貨物駅ということで、石灰などの輸送車輌や燃料など液体貨物を運搬する車輌などが並んでいる。日曜日ではあるが、この日も貨物輸送を実施していた。
 DD13型ディーゼル機関車。正確にはND552型と呼称するらしい。
DD13型ディーゼル機関車。正確にはND552型と呼称するらしい。
車体前部のヘッドライトは一つ目型で、これが今日的には貴重なんですよ、とC.ジョニー氏。臨海鉄道に相応しい海をおもわせるスカイブルーの車体が眩しい。
 この名古屋臨海鉄道は、名古屋港港湾組合と国鉄が出資した珍しい経緯があり、操業は1965年、パノラマカー登場のあとという鉄道会社である。トヨタ自動車の部品を専用に運ぶ列車などもあり、貨物基地であり車輌基地ならではの喧騒と活気が冬の寒空にほの暖かい印象を撮影する我々にも与えてくれる。
この名古屋臨海鉄道は、名古屋港港湾組合と国鉄が出資した珍しい経緯があり、操業は1965年、パノラマカー登場のあとという鉄道会社である。トヨタ自動車の部品を専用に運ぶ列車などもあり、貨物基地であり車輌基地ならではの喧騒と活気が冬の寒空にほの暖かい印象を撮影する我々にも与えてくれる。
 安全第一の標語を背景に無線で指示を飛ばす係員。貨物基地では何度も見た光景であるが、無線一つで片手を機関車に預け、自動化が如何に進もうと必要な熟練機関区員。微調整を行うその姿は陸の船乗り、といった印象。車体番号をみると、DD13ではなくND5527という文字が見える。
安全第一の標語を背景に無線で指示を飛ばす係員。貨物基地では何度も見た光景であるが、無線一つで片手を機関車に預け、自動化が如何に進もうと必要な熟練機関区員。微調整を行うその姿は陸の船乗り、といった印象。車体番号をみると、DD13ではなくND5527という文字が見える。
 幾つか見ることが出来た車輌。DD13と書かれた車両もあったようだ。車体の整備具合から推測して廃棄車輌なのだろうか。この車体は見慣れた旧国鉄塗装で、背景の工場群や煙突と併せ、ここだけがまだ昭和の匂いを感じることが出来る。ちなみに、このDD13系列は、C.ジョニー氏によれば除雪用などでJRでも僅かに残っているとの事。
幾つか見ることが出来た車輌。DD13と書かれた車両もあったようだ。車体の整備具合から推測して廃棄車輌なのだろうか。この車体は見慣れた旧国鉄塗装で、背景の工場群や煙突と併せ、ここだけがまだ昭和の匂いを感じることが出来る。ちなみに、このDD13系列は、C.ジョニー氏によれば除雪用などでJRでも僅かに残っているとの事。
 今回の撮影には当然ながら、車輌基地の外から撮影した。一段低いところに道路が走っており、見上げるような車輌のアングルを撮影することができる。一行が撮影している最中にも脚立持参で撮影を行われている方もいた。フェンスの向こうの車輌基地、車体はやや古いが、活気は今尚現役の車輌そのものである。
今回の撮影には当然ながら、車輌基地の外から撮影した。一段低いところに道路が走っており、見上げるような車輌のアングルを撮影することができる。一行が撮影している最中にも脚立持参で撮影を行われている方もいた。フェンスの向こうの車輌基地、車体はやや古いが、活気は今尚現役の車輌そのものである。
HARUNA
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)