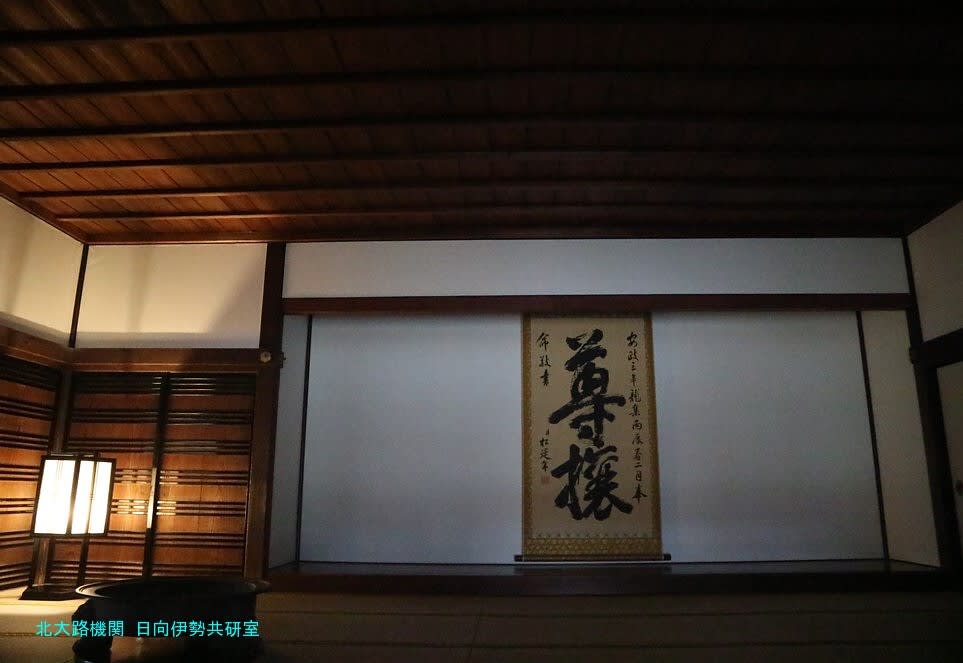■99式自走榴弾砲300両集約案
99式自走榴弾砲と火力戦闘車を僅か300門へ集約される陸上自衛隊野戦特科部隊ですが、300門の定数を前に最新鋭装備を二系統とする点に、少々疑問を感じます。

99式自走榴弾砲と火力戦闘車を比較する場合、自動装填装置を有さない火力戦闘車は瞬発射撃能力も持続射撃能力も火砲として優位性がありません。勿論安価に収めているのですから大量生産し479両を導入したFH-70榴弾砲の後継として500門近くを導入するならば、安価という点は重要ですが、自衛隊は火砲定数を将来的に300門程度とする方針です。

火力戦闘車に先行する装輪式自走榴弾砲としてフランス製カエサル軽自走榴弾砲があります。自動化を操砲系統とするのではなく人力装填を軸とした半自動装填装置に留め、砲兵情報装置等の装備に留めたトラック式自走砲でした。この延長線上に火力戦闘車を望見した場合、自動装填装置を省く設計はカエサルという先行者に妥当性がある様にも感じます。

カエサル自走榴弾砲について。しかし2018年ユーロサトリ国際兵器見本市に展示された最新型のカエサル自走榴弾砲は自動装填装置を備え車内から装填作業を行えるようになりました。カエサル自走榴弾砲は機甲師団へも配備が開始されており、結果的に自動装填装置を欠いて砲兵が直接車外での弾薬装填や操砲作業を行うという運用が厳しくなった構図だ。

アーチャー自走榴弾砲というスウェーデン製装輪自走榴弾砲は、自動装填装置を標準装備し、砲兵はボルボ製装甲トラックの戦闘室から射撃統制を行う事が可能です。カエサルは此れと比べ簡易型という構図でしたが、自動装填装置の採用によりアーチャーに寄った構図だ。アーチャーは言い換えれば装軌式自走榴弾砲の砲塔をトラックに積んだ様なもの。

99式自走榴弾砲は一応生産ラインがまだ残っています、ですから火力戦闘車か99式自走榴弾砲か、という選択肢を日本は取り得るのです。しかし、スウェーデンは装軌式のバンドカノン自走榴弾砲生産は終了、フランスもAMX自走榴弾砲製造が終了しており、今あるものしか選択肢が無い構図です。対して、日本には選択肢が二つある、これは重要でしょう。

戦略機動性を考えた場合、99式自走榴弾砲は40tの装軌式車両であるため、74式戦車のように戦車輸送車に積載し輸送しなければなりません。中砲牽引車で高速道路を疾走できるFH-70と比較したならば鈍重な印象は否めないでしょう。しかし、火砲の数が限られると同時に、陸上自衛隊には火砲以外の有力な選択肢があります、警戒さが必要なものに限る。

即応機動連隊という自衛隊に新しい緊急展開部隊が創設され、軽快な120mm重迫撃砲RTを装備する火力支援中隊を隷下に置く編成の部隊があるため、初動は即応機動連隊に重点を置く、という運用は当然考えられるでしょう。それならば主力が99式自走榴弾砲であって駄目、という理由にはなりません。即ち、120mm重迫撃砲RTと協同すればよいのです。

西部方面特科連隊、それでは戦時中の旧陸軍のように155mm榴弾砲は軍砲兵隊の虎の子装備なのか、と問われますと、実態は管理部隊は方面隊ですが、西部方面隊の場合は担当大隊として第4師団担当の特科大隊、第8師団担当の特科大隊を師団へ配属している方式です。この方式、第8師団に96式多目的誘導弾システムが配置されていた事例があります。

現在の第14旅団にも中部方面特科隊が置かれている。管理者が変わっただけで所属は基本的に同じ、という構図から理解すると、見方が変わってくるでしょう。したがって、99式自走榴弾砲に本土特科を統合した場合には、師団へ配属の特科大隊に99式自走榴弾砲が配備されることとなる。車体は巨大ですが高性能、この威力は際立って大きなものがある。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)
99式自走榴弾砲と火力戦闘車を僅か300門へ集約される陸上自衛隊野戦特科部隊ですが、300門の定数を前に最新鋭装備を二系統とする点に、少々疑問を感じます。

99式自走榴弾砲と火力戦闘車を比較する場合、自動装填装置を有さない火力戦闘車は瞬発射撃能力も持続射撃能力も火砲として優位性がありません。勿論安価に収めているのですから大量生産し479両を導入したFH-70榴弾砲の後継として500門近くを導入するならば、安価という点は重要ですが、自衛隊は火砲定数を将来的に300門程度とする方針です。

火力戦闘車に先行する装輪式自走榴弾砲としてフランス製カエサル軽自走榴弾砲があります。自動化を操砲系統とするのではなく人力装填を軸とした半自動装填装置に留め、砲兵情報装置等の装備に留めたトラック式自走砲でした。この延長線上に火力戦闘車を望見した場合、自動装填装置を省く設計はカエサルという先行者に妥当性がある様にも感じます。

カエサル自走榴弾砲について。しかし2018年ユーロサトリ国際兵器見本市に展示された最新型のカエサル自走榴弾砲は自動装填装置を備え車内から装填作業を行えるようになりました。カエサル自走榴弾砲は機甲師団へも配備が開始されており、結果的に自動装填装置を欠いて砲兵が直接車外での弾薬装填や操砲作業を行うという運用が厳しくなった構図だ。

アーチャー自走榴弾砲というスウェーデン製装輪自走榴弾砲は、自動装填装置を標準装備し、砲兵はボルボ製装甲トラックの戦闘室から射撃統制を行う事が可能です。カエサルは此れと比べ簡易型という構図でしたが、自動装填装置の採用によりアーチャーに寄った構図だ。アーチャーは言い換えれば装軌式自走榴弾砲の砲塔をトラックに積んだ様なもの。

99式自走榴弾砲は一応生産ラインがまだ残っています、ですから火力戦闘車か99式自走榴弾砲か、という選択肢を日本は取り得るのです。しかし、スウェーデンは装軌式のバンドカノン自走榴弾砲生産は終了、フランスもAMX自走榴弾砲製造が終了しており、今あるものしか選択肢が無い構図です。対して、日本には選択肢が二つある、これは重要でしょう。

戦略機動性を考えた場合、99式自走榴弾砲は40tの装軌式車両であるため、74式戦車のように戦車輸送車に積載し輸送しなければなりません。中砲牽引車で高速道路を疾走できるFH-70と比較したならば鈍重な印象は否めないでしょう。しかし、火砲の数が限られると同時に、陸上自衛隊には火砲以外の有力な選択肢があります、警戒さが必要なものに限る。

即応機動連隊という自衛隊に新しい緊急展開部隊が創設され、軽快な120mm重迫撃砲RTを装備する火力支援中隊を隷下に置く編成の部隊があるため、初動は即応機動連隊に重点を置く、という運用は当然考えられるでしょう。それならば主力が99式自走榴弾砲であって駄目、という理由にはなりません。即ち、120mm重迫撃砲RTと協同すればよいのです。

西部方面特科連隊、それでは戦時中の旧陸軍のように155mm榴弾砲は軍砲兵隊の虎の子装備なのか、と問われますと、実態は管理部隊は方面隊ですが、西部方面隊の場合は担当大隊として第4師団担当の特科大隊、第8師団担当の特科大隊を師団へ配属している方式です。この方式、第8師団に96式多目的誘導弾システムが配置されていた事例があります。

現在の第14旅団にも中部方面特科隊が置かれている。管理者が変わっただけで所属は基本的に同じ、という構図から理解すると、見方が変わってくるでしょう。したがって、99式自走榴弾砲に本土特科を統合した場合には、師団へ配属の特科大隊に99式自走榴弾砲が配備されることとなる。車体は巨大ですが高性能、この威力は際立って大きなものがある。
北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ
(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)
(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)
(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)