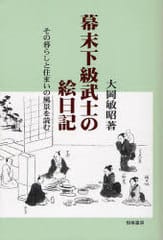画像は相模書房から出ている大岡敏昭著「幕末下級武士の絵日記」である。銀座を歩いていたら相模書房(銀座2丁目)という出版社があった。その出版社の事務所のドアの横にこの本のポスターが掲げてあり、それを見て「面白そうだ」と思い、事務所の中に入って「これちょうだい」と言って買って来た。衝動買いである。この本の内容はタイトルどおりで、ある武士の絵日記に書かれたその生活ぶりを追いながら、大岡氏がそれを解説するものだ。その武士はせっせと暇な生活を絵日記に綴っているが、現代に生きていたなら熱心な「ブロガー」になっていたことだろう。この本の中で私が関心を最も強く持って読んだのは、「5章 中下級武士の住まい」である。住宅史が専門の大岡氏らしい記述が続くのだ。
大岡氏はこの本の中で、現代の住宅と対比させ当時の住宅のつくりを解説している。我が西武七里ガ浜住宅地もそうだが、現代の住宅街では、道路に接するのが東西南北のどの方向の敷地であっても、その敷地の中で建物を北に寄せて建てるのが一般的である。可能な限り南を開けようとする「南至上主義」である。住宅街の中で東西方向の道路に面した敷地に並ぶ家々は、道路を挟んで対照的な風景を見せる。南側で道路に接する開放的な並びに比較し、北側に道路がある並びでは、敷地内で道路側に寄せて建てられた家がほとんどなので、道路から見てアプローチ・デザインにあまり余裕がない区画が多い。また建物外壁に、水周り(風呂、台所、トイレ、洗面)や階段の踊り場などに用いられる小さくて形状が異なる窓が不規則な高さにバラバラと並べられている。場合によってはそこに給湯器や計器類が並んでいたりもするのである。
すでにこのブログで書いたことだが、原因は二つあるだろう。
● 南至上主義
● 景観の公共性という概念の希薄さ
しかし、そんなに南を優先するのはなぜなのだろうか。また道路から見えるのは家の顔ともいうべきものなのに、それをないがしろにするのはなぜなのだろうか。日本よりもはるかに日照条件の厳しい冷涼な気候の国の住宅ですら、方角には関係なく、道路に向けて美しいデザインを見せるように普通は努力して作られている。また建築において採光は重要なポイントだろうが、南からの採光がすべてではないはずだ。
さらに自分の家にとって周囲の家並みが重要なのと同じに、自分の家も周囲と溶け合い家並みをつくる一要素であるからして、道路に面しているにもかかわらず、建物北側がどうでもいいような「捨てた」デザインになってしまうことは、住宅街全体の景観にとってもあまり好ましいことではない。
著者大岡氏の文章を部分的に引用する:
中下級武士の住まいには・・・北入り、南入り、東入り、西入りのいずれの方位の宅地入口であっても・・・住宅の正面を道側に向け、その方向に広く開口し、道と住まいの関係は多少の門と塀があっても開放的な雰囲気であった。方位よりも道を重視していたのである・・・道に広くひらかれた住まいは、外からやってくる人たちを大切にする考えでつくられていたと言える。そしてこの共通の考えで建てられた住まいの町並みには、多少の外観の違いはあっても統一感のある落ち着いた趣の景観があった。現在残る古い町並みが景観的にも優れ、われわれの心をなごませるのは、このような統一されたつくり方にある・・・ところが現代の住まいはこのようなつくり方とは大きく異なっている。それは東西南北、いずれの宅地入口の住まいにおいても建物は南側を広く空けて北側に詰めている。道から見れば・・・北入りの住まいは道のある北に建物を詰めているために閉鎖的で圧迫された雰囲気である・・・現代の住まいは南方位を偏重・・・とくに北入りの住まいを始めとして、東入り、西入りの住まいも近隣社会とつながる道に背を向けた構え方である。道と住まいの関係が非常に閉鎖化し・・・このような道に背を向けた住まいの町並みは、なにか圧迫された感じをもたらし、統一感のない景観になっている。
日本の住宅が「南至上主義」、「北寄せ建築」となったのは、明治以降のことなのだそうだ。